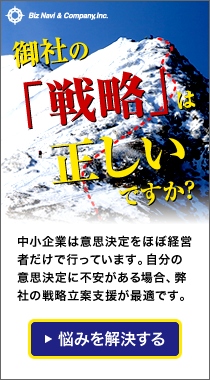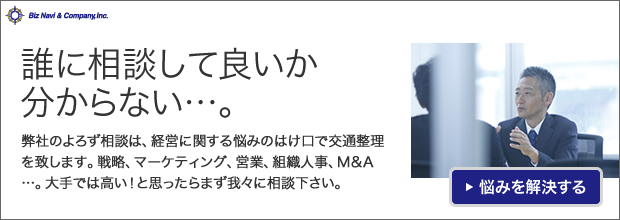早嶋です。約6600文字。
DXは企業の中では当たり前に浸透した。ただ、それは言葉として浸透しているだけで、本来の概念的な、理想的な取組は未着手、未実現のままだ。多くの企業が「DX推進室」をつくり、AIを導入し、業務を自動化し、ペーパーレス化を進める理想を持っている。しかし、その成果はどうだろうか。確かに一部では効率が上がり、コストは削減され、生産性も向上している。だが、なぜか手応えが薄い。組織が強くなった実感が乏しいし、SNSなどで見る劇的な変化は感じない。競争優位が決定的になったという声などに至っては皆無だ。
DXをコスト削減の延長線上に置いた組織は、往々にして部分最適に終わる。現場の困りごとをAIで解決し、業務時間を短縮し、人員を削減する。確かに合理的だ。しかし、その合理化は思想を伴っていない。データとデータの因果を理解し、事業全体の構造を深く掘り下げるための仕組みになっていないのだ。
一方で、DXを競争優位の源泉と捉えた組織は様相が異なる。彼らはデータを削コスト減目的で使用しない。物事の因果を探り、構造を読み、全体を理解するために使う。なぜこの部門の売上が上がったのか。その背後にある投資は何か。どの部門が支え、どの過去の意思決定が現在を生んだのか等。問いと探求は自然と広がり、事業運営を強化する思考は縦にも横にも伸びていく。
今回の命題は、DXはITプロジェクトではなく、思想である、だ。
そしてさらに踏み込めば、DXは組織を強くもするが、同時に弱くする側面がある。効率化だけを追えば、人は物事の因果を考えなくなる。ブラックボックス化された仕組みで成果だけを得られるからだ。結果、文明の果実を当然とみなす人間が増えるのだ。だが、因果を可視化し、構造を理解させる仕組みとしてDXを使えば、結果的にDXは人の精神の質をも高める道具になるのだ。
(DXの本質:可視化と大衆化)
では、DXの本質とは何だろう。効率化のツールか、それとも依存構造を可視化する仕組みだろうか。そもそも経済活動で得られた様々なデータは、コスト削減のための道具と捉えて良いのだろうか。それとも、それらを活用して、物事の因果理解を行いより競争優位を獲得するために活用すべきだろうか。
ここで、少し異なる分野の話をしたい。20世紀初頭、スペインの哲学者、ホセ・オルテガ・イ・ガセット は、『大衆の反逆』の中でこう述べた。近代文明は人類の苦闘の末に築かれた成果である。しかし、その過程を知らない世代は、その文明を当然のものとみなし始める。水は蛇口から出る。電気はスイッチで点く。社会は安全である。すべてが当たり前になる。
問題は文明そのものではない。その文明の果実を当然視する人間の態度だ。
彼が言う「大衆」は数の問題ではない。自分に高い要求を課さず、成果だけを享受する人間の精神状態を指している。この視点でDXを見直してみる。もしDXがブラックボックスを増やす方向に進めばどうなるかだ。業務は自動化され、意思決定はアルゴリズムに委ねられ、現場はボタンを押すだけになる。効率は上がるし、考える必要がなくなる。しかし、物事の因果や構造的なメカニズムなどは全く見えなくなると思う。なぜこの数字が上がったのか。なぜこのコストが下がったのか。なぜこの顧客に気に入られているのか。その背後にある構造や歴史、他部門の支えは自然と意識されなくなるのだ。
そのとき組織の中で起きるのは、オルテガが言う大衆化だ。組織の成果は自分の能力と誤認され、組織や利害関係者間の協力や支え合う構造は忘れられ、相互に依存している仕組みは見えなくなる。そう、文明の果実だけを食べる人間が増えていくのだ。
しかし逆も考えられる。DXを因果関係や物事の構造を可視化する装置として設計した場合だ。売上の背後にある投資や行動が見え始める。1つの業務改善が他部門に与える影響が具体的に見え始める。過去の意思決定が現在の競争力にどのような影響を与えたかが分かり始める。従来のブラックボックスが構造として理解できるようになるのだ。
その瞬間、DXは効率化ツールから思考するための道具に変わる。互いの構造や因果関係が具体的に可視化されることで、自分が組織全体の一部であるという自覚が生まれる。そう、依存構造、つまり見えなかった相互協力の連鎖を理解することで、精神は成熟するのだ。
少し簡単な比喩で説明しよう。仕事仲間で、キャンプに行ったとしよう。これまでリーダー的な存在で仕事が出来た人も、料理を作ることも、火を起こすこともできないかも知れない。そんな時、雑務を担当してくれた方が、料理の手際を見せる。他の仲間はできることを探し、薪を探し、火を起こす。テントを張って野営の準備をする人も出るだろう。キャンプをすると、互いに行動が可視化された中で、同時並行的に作業が進む。出来ない人は自然とできる人のフォローに入り、不足する機能を見つければ、誰かが工夫をして環境を整える。互いの相互関係が見え、各自の仕事の因果がわかれば、自立よりも相互依存による結果、成り立つことを理解できるのだ。
仕事に置き換えても同じだ。依存構造、つまり相互関係の構造と理解があれば、人は自然と役割を引き受ける。しかし、全てがブラックボックス化され、他の動きが見えない空間にいる人は自覚がなく、自分の成果だと当然視するのだ。
これがDXの分岐点だ。DXは組織を強くもするが、同時に弱くもする。ブラックボックスを増やせば大衆化を促進する。因果を見せれば成熟を促進するのだ。そのため、DXの本質は技術ではない。それをどう使うかという思想だ。
(共同体の視点)
ここで、更に別の話をして視点を拡げたい。DXを効率や因果の話にとどめるのではなく、「人間とは何か」という地点まで引き上げてみる。
イスラエルの歴史学者であるユヴァル・ノア・ハラリ は、人類史を俯瞰する中でこう述べている。ホモ・サピエンスが生き残ったのは、身体能力が突出していたからではない。集団で協力し、経験や知識を共有し、物語を信じることができたからだ、と。強い個体が勝ったのではない。弱い個体が、協働によって強くなった種が残った、と。
つまり人間は、単体最適で設計された存在ではないのだ。共同体の中で役割を持ち、互いに依存しながら生きるようにできている。この視点から企業や組織を見ると、多くのことが腑に落ちる。
例えば、銀行口座を考えてみたい。あなたの口座に表示されている残高は、物理的にどこかに積まれている現金ではない。単なる数字であり、データであり、記号だ。しかし私たちはその数字を疑わない。ATMに行けば現金が出てくると信じているし実際に出てくる。だが、その背後には巨大な信用ネットワークがあり、中央銀行、商業銀行、決済システム、法律、監査制度、国家の信用力等々が連鎖している。この制度と人々の合意連鎖が「残高」という数字を成立させている。
ハラリ は、人類が他の種より優位に立てた理由を「虚構を共有する力」に見出した。国家も、貨幣も、会社も、法律も、物理的実体ではない。人々がそれを信じるという合意の上に成り立つ「物語」だという。
会社も同じだと思う。法人という存在は、建物でも機械でもない。人々が「この会社は存在する」と信じ、契約を結び、取引をし、従業員が働き、顧客が支払うことで初めて成立する。会社とは、共有された物語の集合体にすぎない。しかし私たちは、ATMから出てくる現金だけを見るように、売上や利益という数字だけを見るようになる。背後にある信用の連鎖や、過去の投資や、他部門の支え合いの構造には思いを巡らせることを忘れてしまう。
近代技術は、この「依存の網」を見えにくくしている。水は蛇口から出る。電気はスイッチで点く。組織では給料は毎月振り込まれる。自分が何かをしなくても、すぐには困らない。責任と結果の距離がうんと遠くなったのだ。しかし実際は複雑な依存があるのだが、その構造が見えない状態が続いているのだ。これが文明の裏側だ。
企業も同じだ。1つの部門の売上は、他部門の投資や支援の上に成り立っている。1つの成功は、過去の失敗の蓄積の上にある。しかし、その連鎖は日常業務の中では見えにくいし、知らなくても仕事ができる。組織は、仕事の流れ(バリューチェーン)や会社間の連携(サプライチェーン)を意識しなくても良い仕組みを作った。組織を細分化して、一部の役割を切り取り、そこに更に標準化してコピペしても動けるような工夫をしている。
ここにDXが加速すると、更に自動化が進み、ブラックボックスを増やすことも容易だ。ますます依存構造が見えなくなる。人は自分の成果を自分の能力と誤認する。共同体的自覚は薄れるのだ。しかし、DXは構造を可視化するための仕組みとして認識するとどうだろう。売上と投資の連鎖が見え、部門間の因果が見える。その結果、優位性を加速するための意思決定と結果の距離がぐんと縮まるのだ。思想を実現する道後としてDXを活用することで、企業は単なる機能の集合体から、再び共同体として立ち現れる。
DXは効率化の道具にもなるし、共同体を再構築する道具にもなり得るのだ。ここに、経営の覚悟が問われる。
(組織と期限付きトップの問題)
ここまで述べた共同体の視点を、現実の組織運営に引き寄せてみたい。私はグループ会社の経営に関わることが多い。そこでは親会社から数年単位で社長が派遣されるケースが少なくない。2年から3年という任期の中で成果を求められ、評価は多くの場合、親会社の基準で下される。
この構造は何を生むだろうか。
任期付きトップは、無意識のうちに「キャリア最適化」に向かうだろう。短期的な数値改善、目に見える改革、リスクの回避。次のポストへ進むための合理的行動だ。これは個人の善悪の問題ではない。制度がそう設計しているのだ。
実は、いわゆる「プロ経営者」も同じ構造の中だ。特定の企業に数年間入り、劇的な改革を行い、成果を出し、次のステージへ進む。PEファンド主導の経営、VC主導の経営もまた、時間制約の中で成果を求められる。そこではどうしても、短期で可視化できる成果に重心が置かれる。
それ自体が悪いわけではない。むしろ合理的だ。しかし問題は、時間制約が「全体最適」と「歴史の継承」を分断しやすい点にある。企業は本来、過去の蓄積の上に現在があり、現在の判断の上に未来がある存在だ。だが時間を区切られた経営は、どうしても現在の成果を最大化する方向に傾きやすい。土壌を耕すよりも、収穫を急ぐイメージだ。
ここに共同体最適との緊張関係が生まれるのだ。繰り返すが、企業は、過去の投資の上に現在があり、現在の判断の上に未来がある。1つの部門の成功は、他部門の支え合いの結果で、1つの決断は、後任者が引き受ける重みを持つ。任期付きであれ、その企業は「通過点」ではない。誰かの終の場所であり、誰かの生活の基盤であり、誰かの人生の舞台なのだ。
この視点で捉えると、キャリアの最適化か、と共同体の最適化か、という分岐が見えてくる。短期的に見栄えのする改革を行うことと、組織の土壌を耕すことは必ずしも一致しない。数字を改善することと、構造を強くすることも一致しない。
オルテガは「大衆」とは数の問題ではないと言った。問題は態度だ。自分に高い要求を課さず、成果だけを享受する姿勢こそが危ういのだと。彼の言う「貴族的精神」とは身分のことではない。自らを律する態度のことだ。それは、自分の任期中の評価だけを考えて意思決定することではない。自分が去った後の組織がどうなるかまで考えて判断することだ。それは、成果を自分の手柄にすることではない。その成果を支えた人や過去の投資に思いを巡らせることだ。それは、昇進や評価のために数字を整えることではない。見えにくいリスクや構造の弱さを引き受けることだ。つまり、共同体の未来に対して、自分の判断がどう影響するかを自覚し、その重みを引き受ける態度である。
DXも同じだ。
DXを短期的な効率改善の道具として使えば、任期中の成果は出るかもしれない。しかしブラックボックスが増え、依存構造が見えなくなれば、次世代はその重みを引き受けることになる。一方で、DXを構造を可視化し、因果を共有し、組織の土壌を強くする装置として使えばどうだろう。それは任期を超えて効いてくるはずだ。
ここで初めて、DXはIT施策から精神設計へと変わるのだ。経営とは、数字を動かすことではない。精神の質を設計することだ。任期があるかどうかは本質ではない。その組織を「通過点」と見るか、「引き受ける場所」と見るか。その差が、DXの使い方を決定するのだ。
(思想設計としてのDX)
ここまで述べたように、DXは単なる効率化の道具ではない。共同体の構造を可視化する仕組みで、その結果企業の競争優位の源泉になる。ここでは、思想までを組織に以下に実装するかについて整理する。
DXを思想として捉えると、現在の組織に対して新たにインストールすべく方針がいくつか見えてくる。
1. 責任と結果の距離を縮める
近代組織の最大の課題は、責任と結果の距離が遠くなったことだと思う。自分の判断がどの数字にどう跳ね返るのかが見えにくいのだ。だからこそ、DXを用いて意思決定と成果を結びつけるのだ。
実際は、小集団でのリーダー経験、プロジェクト単位での収支責任、KPIと現場行動の連動などがイメージしやすいと思う。データを通じて「自分の判断がどこに影響したか」を可視化出来れば、責任が数字に、数字が現実に結びつく感覚を体験できる。それを実装するのだ。
責任と結果が近づけば、人は自然と慎重になり、同時に主体的になるものだ。
2. 全体構造の理解と訓練
DXの最大の可能性は、因果を横断的に見せられる点にある。売上の裏にある投資。コスト削減の裏にある品質リスク。一部門の成果が他部門に与える波及等。
単なる経営ダッシュボードでは足りない。事業構造を可視化し、ビジネスモデルの本質を理解する。そして、常に、「この数字はどこから来たのか」「この改善はどこに影響するのか」を問い続ける組織文化をつくるのだ。
DXはデータの集約をしてコストを削減するツールではない。構造の可視化の上、新たな価値創造をするための道具なのだ。
3. 疑似キャンプ
企業の中では、仕事の役割が細分化され、標準化され、欠席しても他者に代替可能な状態を構築している。これは効率のために必要だが、共同体的自覚を弱める側面もある。
だからこそ、意図的に役割の重なりや相互依存を体験させる場が必要だ。クロス部門プロジェクト、短期集中の事業開発、ハッカソン、合宿型の戦略立案。そこでは「自分が動かなければ進まない」という状況を擬似体験させ、日常の思考回路に定着させることを狙う。
4. 歴史を語る
組織が弱くなる最大の原因は、歴史の忘却だ。過去の投資、失敗、転機、葛藤。それらが語られなくなったとき、忘れた時、現在の成果は当然視される。文明の果実を当然とみなす態度が組織内に広がれば大衆を増産する。
DXを使えば、過去の意思決定と現在の成果をつなげられる。投資履歴、事業の変遷、組織の進化を可視化する。数字の背後に物語を取り戻すのだ。
(DXの再定義)
最後に、敢えて、もう一度DXを定義し直してみる。DXはITプロジェクトではないし、業務改善のスローガンであってもいけない。DXは、組織の事業マインドを可視化させる仕組みそのものなのだ。責任を見せ、依存を見せ、構造を見せ、歴史を見せる。
今回の議論での、はじめの分岐はこうだった。DXを効率化に使うか、因果を理解するために使うか。後者を選んだとき初めて、DXが競争優位の源泉にあり得る。だがここで終わる組織が多い。因果関係は理解したと言って安心してしまうのだ。
だから2つ目の分岐点が生まれる。理解で止まるか、行動に落とし込むかだ。ダッシュボードで満足するか、悲母日の意思決定が変わり行動が変わるまで設計するかだ。
DXを文明の果実として消費するだけなら、人は大衆化する。組織を共同体として成熟させる仕組みとして設計し、実装する。その違いが、数年後の組織の質を決めるのだ。DXの成功は、技術では無い。経営者が、どこまで引き受けるかで全てが決まるのだ。