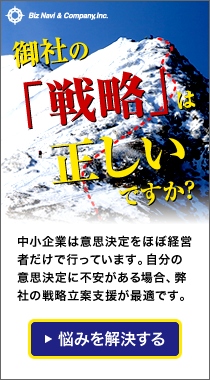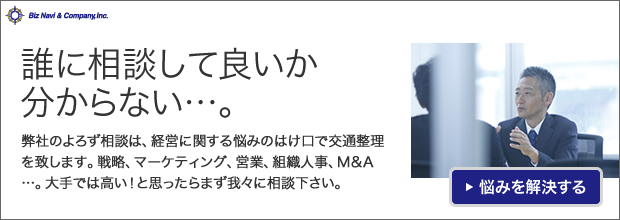早嶋です。約3200文字です。
日本の財政をめぐる議論は、いつも同じ場所をぐるぐる回っている。「財務省は緊縮路線で行くべきだ」と言う人もいれば、「PB(プライマリーバランス)目標が経済を止めている」と批判する声もある。一方で、「国は通貨を発行できるのだから、家計の借金とは違う」といった反論も出てくる。
どれも一理ある。ただ、それぞれが見ている前提も、時間軸も、リスクの置きどころも異なっているだけなのだ。
財政規律を重視する人は、「信認が崩れた後」の世界を見ている。PB批判をする人は、「いま、需要が不足している現実」を見ている。そして、通貨発行権を重視する人は、「制度として何が可能か」を見ている。
本来、これらは互いに補完関係にあるはずだ。ところが実際には、同じ土俵で正解を争おうとするため、話が噛み合わなくなる。そして、その矛先が財務省に向かっていく。
「財務省は緊縮しか考えていない」「頭がいいはずなのに、なぜ分からないのか」といった具合に。
だが、この理解も少しズレている。財務省の中で、「日本は自国通貨建て国債だから破綻しない」という事実を知らない人はいないだろう。それでも彼らが財政規律を重視するのは、「返せなくなること」を恐れているからではない。
彼らが本当に恐れているのは、政策のコントロールが効かなくなることだ。
つまり問題は「破綻」ではない。「制御不能」の状態である。ここで言う制御不能とは、国が借金を返せなくなるという意味ではない。金利や為替といった市場の反応が急変し、政府が「使う・使わない」を自分で決められなくなる状態を指している。
平時であれば、国は状況に応じて財政支出を増減させることができる。だが市場の信認が揺らぐと、「いま景気対策が必要かどうか」といった判断とは無関係に、金利上昇への対応を迫られる。つまり、政策の優先順位を自分で決められなくなってしまう。財務省が恐れる「制御不能」とは、このことだ。
しかし、この「制御不能」という説明が、一般向けに正面から語られることはほとんどない。理由は単純ではない。この話は確率論的で分かりにくく、しかも「どの程度のリスクを許容するか」という価値判断を避けて通れないからだ。官僚は選挙で選ばれた存在ではない以上、その判断を国民に向けて語る立場にはない。
そこで用いられるのが、「国の借金は家計と同じ」という比喩である。この比喩に強い違和感を覚える人も多いだろう。理論的には正しくないからだ。
だが、ここで問題にされているのは正確さではない。家計という比喩は、誰にでも分かる。借金は怖い。収入以上に使い続けるのは危うい。将来にツケを回すのは良くない。そうした感覚を、説明と同時に内面化させることができる。
つまりこれは、事実を厳密に説明するための言葉ではなく、財政規律を社会に浸透させるためのフレームなのだ。内部では市場と金利を見て、外部には生活感覚に近い言葉で語る。説明のためのフレームと、実際の運用フレームは意図的に分けられている。ただ、そのズレの蓄積が、財務省への不信感につながっている。
もう一つ、よく出てくる疑問がある。「財務省は税収が足りないと言うが、なぜ長年続いたデフレにはあまり触れないのか」さらに、「なぜ国家として保有している資産の話をしないのか」という問いだ。
これらについても、財務省が事実を理解していないわけではない。デフレが税収を押し下げてきたことも、国家に相応の資産があることも、彼らは十分に承知している。
それでも、これらの論点が前面に出てこないのには理由がある。デフレを正面から語れば、議論は必ず「需要が足りないのではないか」という方向に進む。需要不足が原因であれば、次に問われるのは「では国はどこまで財政出動をすべきか」という問題だ。これは、PB目標、つまり借金に頼らずに財政を回すという前提と正面から衝突してしまう。
国家資産についても同様である。帳簿上は多くの資産が存在するが、その多くは簡単に現金化できない。売却すれば社会的・政治的な反発が生じるものも多く、財政運営の機動力としては使いにくい。
そのため財務省は、国全体の資産額よりも、毎年確実に使えるお金の流れ、すなわちキャッシュフローを重視する。日々の財政運営という観点から見れば、一定の合理性はある。
ただし、その合理性には代償もある。ストックとしての国の姿が語られなくなることで、国全体の余力や構造が見えにくくなる。結果として、議論は「足りない」「削るしかない」という方向に傾きやすくなる。
こうした状況が続くと、財政の話は次第に「誰が悪いのか」という問いにすり替わっていく。制度や前提の問題であるはずの議論が、いつの間にか官僚個人の姿勢や思想の問題として語られてしまうのだ。
しかし、官僚個人の能力や善悪は、この種の議論から切り離すべきである。官僚は、与えられた法律と制度の中で合理的に動く存在だからだ。ゴールを疑わないのではない。疑うこと自体が、役割に含まれていない。
官僚が前提とする法律や制度は、すべて過去の時代背景の中で作られたいわば「公理」である。そして、日本の財政思想の根底には、戦後の国家設計が関わっている。
戦後日本は、「二度と国家が暴走しない」ことを最優先に設計された。その象徴が憲法9条であり、軍事力の行使を厳しく制限することで、国家が軍事的に拡張していく道を制度として封じた。
さらに、ブレーキは軍事だけではない。財政についても、同様の思想が組み込まれている。それが財政法4条だ。
この条文は、国債の発行を原則として公共事業などの建設的支出に限定し、赤字を補うための国債発行を例外扱いとする考え方を制度化している。要するに、「借金によって国家が肥大化しない」ための歯止めである。
この二つを並べて見ると、戦後日本の国家像が浮かび上がる。日本は、軍事においても、財政においても、国家が前に出すぎないように設計された国なのだ。
したがって、PB重視や均衡財政志向は、最新の経済理論から導かれた結論というより、国家が自らに課したブレーキの延長線上にある。
官僚は、そのブレーキが前提である国家を、ただ忠実に運用しているにすぎない。
だから、日本の財政議論は、経済学の立場の違いとして語ろうとすると、必ず行き詰まる。緊縮か、積極財政か。PBは守るべきか、見直すべきか。そうした問いは重要だが、いずれも、すでに決められた前提の上での議論にすぎない。
本当に問うべき問いは、もう一段深いところにある。
日本は、戦後に設計された「自己拘束国家」のままでよいのか。軍事だけでなく、財政においても、国家が自らを強く縛る設計を続けるのか。それとも、社会構造や国際環境が大きく変わった今、その前提そのものを更新するのか。
この問いに答えることは、官僚の役割ではない。官僚は、与えられた公理の中で合理的に動く存在だ。法律を変え、前提を問い直すことができるのは政治である。そして、その政治を支え、方向づけるのは、本来、私たち国民だ。
しかし、この段階に議論が進もうとすると、必ず別の空気が立ち上がる。「それは財務省と戦う話なのか」「誰の責任を問うのか」そうした問いが前面に出た瞬間、議論は止まる。
だが、ここで問われているのは、誰が正しいかでも、誰が悪いかでもない。問われているのは、どの前提を生き続けるのかという選択である。
日本の財政論が空回りし続けてきた理由は、誰かが間違っていたからではない。議論の焦点が、ずっと手前の次元で止められてきたからだ。
本当に問うべきは、「緊縮か、拡張か」ではない。日本は、国家を自ら縛るという戦後の選択を、いまも正解として生き続けるのか。それとも、その選択を、あらためて引き受け直すのか。だ、どうだろう。