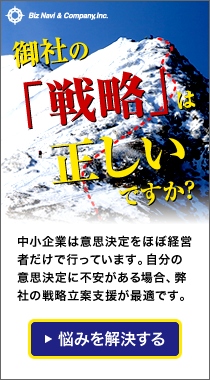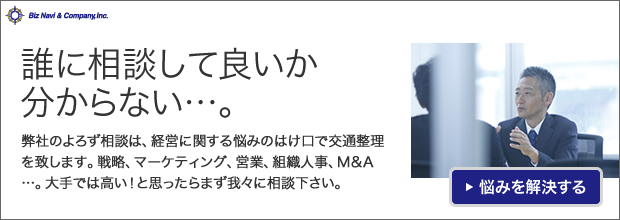早嶋です。
(前回(ゼロイチとM&A)までの確認)
例えば、企業の売上が70億で、数年後に100億を達成するという挑戦的な目標を掲げた企業があるとする。既存の事業が複数あり70億の売上を達成しているが、稼ぎ頭の事業は既に成熟期を迎えている。通常は、事業を継続させるのも難しい局面だ。
ここに対して、不足する売上をM&Aで賄おうとしても、結論から言えば、そのような案件が売りに出ていること自体が極めて稀である。仮に買収することが出来たとしても、その事業をマネジメントすることが難しく、買収した時の企業価値が最高値で減損する結果になることも多く観察できる。特に新規エリアでM&Aを行えば、事業会社から買収企業をマネジメントできる人材も限られており、戦略的なシナジーを出すことは非常に稀だ。
企業は、ミッションやビジョンの実現のために成長を選択するし、成長をあきらめる企業は衰退する以外ない。しかし常に新規事業を自助努力だけで行うゼロイチだけでは実現は難しいため、外部リソースを取り入れて成長を目指すM&Aも必要だ。既存事業の売上を増やす目的であればシナジーが読みやすく買収前調査のリスクも許容できる。しかし新規事業となると、実際は困難を相当伴う覚悟も必要なのだ。
基本は、自社の成長の方向性を議論して整理する。現状と在りたい姿のギャップを確認する。その不足する経営資源は、時間なのか、ノウハウなのか、経験なのか、販路なのか、何らかの技術なのか。兎に角、不足するギャップを徹底的に整理して可視化し具体化することが重要だ。ゼロイチか、M&Aかなどは手段であり、目的が不明確な企業は案外と多いのだ。当然、他の方向性でギャップを埋める手段として提携や出資も見えてくるだろう。
(業務提携)
在りたい姿に対して、現状とのギャップが整理できれば、それをどのように埋めるかが論点になる。自社でやるか、他社でやるかだ。その過程において、3つ目の選択肢が業務提携や資本提携だ。
業務提携とは、企業同士が業務内容について提携することを指す。生産提携、技術提携、共同開発、販売提携などだ。2社以上の企業が契約によって対象とする業務で協力しあうのだ。
生産提携などは、従来製造したことが無い製品を、工場や機械投資、そしてノウハウを蓄積することなく、既に製造が可能な企業と提携して製造することが可能になる。
技術提携などは、特許や知財などの利用を互いに許諾してクロスライセンスを結んだり、他のノウハウなどを互いに提供したりする。通常、特許で公開した技術以外は、企業機密で内容が企業の外に出ることはない。そのようなノウハウを共通の目的を持ち互いに利用できるようにするのだ。
共同開発は、技術や人材を互いに提供し合い、何らかの研究を共同で行う。研究は足が長い作業で、時間や資本をかけたところで必ず商品化されるものではない。そのため、2社以上が集まって巨力しあうことで、開発のスピードを高め、リスクを分散することができる。
販売提携は、提携する企業が互いに販売ルートを共有して、販路を拡大する際に活用される。販路があるということは、過去の営業活動と蓄積した信用があるため、新規に販売ルートを開発して新たな商品を提案するよりもはるかにコスト(お金、時間、苦労等)を下げることが可能だ。
以上、自社の不足するギャップが明確になっている場合は、提携する企業を見つけて、解消できないかを考えるのも必要なオプションだ。提携は互いに組むことでスケールメリットやシナジー効果が生み出せるのであれば検討しない手はないオプションとなる。
(資本提携)
業務提携は、事業の一部を共同で行うが、利益配分の仕方については明確に事細かく約束をしておかなければ紛争になる可能性もある。また、業務提携は情報や技術を一部共有して取り組むため、両社の関係が良好であることが前提だ。しかし関係が悪化した場合、既に共有された情報や技術は元に戻すことは出来ない。都合が悪いこともあるのだ。
そこで資本関係を結ぶことで、業務提携という単なる契約関係よりもより強固な関係性を構築する方法が資本提携だ。資本提携は2社以上の企業が互いに業務面や資金面で協力し提携関係を構築する手法だ。一方の企業が提携先の企業の株式を取得する、或はそれぞれの企業が株式を持ち寄り、提携関係を構築する。
新規事業を開発したい企業は、通常業歴が長く一般的な信用はベンチャーよりはるきあに強い。また、販路や販売後のフォロー体制など歴史とともに形成される資産を多数保有する。一方、ベンチャー企業や中小企業は、何らかの技術開発や新商品を有していたとしても、販売力や製造力、場合によっては販売後のフォロー体制が脆弱な場合ががあるなど、大企業と大きく異なる。
このように何らかの経営に問題を抱える企業にとっては、資本提携の形式で出資を受けることで与信が高まり、自社のボトルネックを解消することにつながる場合もあるのだ。
資本提携では、ある企業が他の企業に(あるいは互いに)出資し、互いの独立性は保たれる。具体的には、資本を受け入れる側の企業が資本を出す側の企業に対して第三者割当による新株発行などを行い、一定数の株式を与える。新株発行により、一方が他方の株式の1/3を超える株式を取得すると、株主総会の特別決議(定款変更、事業譲渡、合弁の承認等、会社経営の重要な決定について要求される)の拒否権が生まれる。この場合、買収(子会社化)されたのと変わらないため、業務資本提携の場合は、双方の独立性を保つために株式比率を1/3未満に設定する。
(メリット)
資本提携の目的は、双方の企業の支援にある。互いに強固な関係を結びながら、販路拡大や製造、場合によっては商品開発などを進めることができる。出資する側は、自社にないノウハウを獲得し、実際に新規事業に結び付けることができるか小さく実験できるのだ。
仮に、M&Aで一気に買収した場合は、経営権は獲得できるが、買収前の調査で検討した以上に事業統合が上手くいかない、実際に想定した新規事業のシナジーが得られない場合もある。一方、資本提携の場合、1/3以下の株式取得で進めるため、M&Aと比較すると出資金は少なく、実務を通じてシナジーを確認することが可能だ。大型の案件を進めるには不安だが、提携より強い関係を構築したい場合は、最良の選択肢となるのだ。
更に、資本提携をすすめながら、実際にシナジーを出す過程で、よりその事業に対しての資金需要が高まった場合、交渉をしながら優先的に追加出資をするなど、徐々に出資割合を高めて、子会社にしていくことも検討可能だ。
なにより、M&Aの場合は、買収前調査はあくまで紙ベースの判断になるが、少額でも出資して、人材を派遣するなどして、業務を取り組むことで、出資先の企業の状況を実業務ベースで半年から1年かけて入念に調査することもできるのだ。
(まとめ)
新規事業を始める際のオプションとして、ゼロイチとM&Aに加えて、提携や資本提携を同時に検討することが大切だ。一方で、事業会社の多くは資本政策に関連する業務は少なく経験も乏しい。積極的にアドバイザーや経験者を雇用して、自社の新規事業開発にも幅広い視点で臨む覚悟が経営者には求められるのだ。
(過去の記事)
過去の「新規事業の旅」はこちらをクリックして参照ください。
(著書の購入)
実践「ジョブ理論」
「M&A実務のプロセスとポイント<第2版>」
「ドラッカーが教える問題解決のセオリー」