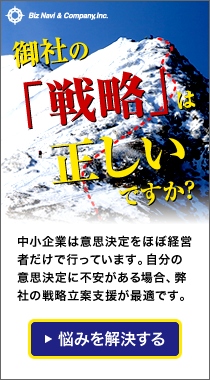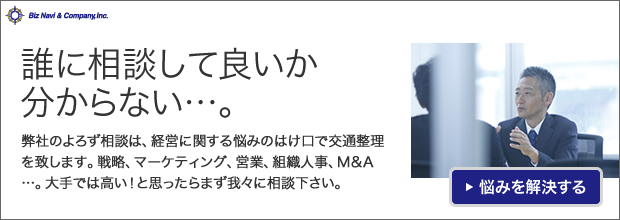年の終わりに鳴らされる除夜の鐘の回数は108と聞く。この数は煩悩を表す数として知られる。しかし、なぜ108なのかと問われると、「煩悩がたくさんあるから」「昔からそう決まっているから」と濁してしまう。実際、108という数字は単なる慣習や語呂合わせではない。人の心の理解において、知的な概念が関連しているはずなのだ。
そもそも煩悩とは何かだ。怒りや欲といった感情そのものを指す言葉だと思われがちだが、そこまで単純ではない。煩悩とは、出来事そのものではなく、心が自動的に起こしてしまう反応に注目する。何かを見て、聞いて、感じたときに、「これは嫌だ」「これは欲しい」「これは私を脅かす」と意味づけし、その反応を何度も繰り返す。その止まない反復こそが煩悩だ。
通常、怒りや不安、欲といった煩悩を、「自分の性格」や「その場の出来事」のせいにしがちだ。相手の言い方が悪かった、今日は疲れていた、タイミングが悪かった。確かにそれも一理ある。だが、それだけで説明すれば、なぜ同じような場面で、何度も同じ反応を繰り返してしまうのかが説明できない。
たとえば、何気ない一言に過剰に反応してしまうときがある。言葉そのものは大した内容ではないのに、強い苛立ちや不安が湧き上がる。あとから冷静に振り返ると、「そこまで怒る必要はなかったな」と思う。それでも、似た場面になると、また同じ反応を示す。ここに、煩悩を「出来事」や「気分」だけでは捉えきれない理由がある。
釈迦は、この繰り返しに目を向けた。単発の感情ではなく、なぜ同じ反応が、同じような条件で立ち上がるのか。その構造を注視したのだ。煩悩を道徳や性格の問題にせず、「起き方」の問題として捉え直したのだ。この理解に立つと、煩悩は単体では存在しないと言える。煩悩は条件がそろったときに立ち上がる現象なのだ。これらを整理すると、識、種、習気(じっけ)、縁という概念が生まれてくる。
識とは、目や耳に入ってきた情報を、「これは何か」「自分にとってどういう意味を持つのか」と切り分ける働きだ。同じ言葉を聞いても、ある人は冗談として受け取り、別の人は非難として受け取る。その分かれ目にあるのが識だ。識が動くことで、世界はただの刺激ではなく、「意味を持った出来事」として捉えられる。
種とは、その意味づけが過去に繰り返された痕跡だ。うれしかった経験、傷ついた記憶、うまくいかなかった感覚。そうした体験は、その場限りで消えるのではなく、心の奥に沈殿し、次に似た状況が現れたときに反応する準備を整える。種は善悪を判断しないが、条件がそろえば反射的に芽生えるのだ。
習気とは、その種が何度も発芽した結果として形づくられる反応のクセだ。怒りやすい、不安になりやすい、身構えやすい。これらは性格というより、これまでに繰り返してきた過去の反応の蓄積に近い。確立された習気は、意識しない限り、同じ方向に心を動かし続ける。
縁とは、これらを動かす引き金になる条件のことだ。相手の言葉や態度といった外的な要因だけでなく、疲れや空腹、緊張といった内側の状態も含まれる。縁が重なり、識が働き、種が刺激され、習気が一気に表に出る。その結果として、煩悩が立ち上がるのだ。
煩悩は、f(識・種・習気・縁)と表現してもよい。掛け算(識✕種✕習気✕縁)で表現しないで関数っぽく表現した理由は、「これらが同時にそろったときに現れる状態」と理解したほうが仏教的だからだ。どれか1つが欠ければ、煩悩は同じ形では起きない。つまり、煩悩とは固定した実体ではなく、縁起の束が一時的に「煩悩」という名前で現れているだけなのだ。
ここまで、煩悩を「結果」として見てきた。識や種や習気や縁が重なったときに、煩悩という状態が立ち上がる。だが、これを更に引いて眺めてみると、別のことが見えてくる。識もまた、何かがあって突然生まれたわけではない。過去の経験や学習、身体の状態や環境との関係の中で形づくられてきた働きだ。種は言うまでもなく、過去の縁の蓄積だし、習気もまた、縁の反復によって作られた軌跡にすぎない。つまり、煩悩を生み出す側だと思っていた要素そのものが、すでに縁の産物として成り立つのだ。
すると、「すべてが縁なのか?」という問いに辿り着く。仏教的には、その通りだ。ただ、何でも偶然だとか、責任がないという意味ではない。すべては条件の組み合わせとして成立し、条件が変われば結果も変わるのだ。識も、種も、習気も、それ自体が縁によって生じ、縁によって変化する。だからこそ、観察し、ずらし、緩める余地が生まれてくるのだ。
話を煩悩の数、108に戻そう。なぜこの複雑な心の動きを108という数に表したのだろうか。単に「煩悩はたくさんある」という意味だけなら、100でも1000でもよかったはずだ。それでも108が選ばれたのは、この数が人間の心の動きを分解し、構造として示すのに都合がよかったからだと思う。
まず、釈迦は人間が世界と接触する入口を6つに整理した。目、耳、鼻、舌、身、そして意だ。見る、聞く、嗅ぐ、味わう、触れる、そして考える。世界は直接心に入り込むのではなく、必ずこの6つの感覚のどれかを通って立ち上がる。ここが最初の分岐点になる。
次に、その感覚をどう受け取ったかという違いがある。受け取り方は3つに分けられる。快、不快、そしてどちらでもない、だ。同じ出来事でも、心地よく感じることもあれば、不快に感じることもある。あるいは、特に何も感じずに通り過ぎることもある。この受け取り方の差が、次の反応を大きく左右するのだ。
さらに、時間の軸が重なる。過去、現在、未来だ。過去の出来事を思い出して後悔することもあれば、今起きていることに反応することもある。まだ起きていない未来を想像して不安になることもある。煩悩は、必ずしも「今ここ」だけで生まれるわけではない。
ここに、もう一つの視点が加わる。それは、そこに執着が生じたかどうか、という点だ。快であっても、ただ感じて終わる場合もあれば、それにしがみつく場合もある。不快であっても、受け流せることもあれば、強く拒絶してしまうこともある。この「染まったか、まだ染まっていないか」という違いが、迷いを決定的なものにしていく。
このように見ると、人が煩悩に陥る分岐点が浮かび上がる。どの感覚を通じて世界に触れたのか(6)、それをどう受け取ったのか(3)、それがどの時間軸にあったのか(3)、そして、そこに執着が生じたかどうか(2)。この分岐を整理して掛け合わせた結果が、108という数になる。108とは、煩悩の実体の数というより、人間の心が迷いへと変わっていく道筋を一覧にした数だと言ったほうが近い。
なお、執着の現れ方そのものには傾向がある。欲しがる心、拒む心、そしてよく分かっていない心。いわゆる三毒で、貪(とん)・瞋(じん)・癡(ち)だ。三毒は、108を構成する数の軸というよりも、迷いがどの方向に傾いていくかを示す「質」の整理だと考えたほうが分かりやすい。
ここで、「では先ほど述べた、識・種・習気・縁とは別の話なのか?」という疑問が浮かぶかもしれない。だが、両者は矛盾していない。見ている角度が違うのだ。108の整理は、煩悩がどこで分岐するかを横から切り取った地図のようなものだ。一方で、識・種・習気・縁は、その分岐がどのような条件の重なりによって実際に立ち上がるのかを、縦に捉えた説明だ。108は静的な整理であり、識・種・習気・縁は動的な説明だと言ってもよい。
両者は同じ心の動きを、別の見方で説明している。108で「どこで迷うか」を示し、識・種・習気・縁で「なぜ迷いが現れるか」を説明している。この二つを重ねて見ることで、煩悩は単なる数でも、単なる感情でもなく、条件の束として理解できるようになる。そして最終的には、ここに行き着く。煩悩も、その構成要素である識や種や習気も、すべて縁の中で生じ、縁の中で変化している。108という数は、その事実を人間が理解できる形に、いったん固定した思考のための道具なのだと思う。
こうして見てくると、108という数の意味も、少し変わって見えてくる。108は、煩悩を1つずつ消し去るための数ではない。むしろ、人の心がどこで、どのように迷いへと傾いていくのかを、丁寧に照らし出すための数だと言ったほうが近い。
除夜の鐘は、煩悩を叩き落とす音ではないのだと思う。心の中で起きている反応の仕組みを、1つひとつ思い出させる音だ。識が動き、過去の種が刺激され、習気が立ち上がり、縁が重なって、また同じ反応をしてしまう。その構造に、静かに気づくための時間をつくる音なのだ。
もし煩悩が固定した実体ではなく、条件がそろったときに現れる現象にすぎないのだとしたら、私たちにできることは多い。反応を責める必要もないし、無理に消そうとする必要もない。ただ、どこで心が動いたのかを観察し、少し距離を取る。その余地があること自体が、すでに変化の入口になる。
年の終わりに鐘の音を聞くとき、108という数を数え切る必要はないのかもしれない。ただ、自分の心がどんな条件に反応しやすいのかを、ひとつ思い出す。それだけでも、来年の同じ場面は、少し違って見えてくるはずだと思う。どうだろう。