
店舗から本部が集客機能にシフトしよう!(店舗事業2)
2021年10月30日
早嶋です。
時代が変わりました。従来は、顧客とコンタクトをとり、顧客情報を管理するコストが高く、店舗系ビジネスはその管理や集客を店舗に一任していました。しかし今は高校生が簡単にプログラムした程度で顧客を管理するアプリやライン等のツールを使って顧客とダイレクトにコミュニケーションできる仕組みがあります。それも企業の金額感からすると随分と安価です。それなのに、100店舗前後の店舗ビジネスを運営する本部は今でも店長任せ、スーパーバイザ任せの集客です。Webやデジタルマーケティングを本部が行い、店舗は来客の対応に徹するといのが構築できる時代になっているにもかかわらずです。
提言です。店舗の顧客管理の仕組みをゼロベースで刷新し、1年間でデータを集め直し、そのデータを利用して100店舗の店長が100通りの集客をするのではなく、本部が責任を持ってデータを分析してここにフォローする仕組みを作る。というのがスマートです。Webと顧客IDとGPSとライン等のコミュニケーションツールを使って、顧客の来店状況、商品の活用状況から適宜適切なマーケティング策を考えて本部がダイレクトに顧客にアプローチするのです。顧客のデータを取るなどの活動も店長が積極的にしなければ出来ない従来の発想を捨て、サービス利用時にレジで会計をする時に自然とデータが収集する仕組みに切り替えます。店長は、その日に来店する顧客のデータが事前にわかり、重要顧客に対しては、どのような接客をすると良いのかを毎朝仲間とミーティングして日々の接客サービスに没頭する仕組みに切り替えるのです。そして、その実現も実は難しくないのです。
現状の落とし穴はパッチワーク的に動いているITシステムです。複数のベンダーが部門最適で仕組みを入れており、しかも連動していない。そのためデータを駆使してなにかしようにも、データの整理や連携を店頭で行わなければなりません。無駄な時間がかかり結果的に目の前のお客様の接客サービスに没頭するという極めて正しい行いになるため、データ活用がすすまないのが現状です。
本部はそのような仕組みを一度捨てて、サンクコストとして処理してください。両利きの経営では無いですが、創造する。維持する。だけでは企業は伸びず、破壊するという行為を行わねければ刷新はできないのです。
上記の取組とともに実現すべきは組織の改造です。従来は顧客の動向は店舗でしか判断できなかったので店長がいて、スーパーバイザがいました。しかしDX化して現場のデータを本部で吸い上げるようにすれば、基本100店舗の店長は皆スタッフで良く、指示はダイレクトに本部から行えるようになります。そのため店長が不要になるか、スーパーバイザが不要になるか、あるいは両方が不要になります。
店長として成績を上げていた数名、現場で長年キャリアを積んで様々な取組をした社員数名。実質的な仕事が出来ているスーパーバイザ数名を本部に集めます。そしてITと経営のことを理解している責任者は、仕組みを構築しながら、彼ら彼女らの話を取り入れて実質的に現場で使える仕組みを構築します。
店舗ビジネスで良く観察できる失敗事例は、本部スタッフのインテリが現場の経験がなく、勝手にシステムを構築することです。そのため現場からは不平や不満が出まくる。更にシステムを一気に完成させようとする発想を持っています。どうではなく、全体の構想を明らかにしながらも、現場の困りごとを解決し、自社の方向性に進むような仕組みを上記の選抜チームとともに仕様をつくり現場でテストしてを1年の中に数回繰り返し、その後に一気に展開させるという発想で仕組みを構築していくのです。その後も、顧客のデータや店舗の売上推移をみながら適宜自動化できる分はIT担当に任せ、現場でしか出来ない接客サービスを特定して、そこに社員の資源を投下する発想をもつのです。
ぜひ、15年以上の歴史を持つ店舗ビジネスの経営者、スーパーバイザ、店長は昨今のD2Cの事業ケースを10社分くらい研究すべきです。基本的には店舗は集客せずに、本部がITを活用してデジタルで集客をする。リピート等の仕組みは店長とデジタルツールで顧客を管理していく。店長は店の売上に責任を持つのではなく顧客の推奨度や満足度と言った指標で管理をして、店長の評価は売上ではなく店舗スタッフの成長や行動に対して評価をします。昔と違って店舗がコンタクトポイントとなり別の店舗で売上が発生したり、Webで売上が発生するからです。店舗売上で店長を管理した瞬間から店長は部門最適になります。そのため参入が浅いD2C企業は、はじめから店長に収益責任を持たせないのです。
対前年比管理を見直して見よう!(店舗事業1)
2021年10月29日
早嶋です。
成長している時期、特に店舗ビジネスなど、毎日同じ行動の結果、ある程度の成果が出る手の商売は、対前年比管理を当たり前のように実施していました。しかし、業績が下がっている昨今、その手法を見直すことをおすすめします。
その理由は、以下のような分析を行ってから考えて見てください。例えば、直近の成績から5年位のスパンで管理会計区分の売上で大きな単位でその推移を見てみます。売上=A商品郡+B商品郡+C商品郡=α事業部+β事業部+γ事業部=X店舗+Y店舗+Z店舗などが管理会計区分での売上になります。
日本経済の特徴として1996年頃を堺に殆どの業界がステイか下り坂です。そのため5年程度の推移を見れば、明らかに業績が激減していることが見えるでしょう。意外なことに、こと店舗ビジネスにおいて、店長は昨対比か昨月費の数字しか見ていないので、経営トップが言っている業績の激減や環境変化について「体感」していません。毎年、あるいは毎月、少しづつ下がっているイメージはあるものの、数字を比較する上では、あまり変化が見えないのです。
これは実は店長を管轄するスーパーバイザに対しても同じです。彼ら彼女らもまた短期的な店舗の業績に追われ自身の給与を管理されているためその日の売上に一喜一憂するため数年スパンの傾向値など見向きもしません。その結果、本部と店舗(現場)では、危機感の感情がかなり異なっています。
そこで上述したグラフの作成です。できれば、デジタルのこの時代、敢えてアナログで店長を集めて、5年分の数字を持参させ、あるいは提供してグラフを描いてもらうことが効果的です。もちろんエクセルでもOKです。すると改めて数字が激減していることを直視します。
例えば100店舗ある企業が同様のことをした場合、店舗によっても特徴が出てきます。その場合は、なぜA:伸びている店舗があるのか。B:なぜ変わらない店舗があるのか。C:なぜ減少している店舗があるのか。の3つに分けて店長同士ブレストさせます。これをエリアごと、管理会計上の商品郡ごとなど、いくつかの種類に分けて、その稽古うちをA、B、Cに分けてブレストさせます。日々目の前の経営に直面している店長、スーパーバイザに取って何気ないことがどんどんフラッシュバックして、思い当たるフシがどんどん言語化されます。
その上で、本部は本部の方針を示し、新たな事業を行う意義や、管理会計上の主力商品の資源バランスを変えることなどを再度説明するのです。
対月対年管理をしている店舗ビジネスの本部が、突然方向変換の理由を説明して、現場に落とし込もうとしても現場に変化が置きない理由は、店舗に全くの危機意識も危機感も無いことに由来するのです。本部が焦っても、現場が動かなければ経営にインパクトが無いのが店舗ビジネスです。
DX化の呪文の奥に潜む現場の弊害
2021年10月25日
早嶋です。
一度でもデータをいじった経験があれば、かんたんにDX化が進まないことがわかると思います。そもそもアナログで最適化出来ていない企業がデジタルで最適化できるはずが無いのです。DX化は企業の仕組みをゼロリセットし、デジタル化に最適な指揮命令系統や組織、管理の仕方や評価など、まるっとするっと変える勇気と覚悟があっても結構大変だからです。したがって、DX化を実現できたら、そこには必ず組織の変革があり、新たな未来が見えるかもしれないのです。
DX化関門の1つ目はデータそのものです。多くの経営者は社内にはデータが溢れているから、「それらを活用して売上や利益を上げれるだろう。」なんて簡単に妄想します。が、間違いなく不可能です。そもそも偏在しているデータがいくら豊富にあっても、それらは活用出来ないのです。編集等手を加えない限り。
いわゆるデータの不備ですが、部門が異なる毎にデータの管理の仕方が異なったり、同じデータでも機能毎に意味が微妙に異なっていたり、全体としてルールがあっても現場レベルでローカルルールが正常運転している場合など様々です。データを分析する前に、それらのデータを使えるレベルにする必要がまずあるのです。
例えば、管理の仕方です。ある部門では大人を18歳と認識し、ある部門では大人を20歳と認識する。部門を統合してデータを分析しても大人の概念が異なり、統合したデータが無意味になります。例えば、定義の違いです。売上のタイミングをある部門では発生ベースで認識し、ある部門では入金ベースで管理します。2つの部門の売上を統合した結果の売上は何を意味するのか不明です。これらは全て全体最適で管理されず各々部門最適に動いてきた過去の弊害なのです。
データ統合の際に意味があるデータに修正する作業はクレンジングと称されます。じみーに大変であることが想像できると思います。当然、不足するデータに対しては新たに取得するルールを設けて収集することなども考える必要があります。これらのニュアンスが想像できない人は、既にデジタル化以前に近年の思考についていけない弊害です。断定しても良いですが、早く代替わりしたほうが良いのです。
上記のようなことが小さな会社でも発生しているのですから、組織再編する企業規模や、毎年のようにM&Aを繰り返して規模拡大している企業はデータのクレンジング作業がいつまでたっても終わりません。そのため企業によっては過去のデータに見切りを付けて、新たに収集したデータでDX化を実現させる企業もあると思います。
当然、データが集まっても、それらを解析し実行する部隊が必要です。2つ目のDX化の関門は人材です。企業において高々にDXを推進すると言いながら、毎年同じ人事戦略で、毎年同じルートで新卒採用を進めています。中途も代替同じような感じです。スペックをあまり決めずに集めています。そう、「その人材を獲得してもDX化なんて幻ですよ!」と助言したいくらいです。
もちろん初めは外部の専門家に頼んでデータの収集や社内データのクレンジングをすすめるでしょうが、その作業はDX化を宣言したら永続します。そのため社内でその取組ができる人材を内製化しなければ、いつまで経っても経費がかさむばかりです。データが揃って集まる仕組みが出来ても、分析するにもノウハウと経験の積み重ねが必要です。いわゆるデータサイエンティストの教育か、その確保が必須になります。
例えば、イメージして見てください。データ分析だけできる人材に、「このデータを適当に分析してなにか法則を見つけてみて?」と言っても100%当たり前の分析結果しかでてこないと思います。出てきたとしても、すごい工数をかけて「売上の80%を上位20%の顧客で賄っています!」なんて当たり前のコトを連発されて終わりです。そう、データを分析するためにはその業界やその事業の中身に対してある程度課題感と仮説構築を行いながら分析しなければ、鋭いインサイトなんて生まれないのです。
そのため成功している企業は、ある程度経営分析ができる社員や、現場の経験がある筋の良い社員にデータ分析のスキルとツールの使い方を教育しています。一定のキャリアを積み、ある程度分析に理解のある人材に対して課題提言を行わせ、データ分析の得意な専門家とタッグを組むなどしてデータの分析と活用を補完するのです。少なくとも事業がわかる人材がデータ分析の基本を持っていれば、外部に分析そのものの仕事を丸投げしてもある程度辺りを付けて指示をするので、「当たり前の結果」に高額の外注費を支払うリスクは低減されます。
とここまで見てくると、基本的に、色々器用にこなす人材に仕事が集中し、その人材がヘトヘトになるまで働く結果、疲弊していくというのが関の山なのです。経営者としては、そのメインディッシュ級の人材が仕事ができるように、必要なスペックの人材を適宜あてがうコトをしなければ、既存の取組に対しても逆効果になることを理解したほうが良いのです。
とここまで議論をすると、これがたまたまDX化というスローガンであって、過去からのイノベーションや新規事業などと唱え、全て同じサイクルで結局何も出来ていない企業がみんな連呼しているのがDX化じゃないかと。私はそのように滑稽に見てしまっています。もちろん、仕組みを作ってガンガン成果を出すお手伝いもしていますが、覚悟が双方に必要です。それが出来ない仕組みは極めて滑稽に感じます。
【動画】21年度異業種交流型・武者修行研修・リーダー版向け
2021年10月24日
本ページは、2021年度異業種交流型・リーダー版武者修行研修・受講者向けのページです。
セッション3(Day4)受講の事前課題
事後課題として、セッション2で議論した(強み)✕(社会課題)のアイデアをブラッシュアップして下さい。その際、1)ビジネス・モデル・キャンパスの視点を再び議論して深堀りしてください。また、その際に、2)MVPを作成して、実際の消費者や対象層にヒアリングを行ってください。サンプル数はできる範囲で結構です。セッション3では、各チーム25分の持ち時間の中で10分から15分程度、プレゼンして頂きます。3)各チームでプレゼン資料を整理してください。
1)ビジネスモデルキャンパスのブラッシュアップ
2)MVPの作成とMVPを活用した調査
3)セッション3のプレゼン発表資料の準備
上記をすすめる当たり、プレゼンテーションの基礎の動画を参照ください。
プレゼンテーションの基礎 概要編
プレゼンテーションの基礎 プレゼンテーションの流れ編
プレゼンテーションの基礎 準備編
プレゼンテーションの基礎 コンテンツ編
プレゼンテーションの基礎 デリバリー編
また、セッション2のリーダーシップの学びを深める目的で、以下のリーダーシップの基礎の動画を見て振り返りに活用ください。
動画視聴のパスワードは各社事務局の指示に従って下さい。
セッション2(Day2&Day3)受講の事前課題
事後課題として、別途事務局から連絡があった通り、1)ピクト図の作成、2)登場人物の整理と調査を各チームで整理、を行って下さい。なお、1)と2)を行う際に、以下の動画を視聴下さい。参考になります。
「新規事業10億ビジネスを創造」
こちらの動画では、ビジネスモデルキャンパスの考え方を理解ください。内容は10億の事業を創造するとしたら、どのようなコトを考える必要があるかについて整理しています。Day2、Day3の議論で売上と費用を考える際のヒントになります。
「デザイン思考の基礎 試作フェーズ」
こちらの動画はデザイン思考の基礎の4本目の動画です。試作のフェーズについて解説しています。皆さんが議論したビジネスモデルを早い段階で確かめる際に、MVPの作成やテストマーケティングを実施して頂きます。その際のヒントになります。
動画視聴のパスワードは各社事務局の指示に従って下さい。
セッション1(Day1)受講の事前課題
受講者は、事前課題を準備して、第1回目(21年9月16日)のワークショップ(オンライン)へ参加ください。
1)「自己紹介シート」の作成
参加者同士の理解を深める目的で、各自自己紹介シートを作成ください。テンプレートは各社事務局の指示に従って下さい。
2)事前課題「社会課題から事業チャンスの抽出」
現時点でご自身が注目する社会的な問題やそれに関連したテーマで事業チャンスを整理して下さい(A4用紙1枚程度、フォーマットは自由)。
例)マイクロプラスチックについて
現在、マイクロプラスチックは年間●トンの規模で海洋に放出され、その影響により、・・・・・。ここに対して●●の取組を活用することで●●の事業チャンスがあると考えます。
3)事前課題「動画視聴」
「新規ビジネス創造の前に考えること(約35分)」
「新規事業創造の考え方(約40分)」
「環境分析の考え方(約35分)」
動画視聴のパスワードは各社事務局の指示に従って下さい。
新規の方向性を決めるのはトップの仕事
2021年10月21日
早嶋です。
生産性が悪い企業、変化しない企業、成熟事業がピークを迎え新たな事業を創造しなければならないが行動を起こさない企業。トップはスローガンのように「新規事業」「イノベーション」「DXの活用」などを掲げる。が、現場では「またか・・・」という声が聞こえてきます。
そもそも、成熟し次の事業を生み出す場合、現場に新規事業のネタを求めるのはNGだと思います。トップが中心となり、次の事業の方向性を議論して戦略を示すべきなのです。そもそも現場は全体を見る力を持たないし、仮に見れたとしても意思決定なんて出来ません。そのためいかなる新規事業も基本はトップがフルに関与しなければならないと思うのです。
よくある風景としては、若手社員やベテラン社員を集めて新記事業を起こすワークショップを開催して方向性を決める取組です。体裁は教育目的で、新規立案を研修材料に取り入れ、自由闊達な議論をさせ、最終的に役員などのトッププレゼンを折り込みます。そのアイデアいいね、となっても役員一同、誰も行動を起こしません。社長もその話を聞いていても、実際の計画に織り込むことは有りません。そうなると、何のための若手のワークショップだったの?となり。不信感が募るばかりです。
あたかも自分たちの保守のために、本当は変わらないと思っても、もうすぐ定年だから、コトを大きくしたくない。と思うのでしょうか。だったら、早いところ引退して役割を若いマネジメントに託すべきではないでしょうか。
理系の大学2年生の就職不安に対して
2021年10月13日
早嶋です。
日本の理系の大学2年生に対して。就職をなんとなく不安に思っているのであれば、次のような取組をしてみるのはどうでしょう。
前提として、今後の社会は、自分の頭で問いを立て、その解決策を自分なりに提案し、実践する人材を欲します。ITや皆さんが学業で学ぶ科目は、上記を表現するための言語や思考でふわふわしたものをスッキリ明快に他の人がみてもわかるようにするツールです。
更に、言えば、自分が何をしたいなんて、多分30になっても40になってもわからないから、自分がやりたいコトを見つけた時にできる能力と時間と財力を身に着けていることが大切だと思います。そのため就職は単なるスタートで究極、いつでも修正することが可能です。そのために悩むよりは、今の学業生活をうんと楽しみ、活用することに専念してみてください。
ということでやってみると良いと思うことの1つ目。理系の大学生は、研究室に配属され、その研究室の教授が企業の就職の推薦枠を持っています。そのため研究室を選ぶ前に過去の先輩方がどこに就職しているかを確認することをおすすめします。大学の業務課などに聞いたらたいていは教えてくれるはずです。そして、その中からピンときた研究室を選べるようにすると良いでしょう。
2つ目。ということは、自分で研究室を選べる立場になっておくことが大切です。研究室は2年生の終わり頃から選択しますが、基本は成績順で決められます。流れとしては、自由に生徒が選び、希望が多い研究室は、その学生の中で上位の成績順で選択されます。そのため、日頃から大学の勉強をして、テストで良い点数を取っておけば、選択する際に優位な立場になれます。理系の学生は、特に日本において真面目に勉強するのが少ないですので、当たり前に学問に励めば難しいことではありません。
3つ目。今はcovit-19の関連で海外や国内など自由に旅行に行けないでしょうが、できるだけ大学生のうちに、行ける場所は色々足を運んでみることをおすすめします。今はスマフォでかんたんにそのエリアの情報が獲得できるので行ったつもりになる人も多いと思いますが、1次情報ってやっぱりパワーがあります。企業に就職しても、この習慣がない人は、机上で全てを考え、計画通り行くことを当たり前としますが、学生の時に色々経験を積んで於けば、うまくいかないコトを前提に考えはじめます。これは良い習慣です。
4つ目。大学生って、付き合う友達が偏りがちだけど、できるだけいろいろな価値観の人間と触れ、長い間関係を構築することをおすすめします。そのためには、自分の居心地の良いグループ以外に、部活の仲間、趣味の仲間、留学生の仲間、バイトの仲間、等々、意図的にジャンルが違うグループを5つくらい見つけて、定期的に異なるグループとコミュニケーションを取り続けることです。様々な視点を持つことで、自分が将来新たな問いを立てる際や意思決定をする際に役立ちます。
5つ目。理系の学生は1年生、2年生は必須科目が多くて、選択科目を取る余裕が無いと思いますが、できるだけ専門外の科目も履修すること。だって、そこに教えに来ている先生って、普通にすごい人で、その時間、ほぼほぼ独占して学びを得ることができるからです。関係の無い知識が増えれば、新たな問や新たな興味が泉の如く湧いてきます。また、そこで教えている先生とのネットワークは、更に異なるグループへと発展して人脈がガンガン広がります。
どうもがいてもcovit-19は1年は続くでしょう。すると皆さんは3年生。その際に、能動的に動くことをしていない学生は、そのまま残念が学生生活を過ごすことでしょう。そして、全てにおいてcovit-19のせいにするでしょう。でも世の中同じ環境にいて逆境を乗り切れる人間とそうで無い人間に必ず分かれます。後者の人間になるために、ぜひぜひ、上記の5つの一つでも取り組んでみてください。
パートタイムは無いでしょう
2021年10月12日
早嶋です。
M&Aという言葉や概念は11年前、一般財団法人M&Aアドバイザー協会を設立してから随分と世の中に浸透していると思います。そして最近は、シリアルアントレプレナーをイメージし、売り手の立場として会社そのものを商品として売却する仕掛けを意図的に作っている経営者も増えています。これに関しては良いとか悪いとかはなく、その戦略なので間違っては無いと思います。
ただ、シリアルアントレプレナーを目指すのであれば、はじめの一件は是非フルコミットしてもらいたいところです。どんなに優れた事業モデルでも現時点で赤字で、かつ経営者がパートタイムで事業を行っているような取り組みは、どんなに御託を並べられても時価総額のイメージがピンと来ません。それは売り手の都合であり、買い手の意思を無視しています。
更に、そこに対してM&Aでバイアウトしたいのであれば尚更です。IPOはたしかに将来の可能性に対してある程度価値を評価するでしょう。しかし中小企業のM&Aにおいては、今の利益が重要で、過去からの取り組みで何をしたのかがなければ将来の推定もできません。ですので社歴が1年ポッチの会社で赤字であれば、仮に優れた仕組みを持っていたとしても、相当の経営者でなければ買収する気持ちにななれないと思います。
企業のベースは、その企業を起こす大義名分で、経営者は本気でその大義名分を達成する気持ちで行動し続けるものです。その結果、企業の収益がついてくる。それを志がなく、売却が目的ですよってな会社は、従業員にも、顧客にも、取引先にも申し訳ないと私は思います。あくまでも一部の特定のシリアルアントレプレナーを目指している方に向けてのメッセージで、他の経営者や成果を残しているシリアルアントレプレナーに対しては社会に価値を提供し続けているので立派だと思います。
囚われのない素直な心で聞く
2021年10月6日
原です。
ビジネスを取り巻く環境の変化が早く複雑な時代、顧客の声は、企業の問題解決やマーケティング活動が顧客重視の傾向になればなるほど、貴重な情報源ととらえられるようになってきました。
私の最近の経営相談でも、「顧客の声をもっと自社のビジネスに活用したいのですが、具体的にどのようにしたら良いでしょうか」という相談を受けることが増えてきました。
私は、これまでに多数の「顧客の声」を活用したマーケティング調査に取り組みました。そして、企業の製品開発・サービス開発や改良、自治体政策課題研究など多様な問題解決の解決策提案に役立てています。
調査結果から明らかに見えてきたことは、企業側が提供している商品やメッセージに対して、消費者が誤解しているケースがとても多いのです。
企業側が「知っていて当たり前」、「伝わって当然」と思っていることも、顧客は意外と分かっていないものです。
つまり、企業側と顧客側にギャップ(誤解という問題)があるのです。
ギャップが生じているなら、それを解決しなくてはいけません。そのためにはどうすれば良いでしょうか。
問題点は、「あるべき姿」と「現状」のギャップを分析することで発見できます。まずは、「現状を知る」ことから始めます。つまり、「顧客の現状を知ること」なのです。顧客は、何を意識しているのか、何に価値を感じているのか、企業側が商品や広告を通じて伝えたメッセージをどのように感じるのか。そのように意識し感じる理由はなぜなのか。これらの顧客の現状を知ることが、ビジネスの問題を解決するための第一歩となります。
顧客の現状を知るには、グループインタビューなどの顧客の声を聞くことが「素直な」方法です。
松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)創業者の松下幸之助氏は、次のように述べています。
「世間、大衆の声に、また部下の言葉に謙虚に耳を傾ける。それができるのが素直な心である。それを自分が正しいのだ、自分のほうが偉いのだということにとらわれると、人の言葉が耳に入らない。周知が集まらない。いきおい自分一人の小さな知恵だけで経営を行うようになってしまう。これまた失敗に結びつきやすい。素直な心になれば、物事の実相が見える。それにもとづいて、何をなすべきか、何をなさざるべきかということも分かってくる。なすべきを行い、なすべからざるを行わない真実の勇気もそこから湧いてくる。」(引用:「実践経営哲学」著者 松下幸之助)
私は、大学生の頃から松下幸之助氏の著書を何度も読み返しています。
インタビューで顧客の現状や実態を把握することは、問題を発見し、それを効果的に解決していくための土台となります。インタビューの重要性、有効性を認識し、机上で悩む前に「素直に顧客の声を聞く」姿勢がとても大切です。
職場に活かす心理学
2021年10月6日
安藤です。
仕事でのマネジメント・人間関係構築に活用できる心理学を2つ記載いたします。
1つは、「語用論」です。もともと語用論には、言葉とは用いる場面や発する人、受け取る相手によって意味合いが異なっているということを示しています。例えば、「できていないよね」という言葉一つとっても、ピリピリした上司―部下の関係で、上司が部下に向かって「できていないよね」と言えば、「できていない」という意味や能力を否定されているように捉えられるかもしれません。それに対して、親友から「できていない」といわれたとしたら、もっと「できていないところを指摘してくれている」という意味で捉えるかもしれません。同じ言葉でも“文脈” によって意味合いが違います。このような語用論的理解が、文脈の理解において重要視されます。文脈とは、物事を前後の状況(文脈)に合わせて臨機応変に認識することです。前後の文脈や置かれた状況によって、認識する意味が変化することを文脈(コンテキスト)効果と言います。 人間は感覚器官から情報を得ると、それまで蓄積した経験や知識をもとにそれがなんであるかを認識します。一般的な例からすると、文字の場合、線分や輪郭の組み合わせからパターンに当てはめて「何の文字か」を判断しています。別の見方をすると、語用論から少し外れるかもしれませんが、受け取る相手によって意味合いが異なるということは、互いの関係性も関係していると考えます。日頃からどのような関係を築いているのか、信頼関係があるのか、そんな観点からも捉え方が変わるのではないでしょうか。
2つ目は、ダブルバインド理論です。ダブルバインド理論(二十拘束理論)は、グレゴリー・ベイトソン(Bateson.G)らが、パロアルト・グループの研究での概念です。ダブルバインドは、あるメッセージ(言語的)と、それとは矛盾するメタメッセージ(非言語的)を同時に与えられることのよって、混乱する状況に置かれることを言います。
例えば、事務所で部下Aさんを上司が呼ぶ時に笑顔で呼ぶとします。そのAさんが、近づいてくると上司が不快な表情をしていたり、威圧的な態度になったりすることがあると部下Aさんは、自分がどのような態度をしたらよいのかわからなくなります。 ここで最も影響をうけるのが非言語コミュニケーションです。コミュニケーションには、「情報」と「情報に関する情報」の2つのレベルがあります。別の例でお話をすると、「あなたの話をきいているよ」といいながら、パソコンに視線を向けて、それをいじっている状態だったらどう思うでしょうか。「話を聞いている」という言語的情報と、「~ながら」でしか聞いていない」という非言語的情報の2つのレベルのコミュニケーションが同時に行われています。このように、非言語的コミュニケーションによって、人間関係における問題となることは少なくないのではないでしょうか。
*非言語コミュニケーションとは、他者とコミュニケーションを図る上で、表情や顔色、声のトーン、話す速度、身振り手振り、視線などのことです。また、服装や髪型、香りなども非言語コミュニケーションとして影響しているといわれています。
コロナ禍で在宅勤務が増えており、聞きたい事が直ぐに聞けない。そのために、業務が進まずに支障がでているなど、コミュニケーションの問題が多くなっているようです。そのようなことも含めて、コミュニケーションの問題・課題、他
人材育成・開発に関して、気軽に弊社にご相談くださいませ。
発情期の牛、働く人の幸せ
2021年10月5日
◇牛の発情期センサー
原田です。
15年くらい昔のことです、あるベンチャー企業の事業内容に衝撃を受けました。
その事業は、雌牛の発情期をセンサーで感知するというものです。これまで雌牛の発情期の判断はベテラン飼育員の目利きに任されていました。それがセンサーで測ることで、人に頼らず確実にわかるというものです。
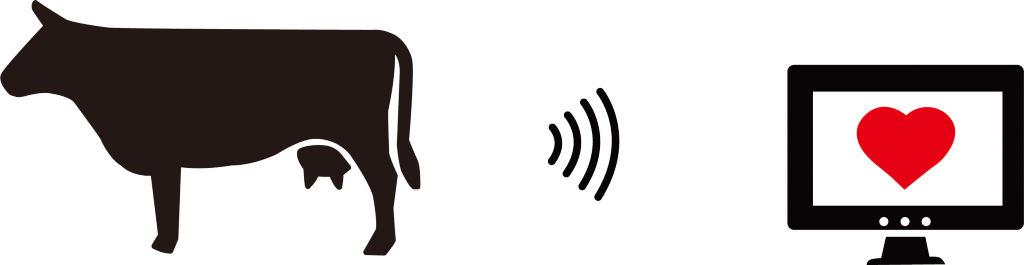
雌牛は発情期になると、特有の落ち着きのない動きを取るようになります。発情期は一定のサイクル(20日くらい)でやってきます。一方で発情期は短く、適正な受精をするためには、早期発見が求められます。もし、受精に失敗すれば、なかなかの損失になります。しかし、雌牛にセンサーをつけることで、特有の動きを検知し、迅速に知らせてくれます。ベテラン飼育員の目利きに頼ることもなく、確実性も高いです。
そして、この技術は現在、業界では標準的な技術になっています。WEBを検索すると同じ製品を提供する企業がたくさんあって、私が読んだ冊子の企業がどうなったかはわかりません。確か宮崎の企業で、産官学連携の案件だったような記憶があります。多分この企業だと思います。
特許情報プラットフォームを検索すると、1998年には、「識別記号および雌牛発情期表示器」という特許が出願されています。ちなみにスウエーデンの人の発明のようです。上述の企業も1999年から「発情ピタリ」という製品を開発しているようなので、何か関係があるのかもしれません。
ちなみに現在は、似たような特許が、NECや富士通からも出願されています。なので「雌牛発情期センサー業界」は様々な企業の製品が入り乱れています。
◇働く人の幸せセンサー
そして、5年くらい前、同じような原理のセンサーに衝撃を受けました。それは働く人の「幸せ」を、センサーで図ろうというものです。

2015年日立グループの「イノベーティブR&Dレポート」に、「ウエアラブル技術による幸福感の計測」という小論文が掲載されました。
https://www.hitachihyoron.com/jp/pdf/2015/06_07/2015_06_07_13.pdf
内容は、人の「幸せ」をウエアラブルセンサーを使って定量化するというものです。詳しい説明は省きますが、研究チームは、人の身体運動に着目し、「1/Tの法則」を見いだしました。そして、人の「幸せ」と「1/T」のゆらぎに強い相関があるというのがこの小論文の結論です。
この「1/T」のゆらぎは、隠れた身体運動の特徴を捉えた指標であり、移動が多い営業職と、椅子に座る業務が中心の事務職のように職種による運動量の差には影響されないということです。
また、「幸せ」を単に居心地のよい安楽な状態と定義していません。自身のレベルに応じて、仕事をしている状態が幸せだということです。つまり仕事が簡単すぎて「退屈」という状態と、難しくて「不安」という状態の間に「幸せ」があるということです。
この小論文では、フロー理論のミハイ・チクセントミハイにも言及しています。チクセントミハイの著書「FLOW」を読んだ方には、この「幸せ」の定義の素晴らしさがわかると思います。
なお、この研究結果は、日立グループから社内ベンチャー「ハピネスプラット」として、事業化されました。アプリも無料でダウンロードできます。
事業化されて、表現がかなりマイルドになっています。個人情報の扱いがかなり厳しくなったことや、データをAIで解析することの倫理観など、今はいろいろうるさくなっているので、かなり気をつかっているなと思います。
それでもこの定量化された数値は、人の主観が入るアンケートや、専門家が行う複雑な組織サーベイなどよりも信憑性がもてると思います。これを導入する企業は増えていくと思います。
◇なんでも数値化される
近年はなんでも数値化される時代です。睡眠の質を測るスリープテックも普及してきました。体重計も、体脂肪率だけでなく、骨密度から、肉体年齢まで図れます。さらには臭いもセンサーで測れるようになりました。なんと手のひらの臭いでその人の気分がわかるということです。
しかし、数値化の多くは、そのまま解決につながりません。考えてみれば当たり前のことです。体重計を例にとります。おそらく日本人は、1週間に1回以上(多くの人は1日2回)は体重を測っていると思います。しかし、世間はダイエットのコンテンツで溢れています。みんな自分の体重をコントロールするのに必死です。体重を測って予想より軽ければ、うれしくなって、必要以上に食べます。もし予想よりも重ければ落ち込み、食事制限する。その繰り返しだと思います。
社員の「幸せ」を測っても、ネガティブシンキングの人たちが集まっていれば、私はなんて不幸なのだとか、ウチの組織はなんて幸せがないのだとか、余計に暗くなりそうです。性格が悪い人たちの集まった組織であれば、数値が低いのはあいつのせいだ、などとんだやぶ蛇になりそうです。
何事も数値化されても解決策がなければ、そしてその解決策を確実に実行できなければ、それを解釈、または言い訳するのは人間なのでまたひどい結果を招きます。
そもそも組織に明確なビジョンと目標があり、みんなで共有し、実行、フィードバックすれば「幸せ」になります。このことは大昔から変わっていません。
◇取捨選択が大事
今、世の中には、このシステムを導入すれば会社の業績が劇的に良くなるというような魅惑的な製品・サービスで溢れかえっています。営業DXとか、人事DXとか、財務DXとか、そういうセミナー、イベントもたくさん開かれています。
でも結局は、みんなと同じことをすれば、同質化競争に陥り、自社の製品・サービスがコモディティ化し、価格競争になります。そして最後は「気合」と「根性」が引っ張り出されます。いつものパターンです。
このような時代、大事なことは取捨選択、つまり必要なものを見極めることです。大小を問わず、すべての企業で強みの根源は、極めてアナログな要素です。人の熱意であり、組織の風土であり、理念です。
そのためには改めて、自社の内部分析とビジョンの共有、そしてテクノロジーの根本理解が必要です。両方とも、頭に汗をかくしかありません。粘り強く人を育てる必要があります。そして、現場で試行錯誤を繰り返すということです。人が働く「幸せ」はそこにあると思います。
最新記事の投稿
カテゴリー
リンク
RSS
アーカイブ
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月
- 2006年5月
- 2006年4月
- 2006年3月
- 2006年2月
- 2006年1月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年9月
- 2005年8月
- 2005年7月
- 2005年6月
- 2005年5月
- 2005年4月










