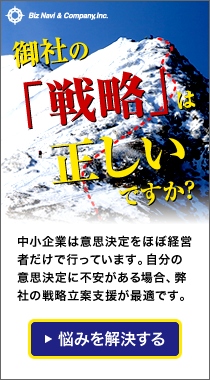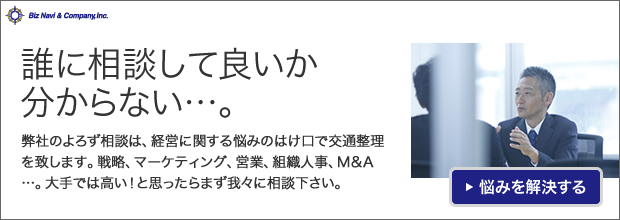早嶋です。今回はとても長いです。約16,000文字。
(転職サイトの「年収アップ」は本当か?)
SNSの広告には、「年収◯%アップ」「転職でキャリアも収入も向上」などの言葉がならぶ。ここ数年、人手不足や賃上げニュースも重なり、「転職すれば給料は上がる」という雰囲気が、半ば常識のように語られている。しかし、日本企業の組織構造や賃金制度を知る立場から眺めると、どうにも引っかかる。
統計を確認した。厚生労働省の「雇用動向調査」で、転職し入職した人の賃金が前職と比べてどう変わったかを見ると、令和6年(2024年)1年間では「増加」40.5%、「減少」29.4%、「変わらない」28.4%という分布になっている。つまり、「転職すれば上がる」が常識になっている一方で、現実には下がる人も同じだけいる。上がる人がいるのは事実だが、皆が上がるわけではない。この前提を置くだけで、転職市場が強調する年収アップの見え方は、異なってくる。
日本企業の多くは、いまだに年功的な賃金カーブと職能等級制度を残す。労働組合の影響も強い。従い、特定の個人を突出して高く評価する設計になっていない。特に組合員層は、「同じ年次・同じ等級なら、だいたい同じ賃金」という前提が存在する。
ここで誤解しやすい点がある。賃金が上がりにくい理由を「労働組合がガチガチだから」と説明すると、話が単純化される。実態は、労組の存在そのものより、組合員層における賃金決定の仕組みにある。多くの日本企業では、組合員層の賃金は個別契約ではなく、制度運用として管理されている。等級、年次、評価ランクといった枠組みの中で決められ、個人ごとに大きく例外を作らないことが前提だ。これは、組合員の平等性を守るためという建前で、会社も説明責任を果たし続けるための設計だった。
仮に、ある個人だけを市場価格に合わせて大きく引き上げたとする。すると必ず、「なぜその人だけなのか」「次は誰が対象になるのか」「それは制度上どう位置づけられるのか」という問いが生まれる。ここに明確なルールがなければ、賃金制度そのものが揺らぐ。つまり、突出処遇は、金額以上に制度を壊すコストが伴うのだ。このコストを負担ができるのは、賃金決定が制度外の人材に限る。管理職、専門職、あるいは代替の利かない特定機能を担う人材だ。彼らは最初から「個別に決める」前提で扱われているため、市場価格への寄せ直しが可能だ。逆に言えば、組合員層で賃金が動きにくいのは、労組が強いからでも、会社が冷たいからでもない。制度として公平性と説明可能性を維持した結果、意思決定が慎重になった構造の問題なのだ。
この構造を前提に、「転職しただけで年収が大きく上がる」という話は、直感的に整合しない。むしろ多くの場合、転職先でも年齢や等級に応じたレンジに当てはめられ、賃金は元のカーブに吸い戻されるのが実態ではないか、という疑問が湧くのだ。それにもかかわらず、なぜ転職市場では「年収アップ」が強調され続けるのか。このズレは、単なる誇張や広告表現の問題ではなく、日本の雇用構造と転職市場の見せ方の間にある、もう少し根深い問題を映しているように思えてしまう
(年収が上がる人と、上がらない人)
転職で年収が上がる人は確かに存在する。しかし、その人たちは日本の平均像ではない。その人達は、いくつかはっきりした共通項があるのだ。
まず1つ目は、賃金決定が組合の枠外にある人だ。管理職層、あるいは高度な専門職に属する人たちは、そもそも年功的な賃金テーブルの影響を受けにくい。会社側も「等級」ではなく「市場価格」で処遇を決めざるを得ないため、転職時に条件が大きく動く余地が生まれる。
2つ目は、業界そのものが成長局面にあり、かつ人材が希少な分野にいる人だ。IT、データ、研究開発、医療の一部、建設やインフラでも特殊資格や特定工法を担える人材などは、「人が足りない」のではなく「その機能を持つ人が足りない」状態にある。ここでは、年齢や社歴よりも「代替可能かどうか」が賃金を決める。
3つ目は、世代としては比較的若く、賃金カーブの初期にいる人だ。20代後半から30代前半は、もともとの賃金水準が低いため、会社を変えることで「平均値に近づく」だけでも年収アップに見える。実態としては、突出した評価というよりは、歪んだ初期配置が是正されたケースだ。
これらの人たちに共通するのは、「転職によって賃金の決まり方そのものが変わる」点だ。組織内の序列から外れ、市場に直接つながった瞬間に、年収が動く。
一方で、転職しても年収がほとんど上がらない、あるいは下がる人にも、共通する構造がある。最も多いのは、同業・同職種への横移動だ。日本の同業他社は、賃金カーブや等級設計が驚くほど似通っている。結果として、転職先でも「年齢×役割」に応じたレンジに当てはめられ、年収は元の水準に収まる。
次に多いのは、「できるはず」という自己評価は高いが、機能として説明できない人だ。不満や違和感は語れても、「自分が何を生み出せるか」を市場に説明できない場合、転職先は慎重になる。条件は現状維持、もしくは様子見の設定になりやすい。
そしてもう一つ重要なのが、30代後半以降の組合員層だ。この世代は賃金カーブの中盤から後半に差し掛かっており、企業側にとっては「即戦力であっても高コスト」になりやすい。結果として、転職が成立しても条件は横ばい、場合によっては下がるのだ。
注目すべきなのは、能力の高低そのものよりも、賃金制度との位置関係が結果を左右している点だ。頑張ったから上がる、評価されたから上がる、という単純な話ではないのだ。転職サイトで語られる「年収アップ」は、こうした構造の中で、組合外、専門性が明確、若年層、成長産業という、ごく一部の層を切り取って平均化した数字であることが多い。
ここで、もう1つ整理すべき論点がある。転職で「年収が上がった」と語られるとき、その中身が何かは、意外と曖昧なままだ。転職サイトの多くは年収という1つの数字で語るが、現実の処遇はもっと分解されている。残業代の有無や時間数、賞与の算定基準(業績連動か、評価連動か)、住宅手当や家族手当、転勤手当といった各種手当。これらが組み替わるだけで、見かけの年収は簡単に動く。
その結果、「年収は上がったが、基本給はほとんど変わっていない」というケースが頻繁に起きている。初年度は残業が多い、賞与算定が甘い、手当が厚い。だが、それが恒常的な賃金上昇を意味するとは限らない。基本給がどこまで上がったのか。それが、その会社での評価や将来の賃金カーブにどう反映されるのか。この点を見ないまま「年収アップ」を語ると、転職広告の数字マジックに飲み込まれやすくなる。
もう1つ重要なのは、「いつまで上がっているのか」という時間軸だ。転職直後の年収は、採用側の期待値込みで高めに設定されることがある。即戦力として迎える以上、最初は評価を先払いする、という判断だ。しかし、多くの場合、2年から3年経つと、その人は賃金制度の内側に組み込まれる。評価は通常運用に戻り、昇給幅も既存社員と同じルールに従う。そこで初めて、実力と制度の整合が問われるのだ。このタイミングで起きるのが、「転職時は上がったが、その後は伸びない」という現象だ。
これは個人の能力が落ちたわけでも、評価が急に厳しくなったわけでもない。単に、一時的に制度の外に出ていた賃金が、再び制度に回収されただけなのだ。つまり、年収が上がったかどうかを語るなら、「初年度」ではなく、「3年後にどうなっているか」を見なければ意味がない。この視点を持つと、転職による年収アップが、いかに限定的な条件で成立しているかが見えてくる。
(同業他社への転職は、年収アップにつながりにくい理由)
転職を考えるとき、多くの人がまず思い浮かべるのは「同業他社」だろう。理由は、仕事の内容が分かっている、経験がそのまま使える、説明もしやすいなど、本人にとっては合理的な選択に見える。しかし、日本企業の賃金構造を前提にすると、同業他社への転職は、年収という点では最も効果が出にくい移動だ。理由は単純で、同じ業界の企業は、賃金カーブも評価思想も驚くほど似ているからだ。
年齢、勤続年数、等級、役職。これらの組み合わせで処遇が決まる構造は、業界内でほぼ共有されている。結果として、転職先でも「この年次ならこの辺り」という暗黙のレンジに当てはめられ、賃金は元のカーブに吸い戻される。特に30代以降になると、この傾向はより顕著になる。即戦力として期待される一方で、企業側から見ると人件費はすでに高めだ。突出した役割の変更や昇格が伴わない限り、「あえて高く買う理由」がなくなる。
同業転職で年収が上がるケースがあるとすれば、それは実質的に転職ではなく、役割のジャンプが起きた場合だ。管理職として迎えられる、特殊なプロジェクト責任を任される、あるいは人材が枯渇している局所機能を担う。こうした条件が揃わない限り、同業他社への移動は「場所が変わるだけ」の横滑りになりやすい。もっとも、「同業はどこも同じ」と言い切ってしまうと、現場感覚とは少しズレる。実際には、同じ業界の中でも、会社の立ち位置によって役割の厚みは大きく異なる。
たとえば建設であれば、元請けと下請けでは、求められる能力の重心が違う。製造でも、地域専業と全国展開では、工程管理や顧客対応のスケールが変わる。公共工事比率が高い企業と、民需中心の企業では、品質・安全・コストに対する評価軸そのものが違う。業界名が同じでも、仕事の設計が違えば、評価のされ方も違うのだ。
だが、ここで重要なのは、「会社が違うから年収が上がる」のではない、という点だ。同業転職で条件が動くのは、あくまで役割が変わったときに限られる。元請け側の調整機能を担う、広域案件を束ねる、リスクを引き受ける立場に移る。つまり、肩書きではなく、責任の範囲と判断の重さが変わった場合だけ、賃金が再定義される。
逆に言えば、業界が同じで、役割もほぼ同じであれば、どれだけ「会社が違う」ように見えても、賃金は元のカーブに吸い戻される。この意味で、同業転職で起きている差の正体は、会社のブランドではなく、役割のジャンプなのだ。
その意味で、同業転職の本質は、年収アップではなく、評価者を変える、渋滞している昇格ルートを抜ける、環境をリセットする、といった時間とポジションの調整にある。
ある製造系企業の30代前半の技術者の話だ。同業他社への転職時、転職サイト上では「年収80万円アップ」と表示されていた。実際、初年度の年収は確かに上がった。だが内訳を見ると、基本給はほとんど変わらず、残業時間の増加と賞与算定の一時的な上振れによるものだった。
転職先では即戦力として期待され、立ち上がりの1年目は評価も高かった。しかし2年目に入ると、評価は既存社員の等級基準に揃えられ、昇格も見送られた。結果として、年収は元のレンジに吸い戻され、本人は「話が違う」と感じ始める。
会社側に悪意があったわけではない。最初から賃金制度は変わっていなかったのだ。ただ、本人が見ていたのは初年度の年収であり、会社が見ていたのは等級に基づく中長期の処遇だった。このズレは、同業転職では決して珍しい話ではない。
(引き抜きという言葉のミスリード)
同業転職と並んでよく語られるのが「引き抜き」だ。この言葉には、条件が良くなり、特別扱いされるイメージがつきまとう。しかし、実際に起きている引き抜きは、性質の異なる2つのタイプがある。
1つは、機能を買う引き抜きだ。建設であれば特定工法を回せる人、製造であれば特定設備や品質領域を握っている人、インフラや研究分野であれば代替の利かない専門性を持つ人。ここでは、「人が足りない」のではなく、「この機能を持つ人がいない」状態が生まれている。ここで言う「機能を買う引き抜き」は、抽象的な能力の話ではない。現場で具体的に任せられるかどうかが判断基準になる。
たとえば建設であれば、特定領域の施工管理を一通り回した経験がある人、特殊工法の段取りとリスクを理解している人、品質や安全の観点から「止める判断」を任されてきた人だ。単に資格を持っているだけでなく、現場で判断責任を背負った経験が問われる。
インフラでは、運用監視や保安、設備更新の計画に関わり、「止められない設備」のリスクを読める人が該当する。トラブルを未然に防ぐ視点を持ち、異常時にどこまで踏み込めるかを理解しているかが、機能として評価される。
医療でも同じだ。夜勤を含めた運用を安定して回せる、専門領域で患者導線や業務フローを設計できる、若手の教育係を担える。こうした役割を実際に果たしてきた人は、単なる人数補充では代替できない。
このレベルになると、企業が見ているのは「人」ではなく、「その人が担ってきた判断と責任の履歴」だ。だからこそ、条件も仕事の中身も、市場価格で再設定される。この場合、仕事の中身も裁量も変わり、賃金も市場価格で再設定される。これは転職というより、人的資本の獲得に近い。
もう1つは、人数を埋めるための引き抜きだ。人手不足を理由に声がかかるケースの多くは、こちらに該当する。業務内容はほぼ同じ、責任範囲も変わらない。ただ欠員を埋めたい。そうなると、賃金テーブルや社内公平性は動かせず、条件は横ばいになる。同じ「引き抜き」という言葉でも、前者と後者では意味がまったく違う。後者は実態として、同業他社への横移動と大差ない。
建設、製造、インフラといった分野では、慢性的な人手不足が続いている。にもかかわらず、賃金が劇的に上がっているかというと、そうではない。ここには、日本的な構造がある。人が足りないのは事実だが、企業は「仕事のやり方」や「役割設計」を変えるよりも、まず人数で解決しようとする。その結果、必要なのは「誰でもいいから人」になり、賃金は上げられない。
(賃金が動く条件と転職者の勘違い)
賃金が動くのは、あくまで機能が足りないときだ。この差を曖昧にしたまま「人手不足」を語るから、転職市場と現場の実感にズレが生まれるのだ。結果として、人は動く、企業は「人が足りない」と言い続け、賃金は大きく動かない、という循環が生まれていく。
ここまで整理すると、共通点ははっきりする。日本で年収が動くかどうかは、「どれだけ困っているか」ではなく、「その人が担う機能が、制度の外に出ているかどうか」で決まるのだ。同業他社への転職が効きにくいのは、能力の問題ではない。引き抜きが条件改善につながらないのも、不誠実だからではない。どちらも、賃金制度の内側で起きている移動にすぎないからだ。この構造を理解しないまま、「転職すれば報われる」「人手不足だからチャンスだ」という言葉だけが一人歩きしている。ここに、若手の期待と現実のズレが生まれる土壌があるのだ。
(若手の勘違いのメカニズムとその後の運命)
若手の早期離職を語るとき、「最近の若者は我慢が足りない」「成長意欲が高いから動く」といった言い方を聞く。だが、実態を見ると問題は意欲でも忍耐力でもない。自分の現在地に対する認識のズレが、5年前後で表面化しているだけなのだ。
若手の早期離職は、印象論ではなく、数字としても無視できない規模だ。厚生労働省が公表した令和4年3月卒業者のデータでは、就職後3年以内の離職率は、高卒が37.9%、大卒が33.8%だ。「大卒の3割、高卒はそれ以上」という水準が、もはや例外ではなく構造として繰り返されている。この現実を踏まえると、問題は個人の気合や根性では片づけられない、ということが見えてくる。
特に大卒の場合、入社から数年が経つと、ある種の感覚にたどり着きやすい。日々の仕事の流れは一通り理解できるようになる。自分が担当している業務が、全体のどこに位置づいているのかも見えてくる。上司が何を考えて判断しているかも、表面的には追えるようになる。そして、現場を見ていれば、「ここはこうした方が良いのではないか」という改善案も自然と浮かぶようになる。
これは、間違いなく成長の証だ。ただし同時に、非常に強い錯覚を生む段階でもある。仕事の全体像が見えるようになることと、その仕事の責任を背負えるようになることは、本来まったく別だ。だが若手ほど、この2つを無意識に重ねてしまう。「全体が見えているのだから、もう一段上の仕事もできるはずだ」「なぜ自分にはまだ任せてもらえないのか」という感覚だ。
一方、会社側はどうか。多くの組織では、責任を段階的に背負わせる設計や、その理由を言語化して伝える仕組みが用意されていない。若手には、仕事は渡すが、判断の重さや失敗のコストまでは見せない。上司が裏で引き受けている調整やリスクは、あえて見せない構造になっている。結果として、若手の側には「見えている範囲」だけが広がり、「背負う重さ」がどこまで違うのかが伝わらない。
この空白が埋められないまま時間が過ぎると、認識のズレは別の形で解釈され始める。「評価されていないのではないか」「この会社にいても成長できないのではないか」といった不満だ。本来、成長途中にあるがゆえの違和感だが、その原因は会社や上司の問題として理解されてしまう。
そして、この空白に入り込むのが、転職サイトやSNSで語られる「数字」だ。年収◯%アップ、20代で◯◯万円、スピード昇進。そこには、責任の範囲も、失敗のコストも、役割の違いも語られない。ただ結果の数字だけが提示される。若手にとっては、その数字が、自分の感じている違和感に対する答えのように見えてしまう。
こうして、成長の途中で生まれるはずの「認識のズレ」は、社内で解消されることなく、社外の物差しで測られるようになる。若手が勘違いをするのではない。勘違いが生まれる余地を、組織が構造として放置しているのだ。この構造を理解しないまま、早期離職を「意欲の問題」や「価値観の変化」で片づけてしまうと、同じ現象は何度でも繰り返されることになる。
この状態は、成長の証でもあるが、同時に錯覚を生む。「もう一段上の仕事ができるはずだ」「正当に評価されていないのではないか」等だ。しかし多くの場合、ここで見えているのは仕事の全体像であって、責任の重さや失敗のコストではない。結果として、能力が伸びたという事実と、役割が変わらない現実の間に、認識のズレが生まれる。このズレを埋める言葉や説明が社内に無ければ、若手は原因を「会社」や「上司」に求めてしまう。そして転職市場に、答えがあるような気がしてしまうのだ。
統計を見ると、大卒者の3年以内離職率はおおむね3割前後で推移している。5年程度まで含めると、4割近くが一度は会社を離れる。では、その後のキャリアはどうなっているのか興味があると思う。
全体傾向として最も多いのは、同業・近接職種への転職だ。仕事の説明がしやすく、即戦力として入りやすい。ただし年収は横ばい、もしくは一時的に下がるケースも多い。次に多いのが、異業種・異職種への移動だが、ここは二極化する。言語化能力が高く、機能として自分を再定義できる人は伸びる。一方で、肩書きやイメージで選んだ人は迷走しやすい。
重要なのは、平均すると条件は大きく改善していないという点だ。転職直後は「環境が変わった」「評価されている気がする」という心理的改善があるが、数年後に同じ不満が再燃するケースも少なくない。
一方で、高卒の早期離職については、やや慎重に見ておく必要がある。一般に、高卒の離職率は大卒よりも高く、離職後のキャリアが必ずしも安定しているとは言い切れない。非正規雇用への移行や、一定期間の非就業状態に入る割合が高い層が存在することも、複数の調査で示されている。
それを踏まえた上で、ここで述べておきたいのは、統計的な優劣の話ではない。私の仮説として言えば、高卒で早期離職を経験した人材の中には、仕事や会社に対する期待値が比較的現実的になりやすい側面がある、という点だ。初職での経験を通じて、「仕事とはこういうものだ」「どこに行っても簡単には変わらない」という感覚を早く持つ人も多い。その結果として、次の職場で過度な幻想を抱きにくく、心理的には安定しやすいケースがあるように見える。
ただし、これはあくまで傾向の話であって、結果を保証するものではない。高卒の離職後に雇用の質が上がるかどうかは、公的職業訓練の利用や、資格取得、現場での技能蓄積といった条件によって大きく左右される。これらを伴わない移動であれば、賃金も職務内容も横ばいのまま固定化される可能性が高い。
つまり、高卒の離職後が「安定している」と言うよりも、「期待と現実のギャップが早く是正される人が一定数いる」と表現した方が、実態に近いだろう。一方で、大卒の場合は、期待値が高い分だけ、移動後も同じズレを抱え続け、再び不満を感じやすい構造がある。この違いは、能力の差ではなく、最初に与えられた期待と、その修正プロセスの違いによって生まれている。
(不満を持って辞める人材の価値)
あらかじめ但し書き記したい。もちろん、組織側の判断ミスによって、優秀な人材が辞めてしまうケースは存在する。上司との相性、配置の失敗、評価の偏り。こうした要因で、本来なら活躍できたはずの人材が力を発揮できないまま去ることもある。それ自体を否定するつもりはない。
ただし、これから扱うのは、そうした個別の悲劇ではない。問題視したいのは、「不満を主語にした離職」が、ある規模で、あるタイミングで、繰り返し発生しているという事実だ。もし原因が個々の上司の資質や偶発的な相性だけであれば、これほど再現性をもって若手の離職は起きない。多数の離職を生んでいる主因は、個人の善悪ではなく、構造の側にある。
その前提に立ったうえで、「不満を持って辞める人材は使いにくい」という表現を、少しだけ正確に言い換えておきたい。ここで言う「使いにくい」とは、能力が低いという意味ではない。組織の中で役割や期待値をすり合わせるための適応コストが高い、という意味だ。
不満を動機に離職する人材の多くは、評価を構造としてではなく、感情として捉えやすい傾向がある。「なぜ評価されないのか」「なぜ任せてもらえないのか」という問いは立てるが、「自分は今、どの役割を担い、どの責任を引き受けているのか」という相対化が弱い。その結果、会社との認識のズレを、制度や役割の問題としてではなく、納得できない感情として処理してしまうのだ。
企業側から見れば、価値を感じている人材は、簡単には手放さない。期待され、仕事が集まり、役割が増え、内部で調整が行われる。一方で、不満が前面に出ている人材は、その調整コストが高くなりやすい。これは性格の問題ではなく、構造的な相互理解の難しさだ。結果として、「扱いにくい」という評価が生まれる。
重要なのは、これは断罪ではない点だ。不満を持つこと自体が悪いのではない。不満が生まれる背景を、組織が説明できず、相対化の機会を与えてこなかったことが、同じパターンの離職を生み続けているのだ。個人を切り捨てる話ではなく、組織が自らの設計をどう見直すか、という話なのだ。
これは能力不足というより、自己認識と市場認識のズレだ。転職市場では、「何ができるか」「何を任せられるか」が問われる。そこに不満や被害感情を持ち込むと、評価は慎重になる。結果として、条件は据え置きになり、次の職場でも同じ摩擦が起きやすいのだ。
つまり、「使いにくい」の正体は、スキルの有無ではなく、組織の中で自分をどう位置づけるかの視点が弱いことにある。
ここまでを整理すると、因果はかなり明確になる。若手は成長する。だが、その成長の意味を会社から説明されない。自分の現在地も、次の段階も見えない。その結果、「評価されていない」「ここにいても意味がない」という不満に変換されるのだ。そこで、不満を理由に辞める。だが、構造は変わらないのだ。次の職場でも、同じ壁に当たるだろう。問題は若手の甘さだけではないのだ。期待と現実のズレを、組織が放置していることにあると思う。
(企業は採用から育成を戦略として取り入れるべき)
ここまで見てきたように、転職市場や若手の早期離職をめぐる問題は、個人の意識や努力だけでは説明がつかない。むしろ問われているのは、企業側が人材をどう設計し、どう使おうとしているのかという視点だ。
多くの日本企業では、「新卒一括採用」「年次別育成」「横並び評価」が前提になっている。だが、この前提そのものが、すでに現実と噛み合っていない。とりわけ建設・製造・インフラといった分野では、人手不足が慢性化し、若手の定着が難しくなっているにもかかわらず、採用と育成の設計は昔のままだ。ここで一度、発想を切り替える必要がある。
まず高卒人材についてだ。従来、高卒採用は新卒一択で語られてきた。しかし現実を見ると、高卒の新卒定着率は高くない。一方で、早期離職を経験した高卒者の中には、現場経験を通じて仕事観が現実的になり、「次は続けたい」「ちゃんと身につけたい」と考えている層が一定数存在する。
企業にとって合理的なのは、高卒新卒だけを追いかけることではなく、早期離職者を含めた再スタート層を戦略的に採用することだ。この層を受け入れる際に重要なのは、最初から一律のキャリアを押し付けないことだ。一定期間、現場で徹底的に鍛え、基礎的な耐性や技能を身につけさせた上で、定期的に選択肢を提示するのだ。1つは、大卒者と同等の経験・学習環境に進むルート。もう1つは、従来型の高卒キャリアとして、現場の熟練者として価値を発揮するルート。
どちらが正解かを会社が決めるのではなく、要件と期待値を明示した上で、本人に選ばせる。これによって、過剰な期待も、被害者意識も生まれにくくなる。選ばなかった人材も、会社にとっては必要な戦力として位置づけられ続けると思う。
一方で、大卒人材の扱いは、これまでとは逆の意味で再設計が必要になる。大卒の若手が辞める最大の理由は、仕事がつまらないからでも、給料が低いからでもない。自分の立ち位置が分からないまま、時間だけが過ぎることにある。そこで企業がやるべきなのは、単に仕事を与えることではなく、3年から5年というスパンで、意図的に「相対化の機会」を組み込むことだ。仕事全体の構造はどうなっているか。自社が業界の中でどこに立っているのか。同年代の他社社員と比べたときの自分の強みと弱み。5年後、10年後に任される役割の違い。こうした情報を、仕組みとして定期的に見せる。
放っておけば、若手は勝手に比較する。SNSや転職サイトを通じて、歪んだ物差しで自分を測り始める。それならば、会社の側が、より現実に近い比較軸を提供した方がいいのだ。もちろん、その前提として、10年スパンで見たときに「この会社にいた方が明らかに優位になる」経験設計が必要だ。難易度の高い仕事、長期的に効いてくる技術、責任のある役割への段階的な移行。これらが用意されていなければ、相対化は逆効果になる。
特定の技能をすでに持っている人材は別として、多くの大卒は「すぐに差がつく」わけではない。だからこそ、短期成果で競わせるのではなく、時間を味方につけた設計が重要になる。
ここで1つはっきりしてくるのは、戦略的な人材活用とは、「全員を同じように扱うこと」ではない、という点だ。高卒も、大卒も、同じ入口、同じ育成、同じ期待値、という設計は、もはや機能しない。
必要なのは、
●どの層を、どの時間軸で育てるのか
●どこで分岐し、どんな価値を発揮してもらうのか
を、最初から織り込んだ設計だ。分けることは、切り捨てることではない。むしろ、分けないことが、無用な不満と離職を生んできたのだ。この視点に立てるかどうかが、これからの企業の人材戦略の分かれ目になる。
(人材戦略は管理職だけでは既に制度疲労を起こしている)
ここまで整理してきた人材戦略を、いざ評価制度に落とそうとすると、多くの企業で同じ壁にぶつかっている。「それは管理職がやればいい」「現場で部下を一番見ているのは上司だ」という発想だ。
だが、結論から言えば、この設計を管理職任せにするのは無理がある。これは管理職の能力や人格の問題ではない。日本の組織構造そのものが、そうなっていないからだ。日本の管理職の多くは、年齢や勤続年数を重ねる中で昇格してきた層だ。現場の実務には強く、人としても誠実で、部下思いの人も多い。しかしその一方で、「人を評価し、育成し、将来の分岐を設計する」という訓練を体系的に受けてきたわけではない。
更に彼ら自身も、相対評価を明確に示され、市場価値という言葉で説明され、キャリア分岐を自ら選ばされた経験を持たないまま、ここまで来ている。その結果、評価はどうしても「今の成果」「手がかからないか」「自分に合うか」といった、短期・主観的な軸に寄りやすくなっている。育成は「背中を見せる」「我慢して覚えろ」という形になり、若手が感じている不安や焦りを、構造として受け止めることができないのだ。これは怠慢ではない。そういう役割として管理職を設計してこなかったことが、最大の原因だと思う。
もう1つ、問題を深くしているのが、日本の評価制度そのものだ。多くの企業では、評価制度は、給与を決めるため、昇格を決めるための仕組みとして設計されている。その結果、評価はどうしても「序列づけ」になり、評価面談は「結果の通知」になり、育成は評価の副産物に追いやられている。
ここで若手が求めているのは、「給料を上げてほしい」ことよりも、「自分は今どこにいて、次に何が待っているのか」を知ることなのだ。だが、評価制度がそれを加味していない。管理職もその認識がない。結果として、若手は会社の外に答えを探しに行くしか無いと考えるのだ。この構造を変えない限り、どれだけ「育成が大事だ」「定着が重要だ」と言っても、評価制度そのものが若手を外へ押し出す力として働き続けるのだ。
そこで必要になるのが、評価と育成を機能として切り出す発想だ。管理職の代わりに評価をするのではない。人事の延長でもない。キャリア相談の外注でもない。切り出す役割は明確だ。管理職が「今の仕事と成果」を見るのに対して、この専門組織は「人の時間軸」を見るのだ。
ここで、この専門組織の位置づけを、もう一段だけ明確にしておきたい。というのも、この手の仕組みは、境界線が曖昧なまま導入されると、「管理職の仕事を奪うのではないか」「人事の監視装置になるのではないか」という誤解を招きやすいからだ。実装の成否は、この線引きをどれだけ最初に共有できるかにかかっている。
まず管理職の役割は変わらない。日々の業務アサイン、成果の確認、一次評価、現場での業務指導。これは引き続き、管理職の責任領域だ。専門組織がここに介入することはないし、判断を覆すこともない。管理職は「今の仕事」と「今の成果」を見る存在であり続ける。
人事部の役割も同様だ。等級制度や賃金テーブルの設計、評価制度全体の整合性、労務・労組対応、最終的な運用統制。人事は全体最適を担う機能であり、個別の若手一人ひとりの時間軸を長く追い続ける役割とは性質が異なる。この分業は崩さない。
その上で、この専門組織が担うのは、管理職と人事の「あいだ」に空いている領域だ。若手一人ひとりについて、数年単位の時間軸で面談を行い、評価の背景を翻訳し、期待値のズレを調整する。部門をまたいで若手の悩みや詰まりどころを整理し、「どこで何が起きているのか」という傾向を構造として抽出し、人事や経営に改善案として返す。個人の決定を代行するのではなく、判断に必要な視点を揃える役割だ。
だからこそ、この専門組織は意思決定権を持たない。昇格も処遇も決めない。評価を下す側にもならない。あくまで、評価と育成が機能するための補助線を引く存在である。この線引きが明確であればあるほど、「監視装置」ではなく「現場を楽にする仕組み」として受け入れられる。
運用の単位についても、あらかじめ現実的な絵を描いておいた方がいい。1人あたり100名前後を上限に担当する設計にするのだ。これ以上広げると、面談は形式化し、時間軸を追うという本来の役割が果たせなくなる。
たとえば社員数が1000人から2000人規模の会社で、入社1年目から7年目までの若手が全社で400人いると仮定する。初年度から全員を対象にする必要はない。離職が多い部門や、若手が集中している部門を中心に、まず150人程度をパイロット対象にする。担当は2名。1人あたり70人から80人を受け持ち、定期面談と管理職とのすり合わせに時間を使う。このくらいの単位感であれば、「実験」ではなく「業務」として回し切れる。
初年度にやるべきことは、制度を完成させることではない。この専門組織が入ることで、管理職の評価面談が楽になる、若手との認識ズレが減る、拗れそうな案件を早めにほどける。その実感を、限られた人数でつくることだ。境界線と運用単位を最初に明確にすることは、そのための前提条件なのである。
若手一人ひとりについて、現在の能力レベル、社内外での相対的位置、この会社で積める経験の価値を整理し、言語化し、本人と管理職の双方に共有していく。役割1人あたりで100名前後を上限に担当し、定期的に面談を行い、評価の背景を翻訳し、キャリアの分岐点を一緒に設計するのだ。重要なのは、意思決定権を持たないことだ。昇格や処遇を決めるのは、あくまで管理職と人事。専門組織は、それを支える材料と視点を提供するのだ。だからこそ、管理職の「補佐・保管」であり、「敵」にならない。
ここで、既存のキャリアコンサル制度にも触れておく必要がある。多くの企業で導入されているキャリアコンサルは、「守秘義務」を前提に、個人の悩みを聞くことに重きを置いている。だが、この設計は、組織の視点では致命的な欠陥を抱えていると思うのだ。個人の悩みは、その人だけの問題ではないという点だ。5年目前後の社員で同じ不満が繰り返されるなら、それは組織構造の問題だ。
それにもかかわらず、悩みは共有されず、ナレッジは蓄積されず、同じ問題が何度も発生している。これでは、育成はいつまでも個別対応に留まり、組織は学習しないままだ。ここで提案している専門組織は、感情やプライバシーは守るが、構造・傾向・制度的な歪みは会社の知として残すのだ。それが、「本気で育成を考える会社」の最低条件だと思う。
この専門組織は、人事部と対立するものではない。むしろ、人事が本来やりたくてもできなかった役割を補完する存在だ。人事部は、制度設計、等級や賃金の管理、法令、労務、労組対応という「全体最適」を担う。一方の専門組織は、個人の時間軸をながく取り、評価の解釈、納得形成という「個別最適と構造の接続」を担うのだ。両者が並走することで、評価制度は単なる序列の仕組みだけでなく、人を育て、残し、収益性を高めるための経営の仕組みに変わるのだ。
ここまでの話を整理すると、こうなる。評価制度を、管理職の善意や経験に委ねるのをやめる。育成を、個人の我慢や根性に委ねるのをやめる。その代わりに、人の成長と時間を、会社として設計する。若手が辞めない会社とは、甘い会社ではない。評価が厳しくても、納得できる会社だ。この専門組織は、離職率を下げるためのコストではなく、人材投資の回収率を高めるための仕組みとして位置づけるべきだと思うのだ。
(組織に実装するやり方)
この仕組みを導入する場合、企業が最初にやりがちな失敗は、「すぐに成果を測ろうとする」ことだ。離職率を下げる、エンゲージメントを上げる、若手の満足度を高める。どれも重要だが、初年度からこれを前面に出すと、制度はほぼ確実に壊れると思う。
1000人から2000人規模の組織で初年度にやるべきことは、はっきりしている。制度を完成させることではなく、「この機能があると現場が楽になる」と理解させることだ。
別の建設系企業では、若手の離職そのものよりも、評価面談のたびに起きる摩擦が問題になっていた。「評価に納得できない」「何を期待されているのか分からない」。面談後に不満が残り、管理職も疲弊していた。そこでこの会社は、評価制度を変える前に、評価面談の前段を設けた。評価を下す前に、若手本人・管理職・第三者的な専門担当が入り、「今の役割」「期待しているレベル」「次に背負わせたい責任」を整理して言語化したのだ。すると、評価結果そのものは大きく変わらなかったが、面談後の揉め事は明らかに減った。管理職からは「評価を通知する場から、仕事を設計する場に変わった」という声が出た。若手が辞めなくなった、という派手な成果はない。ただ、評価をきっかけに関係が悪化するケースが減り、管理職の負荷も下がった。この会社がやったのは、育成制度の刷新ではない。相対化の機会を、評価の前に一つ差し込んだだけだ。それでも、現場の空気は確実に変わったのだ。
事例で見たように、最初にやるべきは、制度の説明ではない。経営トップ、人事、そして一部の管理職との間で、「この仕組みは何をしないのか」を共有することだ。評価は奪わない。決定は覆さない。管理職を査定しない。
あくまで、人をどう見ているかを整理し、言語化し、納得をつくる手助けをする。この前提が腹落ちしないまま全社展開をすると、「人事の監視装置」「評価を横取りする組織」と誤解され、現場から拒絶されるだろう。その上で、初年度は必ず対象を絞るのだ。全社員ではない。全管理職でもない。離職が多い、若手が多い、評価に悩みが溜まりやすい部門を2つから3つ選び、そこで始める。
この段階での主な仕事は、制度運用ではなく「対話」だ。管理職からは、部下をどう見ているか、どこに不安があるかを聞き取る。若手からは、評価や将来について何が見えていないのかを丁寧に拾う。重要なのは、ここで得られた情報を個人の悩みとして終わらせないことだ。「5年目前後で将来が見えなくなる」「評価は不満というより説明不足」「上司と本人で期待値がズレている」こうした傾向を整理し、経営と人事に返すのだ。
初年度に会社が得るべき成果は、数字ではなく、構造の理解だ。後半に入って初めて、評価制度との接続点を小さくつくる。評価面談の前後で、この専門組織が整理役として入る。管理職の判断を否定せず、「どう伝えるか」「どこまで期待しているか」を言語化する。初年度の終わりに問うべきなのは、「辞めた人数」ではない。「この機能がなかったら、もっと拗れていた案件はいくつあったか」そこが実感できれば、この仕組みは次年度に進める。
この仕組みが特に効く業界には、共通点がある。第1に、仕事が高度に分業化され、成果がすぐに見えにくいことだ。建設も製造もインフラも医療も、1人の成果は全体の中に埋もれやすい。若手ほど「自分がどれだけ価値を出しているのか」が見えない。
第2に、育成が属人的になりやすいこと。OJT、現場経験、見て覚える。これは強みでもあるが、同時に評価や期待値が言語化されにくい。結果として、「評価されているのか分からない」という不満が溜まる。
第3に、人手不足と安全・品質要求が同時に存在すること。簡単に人を入れ替えられない。失敗のコストが高い。だからこそ、本来は人を長く育てる設計が必要だが、現実にはその余裕がなく、場当たり的な対応になりがちだ。
建設や製造やインフラに加えて、医療も同じ構造を持っている。専門性が高く、年次や資格で役割が決まり、横断的なキャリアの説明がされにくい。その結果、若手ほど「この先が見えない」と感じやすい。
こうした業界では、「評価を上げる」「給料を上げる」よりも先に、自分の立ち位置を理解させる仕組みが効く。管理職が日々の業務を回しながらそれを担うのは、現実的ではない。だからこそ、管理職を責めず、評価を奪わず、その横で時間軸と構造を補完する専門機能が意味を持つのだ。
(評価と育成を組織の機能として設計し直すこと)
まとめて見よう。この取り組みは「人事施策」ではない。人をどう使い、どう残し、どう価値に変えるかという、経営の話だ。転職しても給料は簡単には上がらない。同業に移っても構造は変わらない。不満を持って辞める人材の多くは、使いにくいのではなく、位置づけられていないだけだ。それならば、企業がやるべきことは明確だ。採用で期待を煽るのでもなく、管理職に丸投げするのでもなく、評価と育成を、組織の機能として設計し直すことだ。初年度は小さく始める。成果を急がない。人の時間を、会社として引き受ける。この覚悟がある企業だけが、人手不足の時代に、人材を「コスト」ではなく「資産」として扱えるようになると思う。