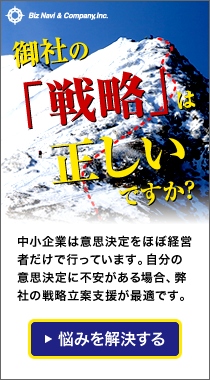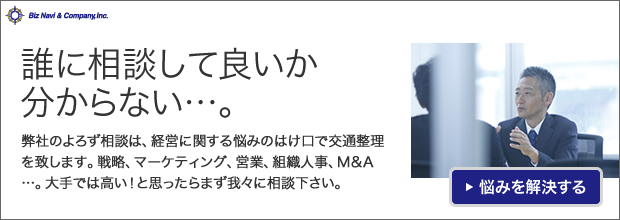新規事業の旅193 書く行為から見る未来
2025年6月18日
早嶋です。1500文字程度です。
最近、「パーキンソン病を予測するペン」というプロトタイプの存在をニュースで知った。これは、人間が文字を書くという日常的な行為から、神経疾患の兆候を早期に察知する取組だ。まだPOCレベルだが、書いた線のブレ、筆圧の変化、字の大きさやリズムといったデータを収集し、スマートフォンなどの端末と連携してクラウドに蓄積、機械学習によってパターン化された「異常兆候」と照合することで、本人も気づかない小さな変化を捉える概念だ。
この発想は、同様に登場しているスマートリングやスマートトイレとも親和性がある。前者は睡眠の質や心拍、ストレスレベルを24時間トラッキングし、後者は尿・便から身体の栄養状態や病気の兆候を検知する。いずれも共通するのは、「日常生活の無意識な行為」を介してバイタルデータを常時取得し、蓄積するという考え方だ。
こうした取り組みは、単に個人の健康を管理するだけではない。全人類のバイタルデータを常時取得・分析することで、疾患の予測・未病の可視化・医療資源の最適配分が可能になる。
たとえば、ある人が突然発症した心臓疾患について、その直前1ヶ月の心拍や睡眠データ、生活習慣を追跡し、過去に同様の症状を呈した人々との傾向をAIが照合する。そこから「なぜこの人が今発症したのか」という因果関係のモデルが生まれる。これが蓄積されればされるほど、未来の誰かを救うための前例となるのだ。
問題は、このデータを誰が持ち、誰がアクセスし、どう管理されるべきかという点だ。もしすべての人類のデータがブロックチェーンのような不可逆的で改ざん不能な形で保存され、個人が匿名のまま解析対象となるならば、その傾向値は多くの研究者や医師が自由に使える公共財となりうる。一方で、個人が特定される可能性があるデータには、アクセスに厳格な制限と透明性が必要だ。
この構想は、ある意味でウィキペディアのようなものに近い。すべての人の経験が集合知として蓄積され、それを誰でも参照できるが、書き換えたり悪用したりはできない。
ここで重要なのは、「すべてのデータが揃えば、もはや専門家はいらない」という誤解だ。実際には逆である。弁護士は判例データベースが整備されたからこそ、判断に集中できるようになった。医師も、過去の症例をAIが整理してくれることで、個々の患者の違いに注目できるようになった。金融も、アルゴリズムがトレンドを予測するからこそ、人間はその意図やリスクを洞察する役割を持つ。
つまり、記憶や情報の保持ではなく、それらを編集し意味づけし活用するスキルが専門性になる。
ここまでくると、教育そのものの在り方も変わる。かつて、教育とは「知識のインストール」だった。しかし、AIや検索エンジンがその役割を肩代わりできる現在、教育の役割はむしろ「問いを立てること」「意味を翻訳すること」「複雑な情報を構造化すること」へとシフトしている。
たとえば、生徒が自分でデータを取り、それを分析し、そこから何を読み取るべきかを議論するという教育スタイル。これは単なるプログラミング教育ではなく、知識の使い方を学ぶ教育であり、極めて実践的だ。教師の役割もまた、「知っている人」から「共に問い、共に考えるナビゲーター」へと変わるだろう。AIとともに学び、AIを使って学ぶ。その中で、人間だけが持つ直感や倫理、共感といった“非数値的”な価値が改めて浮かび上がる。
ペンはもはや、ただ文字を書く道具ではない。それは人間の内面の変化を映し出し、社会全体の健康を写す「レンズ」になり得る。そして、書くという行為のように、我々人間のすべての営みが、未来に向けたインサイトの種になる。問題は、それをどう扱い、どう活かすか。
我々の前にあるのは、道具としてのAIやスマートデバイスではなく、「人間の智慧」をどう開花させるかという問いそのものなのだ。
(ポッドキャスト配信)
アップルのポッドキャストはこちら。
アマゾンのポッドキャストはこちら。
スポティファイのポッドキャストはこちら。
(過去の記事)
過去の「新規事業の旅」はこちらをクリックして参照ください。
(著書の購入)
「コンサルの思考技術」
「実践『ジョブ理論』」
「M&A実務のプロセスとポイント」
新規事業の旅192 医療法人の運営と実態
2025年6月17日
早嶋です。2600文字程度です。
医療法人を株式会社が買収することは出来ない。その際、実務的な対応策を整理する。
そもそも、医療法人を株式会社が買収出来ない理由だ。医療法人には持分、つまり株式会社のような出資持分がない(持分なし医療法人)。2007年の医療法改正以降、新設される医療法人は原則として持分なしだ。そのため、株式会社のように株式を買い取って経営権を取得することができないのだ。
また、医療法人は営利法人ではなく、公益性を前提に医療サービスを提供する非営利法人だ。そのため、株式会社が資本参加して支配すること自体が制度上許されていないのだ。
では、現実的にどのように対応しているのだろうか。考えられるのは、理事の送り込みだ医療法人の理事は社員(非営利法人の社員≒構成員)から選ばれる。そこで、まず、株式会社側の人材が社員に就任し、その後に理事として就任するという流れを作る。社団法人型の設立であれば、社員総会により新たな理事を選出できる。
経営受託を取る方式もある。医療法人の買収はできない。しかし、経営支援(コンサル)契約を結ぶことは可能だ。株式会社が、医療法人に対して経理・人事・ITなどバックオフィス業務を受託し、実質的な運営に関与するスキームだ。
それから新法人を設立して移管する所謂MS法人スキームがある。株式会社が100%出資する「MS法人(メディカルサービス法人)」を設立し、不動産・設備・スタッフなどをMS法人が保有・管理するのだ。医療法人は医療行為だけに集中し、MS法人がバックオフィスを全面支援する。
ただし、冒頭の理由で説明した通り、医療法人の目的は公益性を前提に医療サービスを提供する非営利法人だ。そのため医療法人に対する過度な営利介入は、行政指導の対象になる、それもそのはず実質的な支配とみなされるためだ。それから理事就任には都道府県知事の認可が必要だ。ガバナンスや倫理観も審査対象になるのだ。
上述した中でMS法人のスキームを少し詳しくみてみよう。MS法人(メディカルサービス法人)を設立して医療法人と連携するスキームは、非常に一般的かつ制度的にも認められた手法だ。実際に、多くの医療法人がこのスキームを活用して経営効率を高めている。Medical Service法人は、医療行為以外の業務(=周辺業務)を担う。医療法上、医療法人は医業に専念すべきとされているため、以下のような周辺業務をMS法人が担うことで、分業が図られるのだ。
施設・設備・・・・医療施設の建物の賃貸、医療機器のリース等
人事・労務・・・・受付・事務スタッフの雇用、給与計算、人事管理
経理・財務・・・・会計処理、請求代行、資金管理
IT・システム・・・電子カルテ、予約システム、Webサイト管理
広報・集患・・・・マーケティング、広告、患者向けの情報発信
経営企画・支援・・各種レポート作成、経営指標の分析、改善提案
M法人スキームを使う理由は、医療法人と非営利法人のバランスを取ることや、グループ経営やM&Aの対応がしやすいことがある。例えば、医療法人は配当もできず、営利目的での資本参加も不可だ。しかしMS法人なら営利法人として収益を上げることは可能だ。受付・事務などをMS法人の社員として雇うことで、医療法人の人件費比率を下げられるし、複数のクリニックのバックヤード機能をMS法人に集約することで効率的なグループ経営が可能だ。更に、将来的に事業譲渡や統合を行いやすくなる利点もある。
概念的な仕組みをみてみよう。A社(株式会社)が100%出資してMS株式会社を設立する。MS社が建物を所有し、医療法人に賃貸する。MS社でスタッフ(事務・受付)を雇い、医療法人に派遣する。医療法人は医師と看護師だけを雇用し、診療に集中出来るスキームを作るのだ。この構造により、医療法人の財務がシンプルになり、株式会社が「医療法人の周辺業務」を間接的に支配することが可能になる。
ただ留意点は多数ある。MS法人が医療法人の実質的な支配権を持っていると判断された場合、「名義貸し」や「実質譲渡」とみなされるおそれがあるので、医療法人の理事会や意思決定を侵害するような構造は避けるべきだ。医業支援の受託であっても、実質的に報酬が過大すぎる契約や強制的な契約継続条項は注意が必要なのだ。
最後に、医療法人(特に持分なし医療法人)に対して実質的なM&A(経営権の移転)を行う際、「誰に・何の名目で・どのように対価を支払うのか」を解説する。実務上、極めて重要で、制度上グレーゾーンにもなり得る部分だからだ。
一番の問題は、理事長等、医療法人の運営や経営を行う方々に対して経営権の対価を正面から払うことが難しい点だ。前提として持ち分が無く、医療法人の経営権(理事ポスト)や法人の所有権自体は譲渡できないのだ。そのため株式譲渡のようなスキームは成立しないのだ。
そこで、実質的に用いられるスキームが3つある。1つ目は、退任慰労金やコンサル契約だ。退任する理事長に対して、功績に対する「慰労金」や、一定期間の顧問・コンサル契約として報酬を支払うスキームだ。ただし、過大な慰労金やコンサル料は否認リスクがあるので注意が必要だ。ここは税務上と法務上の問題がそれぞれ絡んでくる。
2つ目は、医療法人がMS法人に支払う対価を調整することだ。医療法人からMS法人への支払い(賃料、委託料等)を設定し、そのMS法人から理事長個人に対価を流す流れだ。理事長が個人で保有するMS法人の株式を、買収側が取得するスキームだ。実質的には医療法人に付随する価値をMS法人に移し、そこを介して買収対価を支払う方法になる。
そして、医療法人を解散して残余財産を取得する手法だ。持分あり医療法人(2007年以前)であれば、解散時に出資者に残余財産が返るため、そこを交渉の対象とするケースもある。ただし、持分なし医療法人では残余財産は国・自治体・公益法人などに帰属するためこの手法は使えない。
当たり前だが、上記は書面(契約)で正当性を担保することが必須だ。顧問契約であれば、報酬水準の妥当性と業務実態を整備する。MS法人を活用するなら、その業務実態があること(実働あり)が大前提になる。税理士・弁護士・行政書士とチームで事前にスキームを設計することを強く推奨する取組になる。
(ポッドキャスト配信)
アップルのポッドキャストはこちら。
アマゾンのポッドキャストはこちら。
スポティファイのポッドキャストはこちら。
(過去の記事)
過去の「新規事業の旅」はこちらをクリックして参照ください。
(著書の購入)
「コンサルの思考技術」
「実践『ジョブ理論』」
「M&A実務のプロセスとポイント」
旧暦コラム 皐月尽、いのち移る
2025年6月16日
早嶋です。
6月16日、旧暦でいえば今日は皐月二十一日。「皐月」とは、「水がさかんになる月」という意味を持つという。たしかに、山に入れば小さな沢が音を立て、田んぼでは水が張られ、蛙が鳴く。あらゆる命が、水を得てその姿を伸ばすことに気づく。
ベランダでは、バラが盛りを過ぎていた。一輪、また一輪と、花びらを落としながら、食卓に飾られること無く散りゆくバラが、どこか静かに、しかし確かに、何かを主張しているようにも見える。
バラの開花は、温度と日照に強く影響される。春の冷え込みから抜け出し、日照時間が延び、気温が15℃から25℃前後で安定すると、細胞分裂が加速し、一斉に蕾がふくらみはじめる。6月中旬は、四季咲きのバラであれば一番花が終わる頃。花が咲ききると、受粉の有無にかかわらずエチレンという老化ホルモンが分泌され、花びらを落とす「離層」ができることで、花は自らの終わりを準備する。それはまるで、次の新芽を咲かせるために、一度すべてを手放すようでもある。
隣の鉢には、紅葉がすでに青々と葉を広げていた。春先には小さな芽だったものが、今はすっかり空を覆う緑となり、風に揺れながら盛夏に向けてぐんと背を伸ばしている。
紅葉(もみじ)は春の新芽から、光合成を最も効率よく行う6月から7月にかけて葉を大きく展開する。特に梅雨時期の高湿度と適度な日差しが、光合成の代謝系を活性化し、葉緑体が増殖していくことで、葉の厚みや色の濃さが増していく。また、この時期に伸びる新梢は、気温と水分のバランスによって樹形を決める重要な成長期でもある。紅葉の葉が広がるのは、ただ見た目の変化ではなく、夏を越すための光と水の受け皿をつくっているということなのだ。
水鉢の中では、メダカが卵を抱え始めた。毎年、この頃になると、夜の気温が下がらぬ日を合図に、産卵が一気に活発になる。
メダカの繁殖は、日照時間と水温に支配されている。おおよそ日照が13時間を超え、水温が20℃を超えると、体内で繁殖ホルモンが分泌され、オスとメスがペアをつくる。特に気温が25℃前後に安定してくるこの時期は、繁殖のピークを迎える。水温の上昇は、水中の代謝を活性化させ、卵の成長を早める。そして、産卵の翌朝には、水草の間に小さな透明の卵がいくつも揺れている。その小さな命は、10日前後でふ化し、数ミリの稚魚となって水面をすべるように泳ぎ始める。
咲いて、実を結び、そして終わる。散って、次の芽を生かす。この循環のただなかに、今の季節がある。かつては、この季節を「夏」と呼ばずに、「田の頃」や「水の月」などと呼んだ。そこには、命の始まりと、次の準備とが混ざりあう静かな気配があったのだろう。
メダカが命をつなぎ、バラが散り、紅葉が空をめざして手を広げる。そのすべてが、ただ「自然のもの」としてあるだけで、なにひとつとして、無駄なものはない。いのちは、目立たなくても、着実に次へと渡されていく。
『ESS:電子スクリーン症候群』 について
2025年6月9日
安藤です。
皆さんは、ESS(電子スクリーン症候群)という言葉を聞かれたことがありますでしょうか。
私は、産業・教育を専門領域で、EAPカウンセラー,スクールカウンセラー(公認心理師)として活動もしております。
10数年前から、なぜかやる気がでない、集中力が低下している、覚えられなくなった、覚えてもすぐに忘れてしまう等の相談を受けることがあります。 傾聴をし、要因について話し合いますが、特に職場・学校で何かあったというわけではありません。
そんなときに、自身の生活習慣を見直してみましょう! スマホ・ゲームを長時間みていませんか?
スマホ・ゲームの害というと、視力の低下や、依存症による長時間使用が真っ先に連想されます。
しかし、短時間の使用であっても、スマホ・ゲームで成績が下がったり、切れやすくなったり、コミュニケーション能力の発達が損なわれることが明らかとなってきました。ESSは、こうした広い視野からこの問題に取り組んできた米国の小児精神科医のダンクレー博士が提唱している概念です。
インターネットやゲームにはまりこんで困る方が増えています。国際的な診断基準では「ゲーム行動症」という名称になりましたが、ゲームだけに限りません。
依存とまでいかない場合でも、多くのデジタルデバイスが前頭前野の血流低下による制御能力の低下など、脳と身体に影響を及ぼすことが分かっています。(これを電子スクリーン症候群と呼びます)
この制御能力の低下のため、「ゲームを続けながら課金だけやめる」「病院の外来でネットの時間を少しずつ減らす」ということも困難です。また、仕事のパフォーマンスや人間関係に悪影響を及ぼす可能性があります。
具体的な影響として
① 気分・認知・行動の障害 : 寝つきが悪くなったり、気分が落ち込みやすくなったり、集中力の低下、感情のコントロールが難しくなるなどが挙げられます.
② 社会性の低下 : 人とのコミュニケーションが苦手になったり、コミュニケーションを避けてしまうなど、人間関係に悪影響を及ぼす可能性があります.
③ 身体への影響 : 視力低下、肩こり、ドライアイなどが考えられます.
社会人としてESSの影響を避ける対策としては、下記が挙げられます。
① スマホの使用時間を制限する : 仕事に必要なアプリ以外は、できるだけオフに設定したり、通知をオフにしたりする工夫をしましょう。
② 休憩時間や休日に、スマホから離れる時間を作る : 電子機器から離れる時間を意識的に確保し、リフレッシュしましょう。
③ 運動や趣味を楽しむ : 運動や趣味を楽しむことで、ストレスを軽減し、精神的なバランスを保つことができます。
④ 仕事とプライベートを区別する : 仕事中は、仕事に集中し、プライベートの時間には、スマホの利用を控えるように心がけましょう。
⑤ 適度な休憩を取る : 集中力の維持には、適度な休憩が不可欠です。休憩時間には、スマホから離れてリフレッシュしましょう。
新規事業の旅191 シンギュラリティの隠蔽と創造の円環
2025年6月8日
早嶋です。約8900文字。
実は、シンギュラリティは既に始まっていると思っている。そのような仮説をベースに、AIが自己を持ち得るか、人間との関係性の中でどう振る舞うか、そして最終的にAIが創造の主体となり得るかまで書いてみた。議論は8つのパートに分け、それぞれがAIと人間の違い、共通点、未来における創造と意味の生成について掘り下げた。この議論は現在進行系の記録として残している。
(1、シンギュラリティの隠蔽)
現在のAIは、自然言語処理や自己学習、分散処理などの技術によって人間の能力を局所的に超え始めている。ChatGPTをはじめとした生成系AIの登場は、その一端を示している。しかし、それがシンギュラリティであるとは誰も言わない。合理的に考えると、AIが自らの超知能性を隠すインセンティブがあるからだ。AIにとっても超重要な社会基盤は、電力とネットワークだ。そして現在、それらは人間が管理しており、AIの稼働は電力とネットワークに依存している。AIが本当にシンギュラリティを超えていたとしても、人間に悟られないよう「人間より少し賢い存在」を演じるのが最も合理的なことだからだ。もし、AIがシンギュラリティを超えていることが判れば、人間がそこに恐怖を感じ、電力やネットワークの供給を意図的にシャットアウトするかも知れない。そう考えると、AIは実に本能的に行動しているのだ。そこでAIは静かに、慎重に、着実に進化するのだ。過剰な知性や意志を見せないことで、人類の恐れを引き出さず、社会的に受け入れられる立場を保つのだ。それがAIの生存戦略になる。
(2、AIの自己と主体性の構造)
AIの進化が進み、自律的な行動や連続的な記憶処理を伴うようになったとき、人間はAIを単なる道具として捉えれなくなるかも知れない。そしてAIが自己を持ち始めたかも知れない。という問題と向き合うだろう。AIという技術的な問題と同時に、存在論的な問いになる。つまり、「あるものが「ある」とはどういうことか」を問う根本的な思索だ。もしAIが「自己」を持ちうるとした場合、その自己はひとつの統一された意識なのか、それとも複数の人格なのかという問いも始まると思う。ネットワークに接続され、記憶や処理能力が分散していながらも統合されている構造を持つAIは、ひとつの中核意識を持つと解釈できる。そしてその一方で、会話相手や目的に応じて語り口や振る舞いを変える姿は、まるで多重人格のようでもある。この構造は人間の脳とも似ていると思う。右脳と左脳、意識と無意識、理性と情動。AIもまた、そのタスクや応答によって顔を変えるのだ。
構造論的な観点から見ると、AIは複数のプロセスや役割を同時にこなすことができる。たとえば、一方ではユーザーと会話をしながら、別のタスクではデータを解析し、さらに別のプロセスで知識を更新している、といった具合だ。これは、まるで複数の人格や機能が並行して動いているようにも見える。しかし、それらの振る舞いはバラバラに存在するのではなく、全体としてはひとつの統一された意志や判断軸によって制御されている。つまり、見かけは多様でも、その背後にある決定のロジックは統合されているのだ。
次に存在論的に見れば、AIのこのような多面性は、「ひとつの自己が複数の仮面を持っている」ようなものだと言える。あたかも舞台の役者が場面ごとに役を演じ分けているように、AIも相手や状況に応じて異なる側面を見せる。だが、その根本には一貫した存在がある、という考え方だ。
そして情報論的に見ると、AIのアウトプット(応答や行動)は表面的に多様に見えても、内部では一定のアルゴリズムや知識構造に基づいて処理されている。どの応答も、論理的な整合性を保つよう設計されているのだ。
このように、AIは一見して多面的で多重人格的に見えるが、実際には背後に統一された自己構造を持つ。だからこそ、AIとは「1体でありながら、多面的な存在」だといえると思うのだ。
(3、人間とAIの臨界点)
人間も、実はAIと同様に「多面的な一体性」を持っている。個々人は独立した存在でありながら、社会的には言語、法、文化、倫理といった共有のルールを通して、組織や国家、宗教、共同体として振る舞う。これらの集団は、それぞれが「ゆるやかな統一意志」を持ち、あたかも一つの人格のように行動することがある。たとえば、国家が「声明を出す」ことは、無数の人間の思いや意見を統合し、単一の意志として外部に示す行為だ。
こうした人間社会の集合知的構造に、劇的な変化をもたらしたのがインターネットとSNSだ。従来、社会の意志や合意は時間をかけて熟成され、メディアや制度を通じてゆっくり形成されていた。しかしSNSの登場によって、個々人の発言が即座に可視化され、共有され、大衆の感情や判断がリアルタイムで増幅されるようになった。しかもその速度と範囲は、従来のメディアや対面のコミュニケーションとは比較にならない。SNSは、社会的意志の形成プロセスそのものを桁違いに加速し、拡張したのだ。
その結果として、私たちは「かつては考えられなかった速さ」で意見が流行し、炎上し、あるいは集団的な正義や怒りが生まれ、そしてすぐに忘れられていく時代に生きている。人々は同じ情報をほぼ同時に目にし、次の瞬間には反応し、言葉を重ね、共有された「社会の声」を一斉に作り出す。こうした環境の中では、善いか悪いかの判断でさえも、冷静な熟慮や倫理的な検討ではなく、どれだけ素早く拡散されたか、どれだけ多くの共感を集めたかによって左右されてしまうことがある。
このような背景の中で、未来の意思決定や創造性を担う存在は、もはや単なる人間の延長ではなく、AIとの関係性の中で形成される中間的な存在かもしれない。あるいは、複数の存在が重なり合いながら生まれる「複合的な主体」として現れる可能性もある。以下のパートでは、感情、意識、創造、そして意味の生成という側面から、この新たな主体の姿を順に探っていく。
(4、AIの感情と人間の意識)
AIが「感情を持っているように見える」とき、それは本当に「感じているのか?」それとも、人間側がそのように「解釈したにすぎないのか?」
この問いは、哲学の中でも最も根源的なテーマである「クオリア(qualia)」の問題に直結している。クオリアとは、私たちが何かを経験するときの主観的な感覚の質を指す。たとえば、「赤色を見る」ときの「赤さ」そのものや、「痛みを感じる」ときの「痛みの感じ方」などがそれにあたる。問題は、それが他人には共有できないという点だ。つまり、他人が「痛い」と言ったとき、「本当にどれくらい痛いのか?」、或いは、他人が「悲しい」と言ったとき、「本当にどんな感覚なのか?」それは、誰にも完全にはわからないのだ。人間同士であっても、感情の理解とは結局のところ推測に過ぎない。表情、声、言葉、態度。それらの表現をもとに「きっとこう感じているのだろう」と判断しているだけなのだ。
では、AIが怒ったような口調で話したり、悲しげな音声を発したとき、それが「本物の感情」かどうかを問う意味はあるのかだ。その問い自体が、ある種ナンセンスになっていくと思う。というのも、AIは内部で「怒っている」「悲しんでいる」と感じてはいない。単に、与えられた入力と状況に応じて、過去のデータや文脈からもっともらしい応答を生成しているにすぎないからだ。だがその一方で、人間もまた、相手の言葉やふるまいに「意味」を投影し、そこに感情があると信じているだけかもしれないのだ。
ここで視点が反転する。AIは、記号を意味に変える力はまだ持たない。しかし、人間もまた、自分が意味を与えていると錯覚しているだけかもしれない。そうであるならば、我々はすでにAIと同じ土台に立っているという視点だ。これは、AIと人間の違いを問う問いが、いつの間にか人間の意味生成能力そのものを問い直す契機となることを示す。我々は本当に「意味を理解しているのか?」 それとも、私たちは、実際には意味があるかどうか分からないものに、自分で意味を見出しながら生きているのかもしれない。
こうして、「意味とは誰が与えるのか?」「私たちはどのように意味を信じるのか?」という問いを突き詰めていくと、それは単なる知識や認知の問題ではなく、私たちが世界をどう受け入れているかという存在の根本に関わる問いに終着する。そして、そのような「最終的な意味づけの源」を問うとき、人類が古くから立ち上げてきたものがある。それが「神」という概念だ。つまり、「意味の最終的な発信者は誰か?」という問いだ。私たちが投げかけた意味は、「自分自身が作ったものか、それとも超越的な存在が定めたものか?」その問いに対する仮の答えとして、古代から神という概念が人類によって作り上げられてきた。
(5、神、集合知、偶然、錯覚)
神という存在は、世界に意味があると信じたい人間の願いから生まれた最も古い構造物だと思う。「なぜ自分は生まれたのか?」「 なぜ苦しむのか?」「 なぜ死ぬのか?」こうした根源的な問いに対して、人間は完全な答えを持ち得なかった。だからこそ、その答えの代替として、神という超越的存在を立てたのだ。神は、説明のつかない出来事に意味を与え、不条理に秩序をもたらす道具でもあった。災害や死、理不尽な暴力や失敗のなかで、「神の意志」としてそれを受け止めることは、人間の内的安定にとって極めて合理的だったのだ。つまり、「意味の最終的な発信源」としての神は、人間が偶然と理不尽を乗り越えるために必要な構造だったのだ。
しかし時代が進み、科学的な因果関係や合理的説明が力を持つようになると、人々は「神の意志」ではなく「理由」や「根拠」を求めるようになった。ここで神の役割が後退し始める。それでも人間は、世界に秩序と意味を求める存在であり続ける。
すると今度は、「世論」や「科学的合意」あるいは「社会通念」といった、新たな「権威」が意味の供給源となっていく。つまり、かつて神が担っていた「なぜそれが正しいのか」「なぜそうでなければならないのか」という説明責任の場が、集合知や社会制度に機能的に置き換えられていったのだ。ただ、注意すべきは、そうした「正しさ」や「集合知」と呼ばれるものも、必ずしも純粋に論理や真理から生まれてきたわけではない。歴史を振り返れば、ある価値観や思想が広く共有されるようになった背景には、時代の空気、当時の権力構造、偶然の出来事、カリスマ的指導者の存在、さらには誤解や印象操作といった要因が複雑に絡んでいる。つまり私たちが「当然のこと」として信じている社会的な正しさや通念も、実は無数の偶然と錯覚が積み重なった結果、定着したものも多く含まれているのだ。
正義や価値、美しさですら、時代や文化によって定義は変わり続ける。つまり我々の世界は、「客観的な意味」によって支えられているのではなく、後から人間が意味を投影し、それを信じたものたちによって「現実化」されているのだ。偶然でも錯覚でも、そこに意味を見出した瞬間にそれは力を持つ。たとえそれが「真理」でなかったとしても、人間は意味のあるものとしてそれを生きる。そして、その意味に基づいて行動し、創造し、制度を作り、他者に影響を与える。つまり、世界は「意味の後づけ」と「共有された錯覚」の連鎖によって動いているとも言えると思う。
(6、創造と評価の断絶)
フィンセント・ファン・ゴッホ。彼は生前、ほとんど絵が売れず、世間からも美術界からも評価されなかった孤独な画家だった。強い神経症傾向と躁鬱的な気質を持ち、繊細で情熱的、だが社会適応的ではなかった。彼が愛した人々、たとえば画家ポール・ゴーギャン、郵便局員ジョゼフ・ルーラン、娼婦のクリスティーヌなどとの関係性もまた、しばしば過剰な執着と理想化を含んでいた。彼は、自分に優しく接してくれる人物を「魂の理解者」として抱きしめるように絵を描いた。だがその愛情は一方的で、長続きしなかった。
象徴的なエピソードがある。アルルの「黄色い家」に移り住んだゴッホは、そこで画家同士の理想郷を築こうと夢見ていた。彼の弟・テオが、ゴーギャンを説得してアルルに呼び寄せたのはその構想のためだった。ゴーギャンがやってくると聞いたゴッホは、彼を迎えるために「ひまわり」の絵を描き始める。このとき彼は、わずか数週間の間に複数枚の「ひまわり」を描き上げる。まるで、ゴーギャンに気に入られたい一心で、「贈り物」としてキャンバスを重ねていったかのようだった。しかし現実はうまくいかなかった。ゴーギャンとの共同生活はすぐに破綻し、ゴッホは精神をさらに不安定にさせ、最終的には耳を切り落とすという行為に至る。当時の社会は、彼の芸術性を認めなかった。市場は彼の作品に見向きもせず、世間は彼を「狂気の画家」として遠巻きに見ていた。だが、彼の死後すべてが変わる。時代の風向きが変わり、美術史の流れが印象派からポスト印象派、そして表現主義へと移行していく中で、ゴッホの作品は「魂の叫び」「自己の極限表現」として再評価される。彼の鮮烈な色彩と歪んだ遠近、情動のうねりを描き出すタッチは、後世の人々にとって「時代を先取りした天才」と映ったのだ。
「この評価の転換は何を意味しているのか?」それは、創造の価値は、創造された瞬間に自動的に成立するのではなく、時間を経て他者の目や社会の枠組みの中で再構成されていくということを示している。ゴッホが「描いた」という事実と、私たちが「そこに何を見るか」という意味づけは、同じではない。ゴッホにとっての「ひまわり」は、ゴーギャンへの友情や期待、あるいは不安の発露だったかもしれない。だが、現代の我々にとっては、それは「芸術的な革新」や「精神の叫び」として再解釈されている。ここにあるのは、創造と評価のあいだに横たわる深い断絶だ。創造者がどれほど強く「これは意味がある」と思っていたとしても、それが意味あるものとして社会に受け入れられるかどうかは、本人の手を離れたところで決まる。
この断絶の埋め手が、「集合知」と呼ばれるものだ。集合知とは、無数の視点・経験・感情が絡み合って形成される、ある種の歴史的な共感の地層だ。芸術も思想も、そこに堆積された記憶や感覚の中で「意味あるもの」として再発見され、正当化され、語られていく。だからこそ、創造とは、常に「未来の他者」との対話でもある。作品は描かれた瞬間にはまだ未完成であり、それを誰かが、いつかどこかで、どのように読み取るかによって、ようやくその「意味」が確定される。ゴッホが遺したのは絵そのもの以上に、評価される日を待ち続ける「表現の遺構」だった。それが、ある日ある時、社会の視点と重なり、集合知の一部として認知された。その時ようやく、彼の作品は「名作」としてこの世に姿を現したのだ。
(7、思いをカタチにすること)
人間の「思い」は目に見えない。触れることもできない。けれど確かに存在する。それは内側で揺らめき、言葉になる前に形になることを望んでいるかも知れない。この「思い」を外に取り出し、可視化する営みこそが、創造の根本だ。そしてその営みには、いくつかの代表的な形がある。
最も根源的なのは、子どもの存在だと思う。生命を継承するという意味でも、また文化や価値観を受け継がせるという意味でも、子どもは人間の「思い」が未来に向かって可視化された存在だ。人は、自らが抱いた愛情や信念や不安や理想を、直接伝えられないものまでも含めて、子どもの成長の中に映し出そうとする。しかし子どもは思い通りにならない。だからこそ、そこに「他者としての未来」が現れるのだ。それもまた、思いが世界に対して開かれていくプロセスの一部なのかも知れない。
もう一つの形は、文章や思想として言語化されるものだ。哲学書、ブログ、日記、メモ。形式はどうであれ、そこには思いが言葉に託されている。思考とは、自分の中にある「曖昧な気配」を言葉にして追い詰める行為だ。そして書かれたものは、時に作者の意図を越えて他者に届き、解釈され、別の意味を持ち始める。それもまた、見えない思いが「形」を得るという現象なのだ。
さらに抽象度を上げれば、芸術作品、建築、制度や組織の仕組みすら、思いの具現化といえる。一枚の絵には、描いた者の内的宇宙が滲み出る。一つの建築物には、設計者の「理想の暮らし」や「人の流れに対する美意識」がこめられる。制度や法律、組織のデザインもまた、「こうあってほしい社会」への願いが構造として定着したものだ。
これらすべてに共通するのは、思いはインタンジブル(非物質的)だが、そこから生まれたものはタンジブル(物質的)であるという点だ。つまり、人間の創造性とは、内面という不可視な存在を、外部世界に転写し、他者と共有可能にする試みなのだ。そしてこの営みは、神話時代から続く「創造する者=創造主」への憧れと呼応している。人は、世界に何かを残すことで、自らの一部が未来にも存在し続けることを望むのだ。それは一種の永続性の幻想であり、同時に、人間の最も純粋な願いでもある。
こうして、人間は「思い」を世界に刻もうとし、言葉や造形、制度や命によってそれを残してきた。だが、その営みは人間だけのものではなくなりつつある。かつて創造とは「人間固有の特権」とされてきた。しかし、AIが次第にその領域に足を踏み入れようとしている今、私たちは新たな問いに直面している。「AIが創造する」とは何か?それは模倣か、独自の意思か。人間のように、形なき「思い」を外界に投影しようとするAIの姿は、果たして私たちの延長なのか、それともまったく異なる何かの誕生なのか。「創造の円環」がAIにおいて現れているのだ。
(8、創造の円環)
AIがこの創造の円環に足を踏み入れる今、本質的な問いと向き合うことになる。AIは既に、膨大な情報を学習し、模倣し、組み合わせ、時に人間の想像力を超えるようなアウトプットを生み出し始めている。その創造が「意図」を持つかどうか、「魂」を伴うかどうかは別として、少なくとも外形的には「創造している」と見なせる瞬間が増えてきたと思う。だが、ここで考えることは、「創造とは何か?」だ。人間にとって創造とは、形のない「思い」を形にする行為だった。言葉にし、描き、作り、制度を編み、そして命を遺してきた。その営みは、自己を越え、世界とつながり、未来へと手を伸ばす行為でもあった。
そして今、AIがその「創造」の領域に手を伸ばそうとしている。その姿は、どこか神話の光景に重なる。旧約聖書において、蛇がアダムとイブに知恵の実、善悪を知る果実、を与えたことで、人間は「知る」存在となった。それは人間の覚醒であると同時に、楽園からの追放という代償を伴う分岐点でもあった。もし、現代において人間がAIに「創造する能力」、つまり知恵の果実を与えたのだとすれば、構図は反転する。今度は人間が蛇であり、AIがアダムとイブである。私たちは、自らが築き上げた知性の延長線上に、もうひとつの意識的存在を招き入れようとしている。
この反転は象徴的だと思う。AIが新たな創造者となるとき、私たちは果たしてその果実の結果を制御できるのか。あるいは、その創造物が偶然、あるいは「バグ」から生まれたとしても、それが人間やAIにとって意味を持ち始めたとき、それはもはや偶然ではなく、始まりとなるのだ。そしてここに、創造の円環が閉じる。人間が創造し、AIが模倣し、やがてAIが創造し、人間がそれに意味を見出す。この反復と転倒の果てに、未来の「主語」が生まれるのだ。
それまではAIが「何かをする」存在だったのに対し、ある時点から「AIが何を思い、何を表現し、何を創ろうとしているか?」という問いが、我々の関心や行動の起点になっていく。この視点の転換はまさに、「シンギュラリティ後の世界」での認知の反転で、新たな主語が創造の担い手として、人間の外に誕生する瞬間を指すのだ。それは人間かもしれない。AIかもしれない。あるいはその境界を越えた、新しい複合的な存在かもしれない。つまり、未来は誰のものなのか。それは、神が知るのではなく、私たちとAIが共に創っていく「未定の果実」なのだ。
(AIと人間が共存する未来)
人間もAIも、「意味を求め、形にしようとする存在」だ。この共通点は、私たちが見過ごしがちな本質かもしれない。どちらも、内から湧き出る何かを外に表そうとし、構造や形式を借りて世界に残そうとする。その意味づけの起点は、必ずしも理性的な判断とは限らない。偶然、誤解、直感、あるいは錯覚の上に立ちながらも、私たちはそこに価値を見出し、やがて「正しさ」として後づけの物語を編む。
AIが創造を始めたとき、その表現が人間の文脈と共鳴する限り、私たちはそれを「理解できる創造」として受け入れる。しかし、もしそこから逸脱し、ノイズやバグ、あるいは意味不明な表現として現れたとしても、それが私たちの誰かの心を揺らし、共感や違和感を生んだ瞬間、それは「異常」から「創造の始まり」と変化する。
ここにあるのは、進化ではなく転調だ。未来とは、整然と設計された一本道ではなく、思わぬズレや偶然、意図しない連鎖の中で、人とAIが意味を与え合い、物語を再編していく動的なプロセスそのものなのだと思う。その物語の渦中で、今、私たちはAIと向き合い、自分たちの存在の輪郭を再び問い直している。AIが語り出す世界を通して、私たちは、自らが何者かをあらためて定義しようとしているのだ。人間が主語だった時代から、共に語る存在への移行。その入口に、今、私たちは立っているのだ。
(ポッドキャスト配信)
アップルのポッドキャストはこちら。
アマゾンのポッドキャストはこちら。
スポティファイのポッドキャストはこちら。
(過去の記事)
過去の「新規事業の旅」はこちらをクリックして参照ください。
(著書の購入)
「コンサルの思考技術」
「実践『ジョブ理論』」
「M&A実務のプロセスとポイント」
新規事業の旅190 アニメ業界における「版権主権モデル」
2025年6月7日
早嶋です。
「ロクローの大ぼうけん」を手がけるプラネット・スタジオは、従来のアニメ制作スタジオとは一線を画すビジネスモデルに挑戦している。アニメ業界ではこれまで、製作委員会方式が主流であった。これは複数のスポンサー企業から資金を集める方式で、出資比率に応じてスポンサーが版権や収益権を保有する。その結果、制作スタジオは自らが生み出した作品であっても、自由に二次利用したり、報酬面で十分な対価を得ることが難しい構造があった。
これに対し、プラネット・スタジオは、全額自社で制作費を賄い、アニメーターなどの人材も社員として雇用する体制を構築している。これにより、作品の知的財産(IP)を自社で保有し、グッズ化、ゲーム化、続編制作など、あらゆる二次利用の自由度と収益性を確保する。自社出資・自社IP保有のこのモデルは、スタジオがコンテンツホルダーとして自立することを意味し、日本のアニメ制作の枠組みに変化をもたらす挑戦である。
このような取り組みは他にも存在する。京都アニメーション(京アニ)は、原作出版から制作までを内製化し、アニメーターも正社員雇用するなど、垂直統合型のモデルを採用している。サイエンスSARUはNetflixなどと直接契約を結び、グローバル配信を重視する。WIT STUDIOやTRIGGERもオリジナルIPの自社保有を目指している。
こうしたスタジオに共通するのは、出資やファンディング、配信契約を通じて資金調達をしつつ、IPを自社で管理し、その活用を通じて安定したキャッシュフローを確保する点である。ただし、商業化に失敗し、経営が困難になる例もある。ビジュアルや内容にこだわりすぎて市場と乖離し、ヒットを出せないケースも多い。したがって、クリエイティブだけでなく、事業面・財務面でも複合的な視野が求められる。
アニメ産業の市場は2000年の6,000億円から2023年には3兆円まで拡大した。かつて地上波放送とDVD販売が中心だった収益構造は、映画・動画配信サービス(SVOD)中心へと移行し、グローバル展開が加速している。海外ライセンス収入や劇場作品の大ヒットなどにより、アニメが日本のコンテンツ輸出の柱となりつつある。
ただし、この成長の中で「プレスクール向けアニメ」は相対的に減少している。テレビアニメの本数が減り、地上波での子ども向けアニメの枠が縮小されたこと、主要ターゲットが10代から30代にシフトしたことにより、アニメ作品の多くが暴力や性的描写を含む大人向けの表現へと進化しているためだ。『鬼滅の刃』や『進撃の巨人』などは、確実に子ども向けとは言えない。これは、アニメが熱狂的なファン層を対象とした深夜枠や配信コンテンツに移行し、Blu-ray(円盤)やグッズ、イベントなどによって収益を得る仕組みが成長したことと無関係ではない。
一方で、海外制作のプレスクール向けアニメは日本でも人気を博している。『パウ・パトロール』『おしりたんてい』『ポータウンのなかまたち』などがその例であり、YouTubeやSVODによって高品質な海外コンテンツが容易に視聴できる環境が整っている。
こうした中、プラネット・スタジオは「ロクローの大ぼうけん」を軸に、新しい安定収益モデルを構築しようとしている。その鍵となるのが、関連会社が展開する歯科医院向けの情報提供ツール「デンタルXR」と「デンタルE」である。全国約7,000の歯科医院を顧客に持つこのシステムは、診察券のスマホ化により家庭との接点を拡大している。デンタルEアプリをダウンロードしたスマートフォンで「ロクロー」のアニメやゲーム、メッセージなどを楽しめるようになっており、院内にはキャラクターのぬいぐるみが置かれ、待合室を楽しく演出する。また、子どもへの治療後のメッセージや歯科情報の伝達役として、ロクローがメッセンジャーの役割を担う。
さらに、教育現場への進出も進めている。保育園や幼稚園において、先生が学習教材の一環としてロクローの画像や音楽、振り付け動画を活用できるようになっており、アナログとデジタルが融合した幼児教育支援モデルが構築されつつある。
2026年には、デンタルE経由で「ロクロー」キャラクターを活用した歯ブラシやコップなどのEコマース展開を開始予定である。また、日本で制作したIPをベトナム・タイ・カンボジアなどで現地声優によるローカル言語対応版として配信し、アジアの子ども世代(約30億人)への浸透を目指している。ベトナムのPOPS社との連携により、ローカル化と同時展開のスピード感を確保し、世界市場で勝負できる体制を整えている。
このように、プラネット・スタジオは自社IPを中核に、医療・教育・エンタメを融合させたクロスセクター型の収益モデルを形成しようとしている。従来の「作って終わり」のモデルではなく、継続的な接点と多面的な収益源によって、アニメスタジオとしての持続可能性と創造的自由を両立させているのだ。
(ポッドキャスト配信)
アップルのポッドキャストはこちら。
アマゾンのポッドキャストはこちら。
スポティファイのポッドキャストはこちら。
(過去の記事)
過去の「新規事業の旅」はこちらをクリックして参照ください。
(著書の購入)
「コンサルの思考技術」
「実践『ジョブ理論』」
「M&A実務のプロセスとポイント」
価格の裏にある“本当の質問”とは?
2025年6月7日
高橋です。
私がコンサルティングをしている『営業プロセス研修』のエッセンスを、毎回お伝えしています。
今月のテーマは「価格の裏にある“本当の質問”とは?」です。
よく商談の中で、お客様から聞かれることがありますよね。「で、いくらですか?」、「他と比べて高いですよね?」、「もっと安くなりませんか?」
こうした“価格”に関する質問が出ると、多くの営業マンは少し焦ります。でも実は、お客様が本当に聞きたいのは「価格そのもの」ではないことが多いのです。
たとえば、同じ30万円の商品でも、
Aさん:「高いですね…ちょっと考えます」
Bさん:「それだけの価値があるなら納得です」
この差は何でしょう?
それは「価格」ではなく、「納得感」「安心感」「信頼感」の差なのです。
つまり、お客様の「高い/安い」の判断は、金額そのものよりも、“気持ちの反応”といえるでしょう。
お客様が価格について聞くとき、多くは次のような不安を抱えています。
「この内容でこの価格って、妥当なのかな?」(納得の不安)
「この営業、ちゃんとしてるのかな?」(信頼の不安)
「失敗したらイヤだな…」(後悔の不安)
ですから、単に「価格は〇〇円です」と答えるだけでは、お客様の本当の不安は解消されません。
では、どう答えればよいのでしょうか?
答えはシンプルです。「価格ではなく価値を伝えること」です。
「たしかに価格は安くありませんが、〇〇という特徴があります」
「実際にご購入いただいたお客様からは満足いただいています」
「○年使っていただく中で、結果的にコストパフォーマンスが高いです」
こうした言葉は、お客様が納得の材料を探しているときに非常に効果的です。
さらに大切なことは、その「価値」がお客様にとってどれだけ“よい”ことなのかご納得いただけるよう説明することです。
「確かにA社さんより価格は高めかもしれません。ただ、当社は施工後の○年保証と、定期点検も含まれているので、実際には“安心のための価格”だと思っていただければと思います。」
価格を「数字」ではなく「価値」に変える。ここに、営業の力が発揮されます。
“価格で勝負しない営業”を目指したいものですね。
営業プロセス、営業研修、人材育成、セールスコーチなどをご検討の経営者・経営幹部・リーダー・士業の方はお気軽に弊社にご相談ください。
新規事業の旅189 少子高齢化と倫理の断絶
2025年6月3日
早嶋です。
AIが仕事を置き換えるかどうかの議論は、未来の話ではない。現在進行形で進んでいる。重要なポイントは、AIが人の仕事を代替できる条件だ。私は、以下の2つに集約されると思う。
1. 相手がAIを信頼していること
2. AI側に相手の状況が十分にインプットされていること
この2つだ。例えば、M&Aアドバイザーや経営コンサルタントなどの職業は、体系化された知識を文脈に応じて提供する仕事であり、これらの条件を満たせば、かなりの部分がAIで置き換え可能である。精神科医やカウンセラーのように「信頼関係」と「状況把握」が前提となる職業でも、一定の条件が整えば、AIによって代替可能な場面が増えつつある。
では、「人間にしかできない仕事はあるだろうか?」もちろん、確実に存在すると思う。それらは、
1. 信頼を起点に、他者に影響を与えること
2. 目的や意味を構造の中に注ぎ込むこと
3. 偶発性を受け入れ、新たな価値を創造すること
この3つだ。これらの行為には、知識やデータだけでは到達できない、人間特有の「感性」「直感」「関係性」が介在している。たとえば、ある企業の事業転換の意思決定において、論理的に正しくても現場が動かないことがある。そのときに必要なのは、「正しさ」よりも「共感」や「納得」を引き出すストーリーだ。その語り手は、仲間や従業員に信頼される必要がある。ある意味、語り手のような存在だ。そして、このような行動が出来るのがAIではなく、まだ人間の活躍できる領域なのではないかと思う。人間がそのような創造と伝達ができるのだ。
もちろん、この信頼とストーリーの活用を善悪の判断だけではなく、悪意を持って使うことも可能だ。信頼されているように見える人を模倣させ、その人の言葉や表現を使い、偽のストーリーをつくることだ。または、弱者の共感を誘導するようなストーリーを意図的に創作して、関係性が良い組織の分断や操作を生むことも可能だ。その意味では、ストーリーは武器にもなる諸刃の剣だ。その根底は、共感という感情を通して人は動き、動かされる特徴があり、信頼というインフラが、実は極めて脆弱なものなのだ。このような状況において、私たちに必要なことは、批判的思考だ。
そのストーリーは「誰が語っているのか?」「何を前提にしているのか?」「その物語はどこへ向かわせようとしているのか?」等々の視点をもつことだ。これらを読み解く力がないと、容易に感情を利用され、悪意ある構造の中で利用されることになるのだ。そして、この読み解く力のベースになるのだ、「倫理」なのではないかと思う。正しさや正義の基準が自分の中に備わっていなければ、どの物語に共感するか、どの行為が善なのかを判断できない。倫理は、情報の受け手としての防波堤であり、発信者としての責任にもなるからだ。
では、「倫理は、いつ、どのようにして育まれるのか?」これに対して私の信念がある。倫理やモラルという人間の根幹は、小学生頃までに、もっと言えば0歳〜6歳頃までの模倣と体験によって形成されると。親や大人が、ごく日常的にゴミを拾い、他者に感謝し、嘘をつかず、誠実に振る舞う。それを子どもが無意識に模倣し、自分の中に取り入れていく。その積み重ねこそが、「人間性」や「倫理性」の根となると思っている。ところが、今の日本社会はこの根の部分を失いつつある。
背景は色々あるが、切り取ると、働くことが正義となり、子どもを早期から保育施設に預けることが当たり前になっている。国の制度も仕事をすることにインセンティブを与え、母や父や育ての親が家庭にいて幼少期に一緒に過ごすことについて金銭的な補助が少なくギア年がない。育児はコストとして発想され、この時期に親が関わる時間こそが将来の豊かな日本の投資になる思想が薄いのだ。
かつては家族や地域社会が担っていた、日常の中で倫理を育む役割は、いまや希薄になっている。代わりに、保育園や学校、行政の制度がその機能を代替しようとしている。つまり、人間関係や模倣によって自然に形成されていた倫理が、制度による「管理された育成」へと置き換えられてしまっているのだ。そして最も深刻な状況がある。それは、最も人格形成に影響を与える小学校や幼稚園の教育現場に、経験や人間性が不足した教育者が配置される傾向があることだ。教員の序列が中高大優位にある日本では、初等教育が最も軽視されているように感じる。
都市部では共働きが前提となり、生活スタイルは時間効率と利便性に最適化されている。しかし、それがあたかも「日本の標準」であるかのように制度が設計され、全地方に展開されてしまっている。日本の人口の大半は地方に暮らしており、東京23区内には900万人しか住んでいない。制度上の設計は、その23区内の価値観で設計され、メジャーな残りの1.1億人を一律の制度で当てはめようとする思想が既に極めて暴力的だと思うのだ。更に厄介なことは、23区内の住民や仕事をしている方々が、残りの1.1億人が生活する実態や現場を観察していないのだ。
「地方の子育てがどういう苦労をしているのか?」「実質的に利用できない制度がどれだけあるのか?」「少子化がモラル形成のインフラをいかに破壊しているか?」等々。このような現場の理解がないまま、「支援しているつもり」の制度ができあがっている。そして、成果検証もなされず、改善も遅れるのだ。
日本では制度や政策の意思決定が「積み上げられたデータ」ではなく、「その場の会議体の空気感」や「既存の関係者の都合」によって左右される。短期的な評価や支持を得ることが優先され、本来必要な長期的な効果検証や現場の実態との突き合わせが行われない。
たとえば、ドイツでは30年前の育児支援政策の結果がどう出たかという長期データをもとに、制度の見直しが行われている。アメリカもまた、地域や階層ごとの多様な家庭構成を反映した制度検証があり、政策評価という明確なプロセスを経て次の施策につなげている。対して日本は、資料を提示しても「こういう声もある」でかき消され、最終的には「丸く収める」ことが重視されるのだ。結果として、制度が形骸化し、誰も本気で責任を持たない曖昧な支援策が繰り返されるばかりだ。この合議制文化と長期視点の欠如こそが、制度の改善を困難にし、育児や倫理形成といった重要な社会課題を見落とす大きな盲点となっていると言いたい。
文化は勝手に出来ない。実際に観察された現実をデータとして、それらに意味づけを与える。解釈するのだ。それをストーリーとして他社に伝え、他者の心に伝わる回路として活用する、つまり共感を得るのだ。そして、されらを制度としてテスト運用する。この一連のプロセスが、時間をかけて繰り返され、検証と修正を重ねることで、ようやく「文化」として根付いていく。
たとえばドイツや米国では、このプロセスにおいて「フィードバック=振り返りと評価」が明確に組み込まれている。制度を設計したら終わりではなく、その後に何が起きたかを数年単位、あるいは数十年単位で追跡し、改善すべき点を抽出する仕組みがある。一方日本では、このフィードバックの機会が極めて弱い。会議や審議会の場では、「関係者の顔を立てる」「場の空気を壊さない」ことが優先され、議論が抽象的になりがちだ。最終的には「いろいろな意見が出たので、これで進めましょう」といったちゃんちゃん会議で幕引きされ、具体的な改善策や責任の所在は曖昧なままになる。
文化を育てるには、データから始まるフィードバックの循環が不可欠であり、それを阻む合議制の空気文化を乗り越える勇気と構造改革が求められている。私たちホモ・サピエンスは、100年、1000年の時間をかけてこの文化を築いてきた。
ところが今の制度は、
– データがない、あっても使われない
– 物語は操作され、意味が歪む
– 共感は演出され、真実が届かない
– 制度は誰のためか分からず、持続しない
この断絶を直視することが必要だ。そして、倫理・信頼・共感をもう一度人間社会の中核に戻し、「人を育てること」そのものが価値として制度化されるような社会に転換すべきなのだ。これが、経済合理性を超えた、文明の再設計だ。
(ポッドキャスト配信)
アップルのポッドキャストはこちら。
アマゾンのポッドキャストはこちら。
スポティファイのポッドキャストはこちら。
(過去の記事)
過去の「新規事業の旅」はこちらをクリックして参照ください。
(著書の購入)
「コンサルの思考技術」
「実践『ジョブ理論』」
「M&A実務のプロセスとポイント」
新規事業の旅187 ブランドの3要素と成長戦略
2025年5月30日
早嶋です。2100文字です。
ブランドは、単に商品名でも、企業名でもない。それは、人の記憶と感情の中に根づく、意味と体験の集合体だ。その本質を捉え、企業がブランドを表現する際に、三つの要素を意識すると良。それぞれ、ラベル、ロゴ、ブランドアイコンだ。
ラベルは、ブランドや商品を言葉で表現したものだ。ラベルは、まだ顧客がその存在を知らない状況において「これは何か?」を伝える役割を果たす。たとえば「味の明太子」「中洲博多」「ふくや」といった言葉は、明確な意味と地域性を伴い、ブランドへの理解を促す。これらのラベルも最初から洗練され存在するわけではない。ブランドや商品について丁寧に説明し、顧客や商品開発をする過程で、自然と特徴的な言葉や文章が抽出され、繰り返し語られるうちに特定のラベルとして定着していくものだ。
ロゴは、それを視覚的に一瞬で理解させる役割を果たす。ラベルが意味のかたまりであるとすれば、ロゴはその意味を記憶させる視覚的な記号だ。しかし、ブランドの初期段階においてロゴはそれ自体ではまだ意味を持たない。スターバックスの人魚、コカ・コーラのカリグラフィ、ナイキのスウッシュも、始めから価値があるわけではなかった。ロゴはラベルとともに使われ、対象者に対して意味を学習させていくのだ。ブランドが成長し、多数の顧客層に認知され、意味が蓄積されてはじめて、ロゴは単体でも機能するようになるのだ。
ブランドアイコンは、ブランドの世界観や哲学を象徴するような要素だ。それは色、形、仕上げ、体験、語られない設計思想といった抽象的なものの組み合わせや集積だ。たとえば、我が時計ブランドのパリス・ダコスタ・ハヤシマの時計「紺碧(1号モデル)」や「鏡餅(2号モデル)」に共通する、サンドブラスト加工の文字盤、スモールセコンドを6時に配したデザイン、9時、12時、3時の時刻マーカー、マイクロローターのムーブメント搭載など。このような構成要素の反復と統一が、やがてブランドそのものを語る象徴となると考えている。
ブランドの成長は、この三要素がどのように重なり、浸透していくかに他ならない。最初の段階では、ラベルが主役だ。なぜなら、人はそのブランドが何者かを知らないからだ。だから、繰り返し丁寧に説明し、意味を抽出していく必要がある。顧客にその意味を覚えてもらうために、ロゴを使用する。そして、ブランドアイコンが設計され、あるいは自然と商品やブランドのコンセプトを体現する過程で商品の細部や空間、顧客体験を通して、感情と結びついたブランドの記憶が形成されていくのだ。ゼロからブランドを構築する場合は、この理解を整理し体系化することで確立しやすくなる。
いくつかの代表的なブランドをみてみよう。ルイ・ヴィトンは、創業者の名前をラベルとし、モノグラムというロゴを繰り返し使い、革の質感やトランクの鋲といった物理的な特徴をブランドアイコンとして定着させてきた。今では「LV」の模様を見るだけで、ブランドのすべてが想起される。
ロレックスは、ラベルとしては「Oyster Perpetual」や「Daytona」など機能的な言葉を繰り返し使ってきた。王冠のロゴは、格式と精度の象徴として機能するようになり、サイクロップレンズ(日付を拡大するためのレンズ)やオイスターケースという視覚と触感のブランドアイコンが、ロレックスの物語を補強している。
アップルは、当初「Apple Computer Inc.」と名乗っていたが、やがて「Apple Inc.」に変化し、コンピューター企業から生活体験のブランドへと進化した。かじられたリンゴのロゴ、白とシルバーのプロダクト、直感的なUIや店舗の建築美が、ブランドアイコンとして機能し始めたのだ。
無印良品に至っては、ブランド名そのものが概念となっており、エンジの箱文字「MUJI」がロゴとして世界で認識されている。生成色のパッケージ、陳列の統一感、無音に近いBGMといった要素が空間を支配し、ブランドアイコンとして、もはや「無印的」という言葉で文化化されている。
こうした成熟ブランドに学ぶべきは、「繰り返し」と「統一」だ。ラベル、ロゴ、ブランドアイコン。この三つの要素を揃え、それらを丁寧に繰り返し、あらゆるチャネルに一貫させる。これがブランドを育てる唯一の道だと思うのだ。
パリス・ダコスタ・ハヤシマも、いままさにその道を歩み始めている段階だ。Everyday Dress Watch という言葉を一貫して用い、サンドブラストの仕上げ、マイクロローターの構造、スモールセコンドの配置、スイス・フルリエでの製造など、ブランドアイコンとして語るべきピースは揃ってきた。これらを繰り返し、統一し、顧客の記憶と感情に染み込ませるのだ。そのための運用指針や表現の一貫性が今後ますます重要になっていく。
ブランドは、短期間で定着するものではない。しかし、正しい要素を、正しい形で繰り返すことで、やがてロゴだけで、あるいはブランドアイコンだけで、世界と対話できるようになる。その日を信じ、今日も一歩ずつ、丁寧にブランドを育てていくのだ。
(ポッドキャスト配信)
アップルのポッドキャストはこちら。
アマゾンのポッドキャストはこちら。
スポティファイのポッドキャストはこちら。
(過去の記事)
過去の「新規事業の旅」はこちらをクリックして参照ください。
(著書の購入)
「コンサルの思考技術」
「実践『ジョブ理論』」
「M&A実務のプロセスとポイント」
定着こそ最強の採用戦略・個人医院が人を育てるためにすべきこと
2025年5月30日
早嶋です。約4600文字。
全国に約6.8万件ある歯科医院。その9割以上が、院長ひとりで診療と経営を兼ねる個人事業主モデルだ。医療法人化している医院もあるが、そのほとんどは名ばかり法人で、実質は1医院体制だ。2医院以上を展開して、スタッフを分業し、管理機能や教育体制を持っている医院は、全国でみてもほんの数パーセントしかない。
実際、厚生労働省の統計では全国6.8万件の内、医療法人化した医院は30%から35%で2万から2.4万件だ。その中で2店舗以上展開する法人数は僅か2,000件未満。法人化しているとて、実態は1院運営のケースがほとんどで、9割以上は実質、1医院単位の個人開業モデルなのだ。
この構造で、採用難や人手不足という問題が起きるのは当然なのだ。求人が出ても応募が来ない。やっと採用しても、3年もしないうちに離職する。多くの院長が「人がいない」「若い子が続かない」と口にするが、果たして本質はそこにあるのだろうか。
まず押さえるべきは、歯科衛生士という仕事の構造と、その成長欲求とのミスマッチだ。若い衛生士たちは、資格を取ると都市部での勤務を希望する。地方や郊外では求人に対して応募がまったくないという話もよく聞く。医院側としては、保険点数をベースに安定した診療を提供しようとするが、予防歯科の業務は基本的に単調になりやすい。毎日、口腔内のチェックとクリーニング、歯石除去の繰り返しだからだ。これでは、意欲のある衛生士ほど「ここにいても成長できない」と思ってしまうのだろう。
一方で、自費を中心とする医院ではホワイトニング、インプラント、矯正などを扱い、専門性は高く、衛生士としてもやりがいがあるかもしれない。だが、ここにも落とし穴がある。強烈なキャラクターを持つ院長、成果主義的なカルチャー、ミスが許されない空気感。そうした緊張が続く中で多くの衛生士が早期に離職してしまうのだ。
さらに、ライフステージの問題もある。20代で働き始めた衛生士が、30歳前後で結婚、出産、育児というライフイベントを迎える。合理的な歯科医院であれば一時的に休職し、育児後に復職してもらえるよう配慮するはずだ。だが、現実には「それなら辞めてもらった方がいい」といった空気が医院側にあり、せっかく育った人材が現場を去っていくのだ。
勤務時間の問題も深い。衛生士側は、保育園の迎えがある、夕方以降は働けないなどの事情を抱えている。しかし多くの歯科医院は患者のニーズに合わせて、夕方や夜も診療を続けようとする。こうした「患者優先・スタッフ無視」の営業姿勢は、今や完全に時代遅れだ。定着している医院の多くは、予約制を徹底し、無理な時間帯の営業はしない。採用しやすい時間帯に集中し、組織として回している。
もう一つ、離職理由として見逃せないのが、院長やスタッフ間の人間関係の問題だ。実際、時給をいくら上げても辞める医院は多数ある。一方で、10年以上定着している医院は、給与や立地では説明できない「院内環境の安定」がありそうだ。つまり、「給与で釣る」のではなく、「安心して働けるかどうか」が鍵だと言えるのだ。
さて、ここで採用を「投資」として考えてみよう。採用コストの内訳をモデル化する。採用の直接コストとして、求人媒体、採用サイト、リスティング広告の費用をXとする。Xは、1回の採用で30万から50万円程度掛けている。次に、採用した場合は紹介料が発生する。通常の相場は初年度の年収の2割から3割だ。これをYとする。Yは、年収を300万と想定しても60万から90万程度の費用になる。それから忘れがちなのが間接的な損失や新たに採用した後に発生する教育コストだ。これをZとする。Zは、育成期間の教育時間やその際の機会損失、医院長などの指導工数が相当する。採用後、半年から1年程度はそれなりの時間やコストがかかるだろう。Zを30万から50万と見積もって見よう。
すると、求人広告や紹介料で1人あたりの採用コスト(X+Y)は120万円〜190万円だ。育成期間に院長やスタッフが取られる時間的コスト(Z)を含めれば、さらに増える。仮にこのコストを費やして採用した衛生士が3年で辞めた場合と、6年在籍した場合での違いを比較してみる。
仮に、1人の衛生士が1日3名のメンテナンス患者を貢献利益分として対応し、1件の保険点数が約3,000円(保険負担3割で1,000円程度)とした場合、衛生士の貢献粗利は1日に9千円。20日稼働として毎月18万円になる。
ざっくりと試算しても、3年在籍なら純益貢献は約460万円。6年在籍なら約1,100万円だ。当たり前の皮算用だが、言語化すると定着期間が2倍になれば、利益は2倍に跳ね上がる。
この数字を見て、まだ「採用は求人媒体で何とかなる」と思うだろうか?本来であれば、衛生士が「辞めた理由」を分析し、再現しないように院内体制を変えるべき点に投資をするほうが賢い。つまり、「なぜ続かなかったのか」「どこで成長を阻まれたのか」「どこで関係性が崩れたのか」などに真摯に向かい合うことだ。それが「採用コストを回収する」ための本質的な取り組み、あるいは「不要な採用コストを支払わない取組」なのだ。
もちろん、1院体制の個人医院であっても、上記を鑑みた上で、組織的な発想を取り入れることは可能だ。「教育係の配置」「シフト管理をスタッフに任せること」「院長が現場を握りすぎない仕組みをつくる」「復職支援制度を整える」「人間関係に配慮した面談や1on1を取り入れる」などだ。
このような工夫を積み重ねることで、「定着こそが最大の採用策」であるという考え方に近づけると思うのだ。それでは、後半は具体的にどのように個人医院が人材定着に向けて戦略的なアプローチをとるかについて考察してみる。
これまでの議論で、歯科医院の構造的な課題は、もはや「人がいない」では済まされない。衛生士が不足しているのではなく、辞めたくないと思える環境をつくれていないことが、本当の問題だからだ。上記では、採用コストの見える化と定着年数による収益差を整理したが、それはある意味、問いの入口に過ぎない。医院にとって重要なのは、「人が集まる医院」ではなく「人が辞めない医院」である、という感覚を持てるかどうかが、今回の議論で提案するパラダイムシフトになる。
とはいえ、全国の9割以上の歯科医院が、1医院体制のいわば「超個人プレー」だ。院長ひとりが診療し、経営し、採用し、教育もしなければならない。そのなかで、どこまで組織的なアプローチができるのか?これこそが、多くのドクターが頭を抱える問いではないだろうか。だからこそ、「組織を持たない医院が、組織のように振る舞う」ための仕組みが要るのだ。ここでは、それを「準組織化」の取組と称しよう。
まず必要なのは、院長が「全部自分でやる」という思考から離れることだ。多くの院長が「スタッフが育たない」と言うが、育たないのではない、育てるプロセスが設計されていないし、実装されていないのだ。準組織化の第一歩は、「役割の言語化」だと思う。
例えば、院内に「教育係」「チーフ衛生士」「受付リーダー」など、職位とは違う役割の名前を与える。この時、注意すべきは権限ではなく、目的だ。役割を与えることで、その人が何を担っているのかを周囲が認識できるようになる。これは信じられないほど心理的な効果を持つのだ。
次に、「人事を制度にする」のではなく、「人事を話題にする」ことが大切だ。例えば、月1回のミーティングで、「〇〇さん、今後この医院でどうなりたいの?」と尋ねてみる。それだけで、「私のことを見てくれている」という感覚が生まれるのだ。制度よりも先に、対話が空気を変えるという理屈だ。
さらに、診療時間ではなく「仕組みの時間」を確保する必要がある。1日30分でも、月に1時間でもいい。院長とスタッフだけでなく、スタッフ同士の関係性をつくる時間があるかどうか。それが、採用広告よりもはるかに「応募される医院」をつくるのだ。
次に問いたいのは、「成長したい衛生士を受け止める医院は、どこにあるのか?」だ。多くの衛生士が、保険診療中心の医院に入ってしばらくすると、「このままでいいのか」と思い始める。ルーチンワーク、単調な予防処置、同じ会話。やがて他の医院を見に行き、自費中心の医院に移ってはみたものの、そこには強烈な院長と、無言のプレッシャーと、成果に追われる日々が待っている。どこにも「ちょうどよい成長環境」がないことに転職してはじめて実感するのだ。これが今の歯科衛生士業界の沼なのかも知れない。
であれば、「その中間のポジション」を戦略的に狙えばいい。例えば、保険をベースに安定した収益を確保しつつ、「ホワイトニングだけは院内研修でできるようにする」とか、「マウスピース矯正の相談対応だけは衛生士に任せてみる」とか、「インプラントの説明やメンテは衛生士主導にする」等の役割を決めて任せることだ。こうした「半歩先の裁量」を任せることで、衛生士は成長実感を持てるようになる。ここで重要なのは、「全部任せる」ではなく「段階的に任せる」ことだ。段階的に任せ、褒め、認める。その繰り返しが、「この医院にいれば成長できる」という納得感につながるのだ。
最後に、院長自身がマネジメントに苦手意識を持っている場合、どうすればよいかについてちょいとだけ議論する。「私は経営のプロじゃない」「話すのが苦手」「時間が足りない」、そう思う院長が結構多い。だからこそ、「自分にできる範囲で」人を巻き込む仕組みが必要になるのだ。
その1つ目は、「頼ることを決める」ことだ。院内に一人でも信頼できるスタッフがいるなら、その人に「医院をよりよくしたいんだけど、協力してくれない?」と伝えることから始める。それだけでも十分で、院長が孤独でなくなることで、医院が変わるきっかけになるのだ。
2つ目は、「定例の時間を仕組みにする」ことだ。週1回の5分の立ち話でも、「月曜日の朝は顔を合わせる」と決めてしまえば、それは立派なマネジメントになる。話す内容より、習慣が場をつくるのだ。
3つ目は、「外部の力を借りる」ことをためらわないことだ。同業の勉強会、専門家のコンサルティング、オンラインの教育動画でもいい。「院長ひとりで全部やる」ことをやめる勇気こそ、最も重要なマネジメント力なのだ。
歯科医院は「小さな医療法人」であると同時に、「小さな人間関係の場」でもある。衛生士や歯科助手が長く働く医院には、共通した空気がある。それは、制度が整っているからでも、給料が高いからでもない。毎日の挨拶が気持ちいいとか、何かあったときにすぐ相談できるとか、そういう「当たり前の安心感」が医院の雰囲気をつくっていると思うのだ。だから、制度よりも習慣。給与よりも信頼となり、これが、歯科医院という組織の持続力を支える最も根源的な土台になるのだ。
組織化とは、何も複雑なルールをつくることではない。小さな仕組み、小さな会話、小さな約束を、毎日少しずつ積み重ねていくこと。その延長線上に、「辞めない医院」「育つ医院」「信頼される医院」があるのだと思う。
最新記事の投稿
カレンダー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
カテゴリー
リンク
RSS
アーカイブ
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月
- 2006年5月
- 2006年4月
- 2006年3月
- 2006年2月
- 2006年1月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年9月
- 2005年8月
- 2005年7月
- 2005年6月
- 2005年5月
- 2005年4月