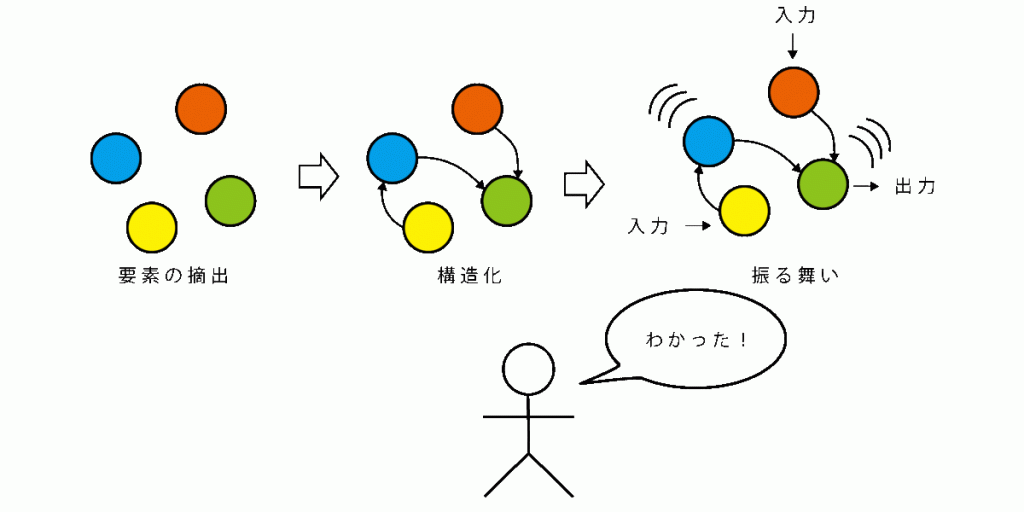早嶋です。2600文字程度です。
医療法人を株式会社が買収することは出来ない。その際、実務的な対応策を整理する。
そもそも、医療法人を株式会社が買収出来ない理由だ。医療法人には持分、つまり株式会社のような出資持分がない(持分なし医療法人)。2007年の医療法改正以降、新設される医療法人は原則として持分なしだ。そのため、株式会社のように株式を買い取って経営権を取得することができないのだ。
また、医療法人は営利法人ではなく、公益性を前提に医療サービスを提供する非営利法人だ。そのため、株式会社が資本参加して支配すること自体が制度上許されていないのだ。
では、現実的にどのように対応しているのだろうか。考えられるのは、理事の送り込みだ医療法人の理事は社員(非営利法人の社員≒構成員)から選ばれる。そこで、まず、株式会社側の人材が社員に就任し、その後に理事として就任するという流れを作る。社団法人型の設立であれば、社員総会により新たな理事を選出できる。
経営受託を取る方式もある。医療法人の買収はできない。しかし、経営支援(コンサル)契約を結ぶことは可能だ。株式会社が、医療法人に対して経理・人事・ITなどバックオフィス業務を受託し、実質的な運営に関与するスキームだ。
それから新法人を設立して移管する所謂MS法人スキームがある。株式会社が100%出資する「MS法人(メディカルサービス法人)」を設立し、不動産・設備・スタッフなどをMS法人が保有・管理するのだ。医療法人は医療行為だけに集中し、MS法人がバックオフィスを全面支援する。
ただし、冒頭の理由で説明した通り、医療法人の目的は公益性を前提に医療サービスを提供する非営利法人だ。そのため医療法人に対する過度な営利介入は、行政指導の対象になる、それもそのはず実質的な支配とみなされるためだ。それから理事就任には都道府県知事の認可が必要だ。ガバナンスや倫理観も審査対象になるのだ。
上述した中でMS法人のスキームを少し詳しくみてみよう。MS法人(メディカルサービス法人)を設立して医療法人と連携するスキームは、非常に一般的かつ制度的にも認められた手法だ。実際に、多くの医療法人がこのスキームを活用して経営効率を高めている。Medical Service法人は、医療行為以外の業務(=周辺業務)を担う。医療法上、医療法人は医業に専念すべきとされているため、以下のような周辺業務をMS法人が担うことで、分業が図られるのだ。
施設・設備・・・・医療施設の建物の賃貸、医療機器のリース等
人事・労務・・・・受付・事務スタッフの雇用、給与計算、人事管理
経理・財務・・・・会計処理、請求代行、資金管理
IT・システム・・・電子カルテ、予約システム、Webサイト管理
広報・集患・・・・マーケティング、広告、患者向けの情報発信
経営企画・支援・・各種レポート作成、経営指標の分析、改善提案
M法人スキームを使う理由は、医療法人と非営利法人のバランスを取ることや、グループ経営やM&Aの対応がしやすいことがある。例えば、医療法人は配当もできず、営利目的での資本参加も不可だ。しかしMS法人なら営利法人として収益を上げることは可能だ。受付・事務などをMS法人の社員として雇うことで、医療法人の人件費比率を下げられるし、複数のクリニックのバックヤード機能をMS法人に集約することで効率的なグループ経営が可能だ。更に、将来的に事業譲渡や統合を行いやすくなる利点もある。
概念的な仕組みをみてみよう。A社(株式会社)が100%出資してMS株式会社を設立する。MS社が建物を所有し、医療法人に賃貸する。MS社でスタッフ(事務・受付)を雇い、医療法人に派遣する。医療法人は医師と看護師だけを雇用し、診療に集中出来るスキームを作るのだ。この構造により、医療法人の財務がシンプルになり、株式会社が「医療法人の周辺業務」を間接的に支配することが可能になる。
ただ留意点は多数ある。MS法人が医療法人の実質的な支配権を持っていると判断された場合、「名義貸し」や「実質譲渡」とみなされるおそれがあるので、医療法人の理事会や意思決定を侵害するような構造は避けるべきだ。医業支援の受託であっても、実質的に報酬が過大すぎる契約や強制的な契約継続条項は注意が必要なのだ。
最後に、医療法人(特に持分なし医療法人)に対して実質的なM&A(経営権の移転)を行う際、「誰に・何の名目で・どのように対価を支払うのか」を解説する。実務上、極めて重要で、制度上グレーゾーンにもなり得る部分だからだ。
一番の問題は、理事長等、医療法人の運営や経営を行う方々に対して経営権の対価を正面から払うことが難しい点だ。前提として持ち分が無く、医療法人の経営権(理事ポスト)や法人の所有権自体は譲渡できないのだ。そのため株式譲渡のようなスキームは成立しないのだ。
そこで、実質的に用いられるスキームが3つある。1つ目は、退任慰労金やコンサル契約だ。退任する理事長に対して、功績に対する「慰労金」や、一定期間の顧問・コンサル契約として報酬を支払うスキームだ。ただし、過大な慰労金やコンサル料は否認リスクがあるので注意が必要だ。ここは税務上と法務上の問題がそれぞれ絡んでくる。
2つ目は、医療法人がMS法人に支払う対価を調整することだ。医療法人からMS法人への支払い(賃料、委託料等)を設定し、そのMS法人から理事長個人に対価を流す流れだ。理事長が個人で保有するMS法人の株式を、買収側が取得するスキームだ。実質的には医療法人に付随する価値をMS法人に移し、そこを介して買収対価を支払う方法になる。
そして、医療法人を解散して残余財産を取得する手法だ。持分あり医療法人(2007年以前)であれば、解散時に出資者に残余財産が返るため、そこを交渉の対象とするケースもある。ただし、持分なし医療法人では残余財産は国・自治体・公益法人などに帰属するためこの手法は使えない。
当たり前だが、上記は書面(契約)で正当性を担保することが必須だ。顧問契約であれば、報酬水準の妥当性と業務実態を整備する。MS法人を活用するなら、その業務実態があること(実働あり)が大前提になる。税理士・弁護士・行政書士とチームで事前にスキームを設計することを強く推奨する取組になる。
(ポッドキャスト配信)
アップルのポッドキャストはこちら。
アマゾンのポッドキャストはこちら。
スポティファイのポッドキャストはこちら。
(過去の記事)
過去の「新規事業の旅」はこちらをクリックして参照ください。
(著書の購入)
「コンサルの思考技術」
「実践『ジョブ理論』」
「M&A実務のプロセスとポイント」