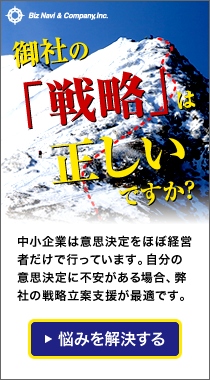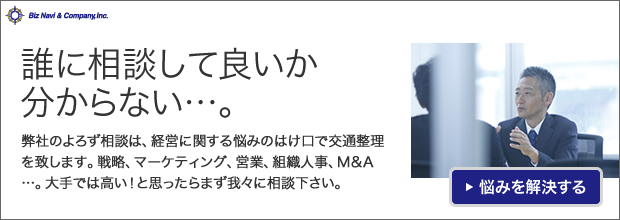早嶋です。約6000文字です。
ここ数年、生成AIを広告制作に活用する動きが、グローバル企業の間で一気に加速している。背景には、制作コストの削減やスピード向上だけでなく、「新しい表現手法」としてAIを前面に出すこと自体が話題になる、という判断もある。
その中で、2024年から2025年にかけて、いくつかの象徴的な事例が注目を集めた。1つは、コカ・コーラによる生成AIを使ったホリデー広告だ。長年続く「Holidays Are Coming」という定番の世界観を、AIを活用して再構築する試みが行われたが、公開後、SNSやクリエイターコミュニティを中心に「人間味がない」「魂が感じられない」といった批判が広がった。コカ・コーラ側は、AIを人間の創造性を補完する存在として位置づけ、表現の可能性を広げる試みだと説明したものの、賛否が割れる状況が続いている。
続いて話題になったのが、2025年末にマクドナルド・オランダが公開した生成AIによるクリスマス広告だ。ホリデーシーズンの慌ただしさやストレスを描いたこの広告は、映像表現の多くをAIで生成したもので、公開直後から「不気味」「冷たい」「この時期に期待される温かさと合わない」といった反応が相次いだ。YouTubeのコメント欄は停止され、最終的に広告そのものが非公開となった。マクドナルド側は、意図と受け止め方の間に大きなギャップがあったことを認め、今回の件をAI活用における学びだと位置づけている。
これらの事例は、単に「広告の出来が悪かった」という話にとどまらない。日経新聞をはじめとする複数のメディアは、著名ブランドであるコカ・コーラやマクドナルドがAIを前面に出した広告で消費者から批判を受けた点に注目し、生成AIの活用とブランド価値の関係、さらには消費者側のAI受容の限界について論じている。特に、クリスマスやホリデーといった感情的価値が強く求められる文脈において、AI特有の表現や制作プロセスが、必ずしも歓迎されていない現実が浮き彫りになった。
一方で、この動きは「AIを使うか、使わないか」という単純な二項対立ではなくなっている。AIを積極的に表に出す企業が批判を受ける一方で、競合ブランドがあえて「人間」「本物」「手触り感」を前面に出すことで評価を高める場面も見られるようになった。生成AIを巡る議論は、技術論を超えて、ブランドがどの立場に立ち、何を信じ、何をユーザーに委ねるのかという、より根源的な問いへと移行しつつある。
では、なぜこれらのAI広告は、ここまで強い反発を招いたのだろうか?
早嶋の考えも交える。1つは、生成AIそのものの技術的な完成度の問題がある。映像の細部や人物の動き、表情の連続性など、視聴者が無意識に「現実」と照合してしまう領域で、AI特有の違和感が残ったことは否定できない。ただし、それ以上に大きかったのは、広告が置かれた文脈とのズレだ。クリスマスやホリデーシーズンは、多くの人にとって「効率」や「新しさ」よりも、「温かさ」「安心感」「毎年繰り返されるお決まりの情緒」が求められる時間帯だ。そこに、制作プロセスとしてのAIが前面に出たことで、意図せず「省力化」「合理化」「人の手を減らした表現」という印象を与えてしまったのだ。
コカ・コーラもマクドナルドも、これまで長年にわたって、ホリデー広告を通じて「変わらないもの」を積み重ねてきたブランドである。トラックが走り、家族が集まり、いつもの味がそこにある。その反復がブランドの信頼を形づくってきた。その文脈において、AIという新しい技術が「裏方」ではなく「主役」として現れた瞬間、消費者の中で無意識の期待との齟齬が生じた。結果として批判は、映像の出来不出来を超えて、「そのブランドが、何を大切にしてきたのか」という問いにまで広がっていった。
興味深いのは、この動きに対して、競合ブランドがまったく異なる立ち位置から反応している点だ。
まず、マクドナルドの直接の競合であるバーガーキングだ。バーガーキングは長年、「王道」よりも「反骨」を選び続けてきたブランドだ。マクドナルドが安心感や規模、日常性を前面に出してきたのに対し、バーガーキングは、不格好なワッパー、直火焼き、挑発的なコピー、そして競合を名指しでからかう広告を繰り返してきた。そこに一貫してあるのは、「完璧である必要はないが、嘘はつかない」「人が作っていることを隠さない」という態度だ。
今回のAI広告を巡る騒動において、バーガーキングは大々的な反論広告を打ったわけではない。しかし、実際のアクター、実物のバーガー、現場感のある映像を使い続けることで、「こちらは本物だ」という立ち位置を自然に浮かび上がらせた。AIを否定するメッセージを声高に掲げる必要はなかった。競合がAIを前に出して批判を浴びた結果、バーガーキングの従来のやり方そのものが、相対的に人間的に見える構図が生まれたからだ。
同じ構造は、コカ・コーラとペプシの関係にも見られる。コカ・コーラが「王道」「伝統」「世界共通の物語」を守り続けてきたのに対し、ペプシは一貫して「カウンターカルチャー」「若さ」「反主流」を武器にしてきた。ペプシチャレンジに象徴されるように、ペプシは常にコカ・コーラという巨大な存在を前提に、自らの意味を定義してきたブランドだ。
今回、コカ・コーラのAI広告が賛否を呼ぶ中で、ペプシが公式にAIを巡る対抗広告を大々的に展開したわけではない。それでも、SNSや広告業界の文脈では、「人が作ったもの」「リアルな現場感」「人間のエネルギー」といった価値が、相対的にペプシの文脈と重ねて語られる場面が増えている。これは、ペプシがその都度戦術を変えたというよりも、長年積み上げてきたブランドの立ち位置が、環境変化によって再評価されている状態だと言える。
ここで重要なのは、バーガーキングやペプシが「AIを使わない」という選択を声高に主張したわけではない点だ。彼らは単に、これまで通りのブランド戦略を続けただけである。にもかかわらず、競合がAI活用で揺れたことで、両者の立ち位置はより鮮明になった。王道と反骨、安心と挑発、変わらない物語と変わり続ける姿勢。その対立軸が、結果として消費者の認識の中で再び強く浮かび上がった。
この一連の動きは、AI活用の是非を超えて、ブランドがどの対立軸に立ち、どの価値を繰り返し提示してきたかが、環境変化の中でどのように作用するのかを示している。生成AIは単なる道具だが、その使い方は、既存のブランド構造や競争関係を否応なく照らし出してしまう。今回の炎上とその周辺で起きた反応は、企業がAIを導入する際、単に技術の問題としてではなく、競争と意味の設計として考える必要があることを示している。
ここまで見てきた一連の騒動は、生成AIの是非を巡る議論であると同時に、もう一つ別の問いを見出した。それは、「なぜ、これほどまでに話題が広がったのか」という点だ。
マクドナルドのAI広告が批判され、コカ・コーラの取り組みが賛否を呼んだのは、単に有名企業が失敗したからではない。そこには、必ず比較対象となる明確なライバルの存在があるのだ。コカ・コーラの背後には常にペプシがいる。マクドナルドの動きは、必ずバーガーキングと並べて語られる。重要なのは、これらのブランドが単独で存在しているのではなく、「対立する二項」として、長年にわたって消費者の認識の中に定着してきたという事実だ。王道と反骨、伝統と若さ、安心と挑発。その構図があるからこそ、一方の動きが、もう一方の意味を浮かび上がらせるのだ。
ここで立てたい仮説がある。シンプルだけど興味深いものだ。それは、明確なライバルが存在する市場のほうが、実は市場全体として活性化しているのではないか?だ。
今回のAI広告騒動も、その構図の中で理解すると、別の輪郭が見えてくる。この仮説を検証するために、視野をハンバーガーや清涼飲料水の業界から広げてみたい。同じような構造は、実は多くの業界で繰り返し確認できる。
たとえば、ITの世界では、かつてWindowsとInternet Explorerが市場をほぼ独占した時期があった。競合であるNetscapeが姿を消し、明確なライバルが不在になると、ブラウザの進化は一気に鈍化した。表示速度も、セキュリティも、ユーザー体験も、長い間ほとんど変わらなかった。しかし、Firefoxが登場し、続いてChromeが現れた瞬間、市場の空気は一変。高速化、標準化、UIの刷新が一気に進み、「ブラウザとは何か」という問いそのものが更新された。競争が戻ったことで、技術だけでなく、物語が再び動き始めるのだ。
半導体の世界でも同じことが起きている。2010年代前半、IntelがCPU市場をほぼ支配していた時代、性能向上は年々小さな改良にとどまり、ユーザーにとって世代交代の意味は薄れていった。しかし、AMDがRyzenを引っ提げて本格的に復活すると、コア数、性能、価格のすべてが同時に動き出す。製品のスペックだけでなく、「次はどうなるのか」という期待感が市場に戻った。競争は、単に価格を下げるのではなく、未来を語る力を取り戻させた。
航空機産業では、競合が弱まった結果、別の歪みが生じた。ボーイングが事実上の選択肢となった局面では、安全や設計思想よりも、コストや財務的合理性が前に出やすくなった。結果として起きた一連の問題は、競争が技術だけでなく、倫理や緊張感を保つ役割も担っていることを示している。
日本の携帯電話市場も分かりやすい例だ。iモード全盛期、ドコモが圧倒的な存在感を持っていた時代、料金体系は複雑化し、ユーザー体験は内向きに進化した。しかし、iPhoneとソフトバンクの登場によって、競争軸が一気に変わる。価格、UI、サービスの分かりやすさが前面に出て、通信は「分かりにくいもの」から「選べるもの」へと変わっていった。
これらの事例に共通しているのは、競争が単なるシェア争いではなく、市場に緊張感をもたらし、物語を生み、価値創造のスピードを引き上げている点だ。ライバルが存在することで、企業は自らの立ち位置を語らざるを得なくなる。「なぜ自分たちは存在するのか」「何が違うのか」。その問いに答え続ける過程で、技術は磨かれ、体験は更新され、市場全体が前に進む。
逆に、ライバルを駆逐し、対立軸が消えた市場では、緊張感は急速に薄れる。説明責任は弱まり、物語は途切れ、消費者の関心は静かに冷えていく。競争がなくなると、企業は強くなるのではなく、市場そのものが痩せていく。
今回のAI広告を巡る騒動も、こうした文脈の中で捉えると理解しやすい。コカ・コーラとペプシ、マクドナルドとバーガーキングという明確な対立軸があるからこそ、一方のAI活用は単なる技術導入では終わらず、もう一方のブランドの意味を浮かび上がらせ、市場全体の会話量を押し上げた。批判も称賛も含めて、結果的に「飲み物」や「ハンバーガー」を再び語る理由が生まれている。
ここから先に問うべきなのは、「競争をどう避けるか」ではない。むしろ、「競争をどう設計するか」である。AIの活用は、その設計を壊すこともあれば、逆に浮き彫りにすることもある。今回の事例は、企業がAIを導入する際、単なる効率化や話題作りとしてではなく、競争、対立軸、そして集合知の形成という視点から向き合う必要があることを示している。
ここまで見てきた事例を踏まえると、一つの結論に行き着く。
それは、競争は自然に任せるものではなく、意図的にデザインすべきものだという考え方だ。今回のAI広告を巡る騒動も、単なる技術導入の成否では説明しきれない。コカ・コーラやマクドナルドがAI活用で批判を受けた一方で、ペプシやバーガーキングは相対的に評価を高めた。しかし重要なのは、どちらが正しかったかではない。明確なライバル関係が存在していたからこそ、この出来事が市場全体の関心を集め、議論を生み、消費者の意識を再びそのカテゴリーへと引き戻したという点だ。
これまで議論してきた他業界の事例も同様である。ブラウザ、CPU、航空機、通信。いずれも、競争が消えた瞬間に進化が鈍り、緊張感が失われ、市場が静かに停滞していった。一方で、ライバルが再登場した途端、技術だけでなく物語が動き出し、価値創造のスピードが一気に加速した。
ここから確認できる理屈はシンプルだ。競争は、価格やシェアを奪い合うための摩擦ではなく、市場にエネルギーを供給する仕組みなのだ。競争が存在すると、企業は自分たちの立場を説明せざるを得なくなる。「なぜ自分たちなのか」「何が違うのか」。この問いに答え続けることが、ブランドの物語を生み、価値を言語化し、顧客との関係を更新する。逆に、競争が消えると、その問い自体が不要になり、説明も物語も失われていく。市場が痩せるのは、その結果に過ぎない。だからこそ、企業にとって重要なのは、競争を避けることでも、勝ち切ることでもない。戦いが続く構図を、どう意図的に作るかなのだ。
では、この考え方を、企業はどのように自社のマーケティングやAI活用に取り入れていけばよいのかをまとめてみた。
第1に、競争相手を「消す対象」ではなく、「意味を生む存在」として捉え直すことだ。ライバルがいるからこそ、自社の立ち位置が浮かび上がる。マクドナルドが王道であるのは、バーガーキングが反骨であり続けるからであり、コカ・コーラが伝統であるのは、ペプシが若さや反主流を掲げてきたからだ。マーケティングとは、競合比較を避けることではなく、比較される前提で自分たちの物語を磨く行為だと言える。
第2に、AIの活用を「効率化の道具」ではなく、「競争軸を際立たせる補助線」として位置づけることが重要になる。AIを使って同じような表現、同じような最適解に収束すれば、競争はむしろ弱まる。しかし、AIを通じて自社らしさを強調し、ライバルとの差異を浮き彫りにできれば、競争はより立体的になる。AIは競争を消すための道具ではなく、競争を可視化するための道具として使われるべきだ。
第3に、あえて対立軸を明確にする勇気を持つことだ。すべての人に好かれようとすると、物語は薄まる。王道か、反骨か。安心か、挑発か。人間か、テクノロジーか。どこに立つのかを明確にし、その立場を繰り返し提示することで、ブランドは集合知として定着していく。競争をデザインするとは、敵を作ることではない。選ばれる理由を、はっきりさせることに他ならない。
今回のAI広告騒動は、生成AIの限界を示したというよりも、企業が競争と意味の設計をどこまで意識しているかを露わにした出来事だった。技術は進化する。しかし、競争の構図をどう描くかは、人間にしかできない。AIの時代だからこそ、企業には「競争をどう設計するか」という問いが、これまで以上に突きつけられている。
(早嶋聡史のYoutubeはこちら)
ブログの内容を再構成してYoutubeにアップしています。
(ポッドキャスト配信)
アップルのポッドキャストはこちら。
アマゾンのポッドキャストはこちら。
スポティファイのポッドキャストはこちら。
(過去の記事)
過去の「新規事業の旅」はこちらをクリックして参照ください。
(著書の購入)
「コンサルの思考技術」
「実践『ジョブ理論』」
「M&A実務のプロセスとポイント」