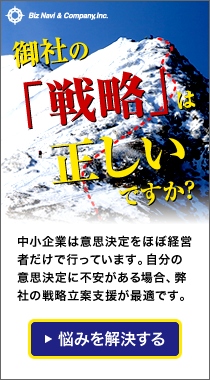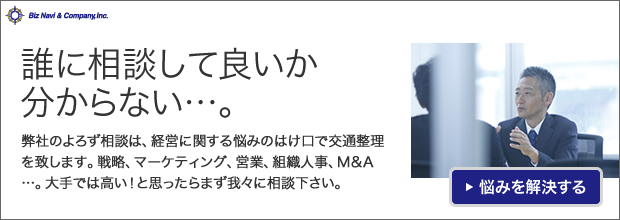早嶋です。
普段は日本を中心にした地図が当たり前ですが、正距方位図法で米国ニューヨークを中心に世界を見ると景色が変わります。米国はユーラシア大陸から離れた位置にあるのです。地理的な条件を考えたときに、少々強引ではありますが米国は英国や日本と同様に海に囲まれた島とみることができます。
第5代目米国大統領のジョームズ・モンローは1823年に欧州諸国に対して米国と欧州間に対する相互不干渉を提唱(モンロー主義)しました。欧州から米国は遠いこともあり、攻め込むことを辞め、米国は一気に西部開拓を進めます。この考えは今も米国外交の基本方針になっていると思います。
当時の米国は西海岸から少し内陸に入った小さなエリアのみで、周囲は先住民が住んでいました。モンロー主義の影響で開拓民は他国から干渉を受けることなく西部開拓に注力します。ただし当時の開拓民は政府から保護を受けることもなく、先住民や過酷な自然環境と戦いながらも自分たちの手と足によって西部開拓を進めたのです。
読者の皆さんは幼少期に「大草原の小さな家」を見たことがあるでしょうか?当時の開拓民をストーリーに展開されるお話です。開拓民の暮らしぶりや生活からは、独立自尊、創意工夫、忍耐不屈という言葉がぴったりなくらい厳しい環境のものでした。皆が銃を持ち、丸太小屋を作り、先住民と戦いながら土地を開拓していくのです。毎日がつらい日々でしたが皆耐え忍んでいました。
しかし、どうにもならない場合は、宗教を拠り所とします。非常に厳しい環境のもと、教会や牧師はいません。開拓民の多くが聖書と向き合っていました。信仰は自ずと原理主義的な思想を強くし、聖書に書いていない世界に対しては全否定する態度を取るようになります。
当時の開拓民の人々の末裔は反同性愛、反中絶、反進化論、反共主義、反イスラム主義、反フェミニズム、ポルノ反対、性教育反対、家庭重視、小さな政府、共和党支持などと上記のような歴史的な背景があります。また、自分自身を自分の責任のもと守るために銃社会に対して寛容であることも理解できるでしょう。
この思想は、苦しみは神からの試練であり、打ち勝つことも信仰の延長として捉えられます。先住民に対しての攻撃は、自分たちを正義として結果的に先住民征服やメキシコ侵略の動機につながりました。当時のメキシコはスペインの植民地で、カトリックを主体でした。米国のプロテスタントがカトリックを受け入れないという考えもあり、メキシコ侵略は正義のための戦いとして浸透しています。
米国は常に悪との対立を行う正義なのです。日本やドイツなどのファシズを倒す世界大戦。共産主義を倒す冷戦。イスラム過激派を倒すイラク戦争。これらもある程度しっくり来ますよね。
1848年。米国はメキシコ戦争に勝利します。当時、今のテキサスやカリフォルニアはメキシコの一部でしたが米国の領土になりました。その結果、米国は大陸国家に成長し、東海岸から太平洋に抜ける立地を手にしたのです。
そして偶然が重なります。カリフォルニアで金が発見されたのです。結果的にカリフォルニアが全米中、そして世界中から注目を集めるようになりました。当時、西海岸から東海岸に向かう場合、陸路ではロッキー山脈を超える必要がありました。ここは相当な難所であったため、東海岸へのルートは実に遠い船旅を強いられました。西海岸からアフリカに向かいインド洋に出る。そしてマラッカ海峡から日本をかすめて東海岸へ向かう壮大な船旅を強いられました。当時はその海のルートが主流だったのです。
1853年にペリーが浦賀に来日したのも同様の海路をめぐります。米国の西海岸から東海岸へのルートの途中に日本があったというのがきっかけなのです。当然、ずっと海路をめぐるのは非効率だったので、米国海軍兵学校の教官であったアルフレッド・セイヤー・マハンによってパナマ運河の発想が出たのもこの頃です。
1861年から1865年にかけて米国では南北戦争が勃発します。北部のアメリカ合衆国と合衆国から分離した南部のアメリカ連合軍の間で行われた内戦です。南部は気候が良くバージニアを堺に南部エリアでは綿の産地として栄えます。南部の地主は奴隷を活用して英国に対して輸出して利益を稼いでいました。一方の北部は工業が主力で英国は競合になっていました。そのため英国製品に対して関税をかける主張をします。これらが発端で南北戦争に発展したのです。
戦争の結果は北部の圧勝。その結果、南部の綿産業は衰退しますが、代わりに北部の産業が発達するきっかけになりました。もし、南部が勝利していたら今の米国はなかったでしょうね。きっと豪州のようにのんびりと農業大国となっていた可能性があるからです。しかしここはタラレバ。
北部の勝利によって米国全体の産業が発展します。北部には大陸横断鉄道もでき景気もよくなります。その結果世界中から移民が大量に押し寄せます。特に当時貧しい国や難民が米国に押し寄せました。イタリアやアイルランド(当時は英国の植民地で貧しかった)、旧ロシア系のユダヤ人なのです。皆出稼ぎ労働者でしたが、ユダヤ系には一部金持ちもいました。ロスチャイルドなどはその流れで、経済が発展する米国のニューヨークに銀行をつくり金貸しをはじめました。米国からも財閥が生まれ石油のロックフェラーや銀行のモルガン家などニューヨークには巨大な金融資本が誕生しました。
【米国と中国の関係の始まり】
ここから米国と中国の関係です。経済発展する米国は市場として中国に注目します。米国で生産された商品を中国に販売していたのです。当時、英国との戦争で中国は負け、市場を開くチャンスがありました。そこで先に出たマハンが提唱するパナマ運河を活用した航路の重要性が再び浮上します。
米国としては、工業地帯がある西海岸の北部エリアからパナマ運河経由で太平洋に抜けて中国を目指すのが好都合でした。当時の船は石炭を燃料とする蒸気船。長距離の航路は途中で燃料である石炭の補給が必要でした。キューバ、プエルトリコ、ハワイ、グアム、フィリピン。ここを抑えることで効率的に石炭の補給ができると考えたのです。当時ハワイは王国で、他の国々はスペインの植民地でした。そこで米国はスペイン戦争をおこして1898年にキューバ、グアム、フィリピンを獲得したのです。そしてハワイも併合して太平洋艦隊の建設を進めます。見事マハンが提唱した戦略を実現したのです。
そんな当時、日本は日清戦争の結果、下関条約により台湾を清朝から日本の領土としていました。フィリピンを米国下においた米国と日本は隣国同士の関係になっていたのです。当時の清朝は内紛でもガタガタでした。仏国が越南近辺を領土として、英国は上海を中心に占領。ロシアは内モンゴルや満州を占拠、ドイツは山東半島と米国はせっかく清朝に入るルートを整えたのにすでに他国に市場を取られていたのです。
そこで当時の米国国務長官であったジョン・ヘイは「清朝よ、ドアを開け!」的な発想で門戸解放宣言(Open door note)により市場の解放を各国に訴えました。しかし結果は誰も米国を相手にすることはなく、清朝は滅び中華民国が誕生したのです。ここまでの歴史を見る限り米国は中国を侵略していません。それどころか他の国に対して中国の分断に反対していたのです。これは今の対立からは想像できないですよね。
そもそも米国が当時中国に入りたかった理由は市場、つまり金儲け以外に別の理由がありました。それが米国の信仰を提供したいという発想でした。当時の米国人は中国人をすべてクリスチャンにしたいと思っていました。実際たくさんの宣教師を米国から中国に派遣していますし、清朝時代の中国には手を差し伸べることも行っていました。しかし中国は受け入れません。むしろ共産主義としてキリスト教徒を否定する動きになり、米国の苛立ちの根底にある感情を形成したのです。
【米国の2大政党】
米国の2大政党は共和党と民主党です。冒頭にも触れたように共和党は開拓農民の政党です。自分の生活は自分の責任で守る。政府はそもそもあまり干渉するな、福祉も要らないから、税金を安くしてという主張です。当然、アメリカ第一で自国の利益を優先的に考える主張です。西部開拓の流れを考えるとトランプの主張はかなり分かりやすいです。地理的にも開拓民が多く住み着いた米国の真ん中あたりに支持層が多いのも納得ですね。
対してライバルである民主党は後から入ってきた移民側の政党です。自分たちも移民なので今後の移民も継続的に受け入れたい。特にユダヤ系は金持ちなので特別な感情を持っています。彼らは国境を超えて投資をしたいためグローバルに関係を広げたいと思います。
共和党と民主党を整理すると少しは米国の政治が見えて来ますよね。大統領占拠は国民投票で決まります。その際、国民に直接アピールするために占拠には多額の費用をかけるのが通常です。そこで銀行の出番です。銀行は歴史的に見ても民主党よりではありますが、バランスをみながらファイナンスをするため共和党にもお金を出します。
銀行としては、投資を増やしてリターンを最大化したいのが常。そのため本音は海外にも投資を増やしたいのです。当然、中国も投資先として考えているでしょうから本音は中国ともうまくやりたいはずです。
トランプは真逆の考え。民主党は世界を統一する方向に動きたくて、共和党は海外には興味がない。民主党は国際連盟や国際連合をつくりたい。ウィルソンは民主党で国際連盟を提唱し、同様にルーズベルト大統領は国際連合の設立に尽力しています。そしてトランプはそのような取り組みにお金を払う意味が無いとしています。実に分かりやすいですよね。
【中国の近代史】
中国大陸を流れる大河は時には荒れ狂い、時には肥沃な大地をもたらします。壮大な大地を相手にはひとりの人間では太刀打ちできません。そこで大量の人民を組織して事業をなすことが求められました。2000年続く中国の官僚システムの基本的な思想です。秦の始皇帝以来、内陸の歴代王朝が強い権力を持ち官僚機構を使い人民を支配してきました。
一方で中国は海に面するエリアも広く、南に位置するエリアでは昔から貿易が盛んです。貿易を行う人々は自由に海を渡り、富を形成します。そのため大陸にいる人々よりも創造的で自由に行動する気質が自然と芽生えます。現在でも世界中で商売を行う架橋はこの海に面するエリアの子孫だと考えられます。宋代以降、海港都市が貿易で発展し、明代には武装商人である倭寇が出現しはじめます。
当時、倭寇の商売相手は日本。室町時代、日本は銀を売ってシルクを買っていました。当時の日本の商人は腰に刀を刺していた時代。非常に強く、当時の倭寇からすると「かっこいい!」という発想だったようです。日本人の衣装や髪型、そして刀を刺す倭寇も出ていたといいます。その憧れはたしかに倭寇の資料をみるとなんとなく分かります。
中国は内陸の力と沿岸の力が存在していました。経済は沿岸が強いため、内陸は頻繁にそこから重税をかけて中央にお金を集めていたのです。
近代になり、英国は自由貿易を清に求め、アヘン戦争により上海を開港させました。市場を中国に求める動きはどの国も同じで、結果的に日清戦争前後で各国が沿岸部を占領し、中国は分裂させられはじめます。しかし、その一方で上海を中心に外資が入り込み爆発的な経済成長を遂げることができました。その際も金銭的な爆発的なバックアップは浙江財閥が行っていました。
1911年、孫文らが中心となって清朝を倒す辛亥革命が起こります。この際も浙江財閥は資金的なバックアップを孫文に行います。中国において沿岸の力(シーパワー)が内陸の力(ランドパワー)を倒した瞬間でした。それ以降中国では沿岸の力が政権を取り1912年に孫文を臨時大統領とする中華民国が南京に誕生します。
ところが内陸の力は黙っていません。ロシア革命の影響を強く受けた共産党がはじめこそは中華民国と手を組みましたが、軍隊は北京に残したままでした。中国共産党は北京財閥打倒を掲げ国民党に協力(国共合作)するも、1925年の孫文の死去とともに蒋介石がクーデターを起こし南京に国民政府を成立させます。この際、浙江財閥が資金を共有すると同時に英米も支持をしていました。シーパワーとランドパワー、所詮は水と油、うまくいかなかったのです。
当時は世界大恐慌の真っ只中、そして日本は満州事変により中華民国との武力紛争を開始します。これにより日本は英米と戦うことになります。日本が加わることによって、当時の構図は、日本。米英+蒋介石率いる国民党。そしてソ連+共産党率いる毛沢東という3者間の対立に発展しました。
ここもタラレバですが、日本が中華民国との争いを始めなければ中国に米英がバックアップするなどなく、共産党の勢力も今のように大きくなかったかも知れないのです。実に馬鹿げていた行動だと思います。
国民党は沿岸の力、つまりシーパワーの発想で自由に貿易をして経済を成長させる考えでしたので金持ちは富み貧富の差が拡大します。一方の共産党は大陸の力、つまりランドパワーが主体です。官僚主義を貫き土地分配を約束します。その結果、貧困層の圧倒的な支持を得たのです。
日本軍の撤退後、共産党は内戦でも勝利します。蒋介石率いる国民党は台湾に戻り、毛沢東率いるランドパワーの国、中華人民共和国が誕生します。隣国のソ連は共産党で一時は同盟を結び朝鮮戦争で中国義勇軍が米国と戦いました。しかし歴史の世界では隣国は常に敵。更に米国がソ連と中国のどちらかを取るかで結果的にソ連を敵にしたことで激烈な中ソ論争がはじまります。
米国は中国を攻めることなく、むしろ分裂を防ぐ働きをしたり、ソ連との争いの中で助ける動きをしたり。これも今ではなかなか考えられない動きですよね。1972年に米国のニクソン大統領は中華人民共和国を訪問して毛沢東や周恩来と会談しました。いわゆるニクソン・ショックにより、これまで極秘にすすめていた米中交渉が公になります。
毛沢東の政治はバリバリの社会主義でした。すべてを国有化して、党の指示にて動く。5カ年計画によって努力してもしなくても報酬は一律。結果、仕事することが馬鹿らしくなり生産性は最低。肝いりの計画経済(大躍進)は失敗に終わり結果はボロボロ。党の腐敗も進み、いわゆる中国のイメージが出来上がっていきます。
そこに当時実権派であった劉少奇がソ連型の政策にNGを呈して、資本主義の道を歩むことを提案しました。ランドパワーの毛沢東とシーパワーの劉少奇の考えが中国を再び二分することになります。毛沢東としては、大躍進政策が失敗に終わり国家主席の地位を劉少奇党副主席に譲りましたが、毛沢東は自身の復権を常に画策していました。結局、文化大革命によって毛沢東は復権します。ここでもタラレバですが、劉少奇が党をリードしていれば今の中国の姿は確実に変わっていたことでしょう。
1976年、毛沢東が亡くなった後、実権派の鄧小平が後継します。彼の考えはいいとこ取りです。経済を成長させて、党の独占支配も続けたい。その象徴が社会主義市場経済です。改革開放政策によって市場経済を認め、外資導入により経済成長を後押ししました。一方で土地は国有化して、企業に付与する形式を取り許認可制度に。これによって共産党が力を維持することができます。再び賄賂が当たり前の世界がはびこり一党独裁で党の腐敗もすすみます。一党独裁ですのでマスコミが騒ぐこともばく泥沼のような経済成長を遂げます。
このままの政策は当然に貧富の差を生み、隠蔽体質の党体制にたいして国民の不満もたまります。当然ながら「民主化の動きがいいんじゃない?」と胡錦涛は政治の民主化を考え民主化デモを容認します。雰囲気は民主化の方向性でしたが当時の共産党とのバリバリのバトルの中、胡錦涛は心臓発作をおこして帰らぬ人となります。この一連の象徴が天安門事件です。民主化を主張する学生と共産党の戦いです。しかし周知の通り戦車を導入した鄧小平が制圧して、結果的にランドパワーがシーパワーを封じ込めてしまったのです。一連の騒動に対して外資企業は利益を上げることができたので黙認していたのです。香港はそんなさなか中国へ、50年間の自由の縛りをつけて変換されました。
鄧小平時代、中国海軍には死島線という概念が提唱されました。これは段階的なもので、中国沿岸から徐々に中国の領海を増やして、米国の力を排除しようとする考えです。沖縄、台湾、フィリピン、南シナ海が第一列島線で、第二列島線のシナリオは伊豆諸島、小笠原諸島、硫黄島、米領のサイパン島、グアム、パラオととんでもない計画です。鄧小平は米国と歩み寄る姿勢を見せながらジワジワと準備を進めていたのでしょう。彼の言葉「能ある鷹は爪を隠す」この真意は気になるところです。
中国からすると1991年のソ連崩壊で北の脅威が消滅しました。ソ連の存在と米国の存在と一気に戦うことは無理と思っていたのでしょう。しかし緊張感が取れたいま、ビジョンは米国に向かっているのです。
胡錦涛時代の2003年から2013年は尖閣海域への公船派遣を繰り返し、東シナ海のガス田を開発しています。これは着実に上述した列島線の取り組みで第一列島線の計画を実行していると考えられます。そして習近平時代になった2013年からは南シナ海の環礁埋め立てと軍事要塞化などいよいよ第二列島線の動きに入っているともみてとれます。
2020年現在。一気に米国と中国、そこに関連する隣国の動きをみてみると国ごとの考えが存在するのではなく、国の中に異なる考えが対立して、その時々の偶然が重なり今の国の考えや動きが出てきていると思います。したがって、米国はこうだ。とか中国はこうだとか論じるのは難しくて、一つの国の中にある対立や力関係を考えることも大切です。
【まとめ】
米中貿易戦争の真っ只中。加えてコロナの時代。何が因果かはわかりませんが、少なからずとも世界の経済に大きな影響を与える2つの国。
中国の驚異はずっとソ連でした。沿岸部は開放的な経済を推し進めるリーパワーの動き。国民党の蒋介石がリードしました。一方で内陸を収めるためには官僚主義や共産主義が良しとされ結果ランドパワーが正当化されます。常に経済と独裁という2つの相反する概念が共存していました。そこに天安門事件が起こり独裁を維持しながらの経済成長を遂げる取り組みが始まったのです。
一方の米国は当初は西部開拓の開拓民からはじまります。誰も信じずにフロンティアスピリッツが当たり前。そして厳しい環境から原理主義的な思想が当たり前になる。そこに対して移民をバックグラウンドとする民主党が入って来ます。南の農業の戦いと北の産業の戦いで、産業が勝利すると、その商品を一気に世界に販売することを目指して太平洋の航路を開拓する。
1つの巨大な大地に、常に対立する考えが入れ替わっている米国と中国。なかなか相容れないことは分かります。ただ、中国も米国も時の政権や政治の思想がシーパワー同士だったらうまくいくのかも知れません。民主党で鄧小平の時はあるいみOKでした。米国もクリントン政権の時は米中関係は比較的良好でした。
しかし習近平とクリントンではガチガチの対立思想です。次の占拠でトランプが負け、バイデン率いる民主党になれば米中関係は今よりは良くなるでしょう。しかし敵の敵は味方と歴史的にみて、米中が争っている時のほうが漁夫の利を得られる日本。習近平がブイブイ言わせて米国と争っている方が日本には実利が落ちてくる。そんな邪な考え方もできるかも知れませんね。
参照:
「歴史で学べ!地政学」茂木誠著
Wikiペディア