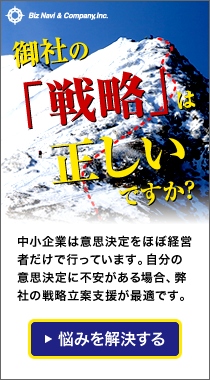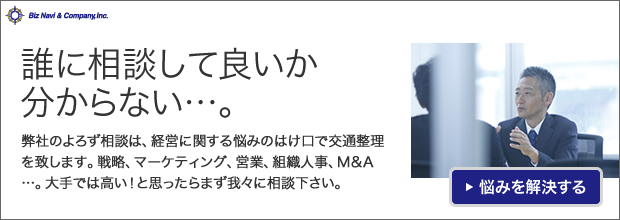早嶋です。約3900文字。
岩手県盛岡市の 萪内遺跡 から出土した土偶に、「しだないくん」がいる。縄文時代の土偶に、現代のキャラクターの名前が与えられている。なんとも軽い名だが、しだないくんは、他の土偶と異なり大きい、等身大に近い。しだないくんは、頭部に加えて、胴や脚と思われる破片が、少し離れた場所から見つかっている。偶然壊れたのではない。意図的に分けられ、埋められた可能性が高い。
ただ、1つ補足しておく。縄文時代の土偶は、そもそも完全な姿で出土するほうが珍しい。多くの場合、頭だけ、胴だけ、あるいは手足が欠けた状態で見つかる。壊れた土偶が遺跡から出ること自体は、特別なことではない。従い問題は、「壊れているかどうか」ではなく、どのように壊され、どのように配置されていたかになる。
しだないくんの場合、頭部だけでなく、胴や脚とみられる破片が、少し離れた場所から見つかっている。これは、単なる破損や廃棄では説明しにくいのだ。縄文人は、ここまで手間をかけて、人の大きさに近い土偶をつくり、それを分解し、土に返している。
祭器をわざわざ生み出せる社会とはどのようなものか。しだないくんのいた時代は約4000年前だ。縄文後期と呼ばれる時代。この時代に、食料でも道具でも武器でもない、純粋に祭祀のためだけの造形物がつくられているという事実は、思っている以上に重い。
土偶は、生存の直接的な手段ではない。それでもつくられたということは、安定した食料供給があり、役割分担があり、専門的な技術を持つ人間がいたということを意味する。つまり、萪内遺跡周辺の社会は、決して未熟ではない。むしろ、相当高度だったと思う。ただ、これほどの文化的成熟があっても、国家は生まれていない。文字も見当たらない。戦争や大量殺戮の痕跡もほとんど出てこないのだ。
ここで視点を変えて見よう。萪内遺跡が営まれていた約4000年前、世界の他の地域での出来事だ。西アジアでは、メソポタミア文明がすでに都市国家を形成していた。楔形文字が使われ、王が統治し、法が刻まれ、徴税と軍事が制度化されていた。文字は、倉庫の管理、労働の記録、命令の伝達に使われていた。これは明確な「管理社会」だった。
ナイル流域の古代エジプトでも同様だ。ヒエログリフと呼ばれる文字が発達し、官僚制度が整えられ、巨大建築を維持するための人と物の管理が行われていた。そこでは王権が神格化され、支配は当然の前提だった。
中国でも、二里頭文化から殷にかけて、青銅器とともに王権的な中心が生まれ、やがて甲骨文字という記録体系が成立していく。占いや命令、祖先祭祀が文字によって固定されていった。
同じ時代、世界の多くの場所では、文字と管理と支配が既に明確に存在していたのだ。そもそも、上記の文明は、文字と管理が必要になったのだろうか。その鍵は、気候と環境だ。
メソポタミアは肥沃だが、雨が少なく、灌漑に失敗すれば一気に飢饉に陥る。エジプトはナイルの氾濫に依存しており、その周期を外せば破綻する。中国の黄河流域も、洪水と旱魃を繰り返す不安定な環境だった。
これらの地域は、人が住めるが、放っておけば生きられない場所だった。水を管理し、土地を管理し、人を動員しなければ、集団は簡単に崩壊する。つまり、文字と管理は、文明の贅沢品ではなく、生存のための必需品だったのだ。
だが、同じ約4000年前に、まったく違う姿の文明も存在していた。それは、インダス文明の都市 モヘンジョダロ だ。モヘンジョダロは、整然とした都市計画があり、上下水道が張り巡らされ、排泄がきちんと管理されていた。だが、王宮らしき建物はなく、巨大な神殿もなく、城壁も弱い。武器の出土も少ないのだ。ここは管理は存在しているが、支配が見えない遺跡だ。当時のインダス流域は、現在よりも湿潤で、モンスーンが安定していた。農耕と牧畜が両立し、資源は比較的豊かだった。奪い合うほど逼迫していなかったのだ。この環境では、強い支配構造をつくらなくても、秩序が維持できたのだろう。
再び、日本列島に目を戻してみる。縄文時代、とくに中期から後期にかけて、日本は現在より温暖で湿潤だった。いわゆる縄文海進の時代だ。照葉樹林が広がり、木の実、魚、獣が豊富に存在していた。人は、自然を過度に管理しなくても生きていけた。この環境では、暴力的な支配や厳密な管理は、むしろコストが高いのだ。
縄文社会とモヘンジョダロには、驚くほど多くの共通点がある。管理はあるが、支配が前に出ていない。都市や集落は成立しているのに、王権や軍事が社会の中心になっていない。こうした類似を前にすると、「もともと人の性質が違ったのではないか」あるいは「遺伝的に穏やかな集団だったのではないか」という考えが、頭をよぎる。
だが、現在わかっている限り、縄文人とインダス文明の人々のあいだに、社会の型を決定づけるような決定的なDNAの違いは見つかっていない。むしろ違っていたのは、人そのものではなく、人が置かれていた環境条件だったと考えるほうが自然だ。同じ人類が、資源が比較的安定し、外圧が低く、奪い合いが合理的でない環境に置かれたとき、似たような社会の形を選ぶのだ。その結果として、縄文とモヘンジョダロは、よく似た姿を見せているのではないだろうか。
もちろん、インダス文明は、やがて衰退する。原因は戦争ではない。モンスーンの不安定化、河川の流路変化、乾燥化といった気候変動だ。一方、日本列島では、縄文の終盤から弥生にかけて、人の流入が始まる。戦争や飢饉、国家形成の圧力の中で、東へ追いやられた人々だ。
彼らは、稲作、鉄器、青銅器、土木技術、織物、暦といった高度な技術をもたらした。だが同時に、戦の文化、略奪の発想、境界を引く思想、そして文字と管理の感覚も一緒に持ち込んでしまったのだ。光と影は、常に一体だ。
ここで早嶋は、あらためて考えた。管理とは、そもそも何だったのかをだ。管理は、最初から支配を目的として生まれたものではない。それは、人口が増え、集団が大きくなり、水や食料、排泄といった問題をその場の話し合いや暗黙の了解だけでは処理しきれなくなったときの、応急処置だったはずだ。誰かが全体を見渡し、調整する。衝突が起きそうになれば仲裁する。余剰が出れば分け、不足すれば耐える。この段階では、管理は役割であって、力ではなかった。一時的で、状況依存で、人格に支えられたものだったのだ。
だが、人類はここで一つの「発見」をしてしまった。人を管理すれば、集団を意図的に動かせる、という発見だ。それは、火や道具の発見と同じくらい、人類史にとって大きな転換点だったのかもしれない。問題は、その発見そのものではない。問題は、その力にどう向き合ったかだ。
管理という仕組みは、本来、手放せるものだ。状況が変われば、役割も終わる。だが、その力に安心を感じる人間が現れたのだ。自分が上に立つことで、世界が分かりやすくなったように錯覚する人間だ。集団を動かせることに、優越や正当性を見出してしまう人間。それを失うことに、強い不安を覚える人間。そこには、能力の問題というより、心の弱さがある。その弱さは、やがて次の欲求を生む。この力を、一時的なものではなく、恒常的なものにしたい。自分がいない場所でも、自分の意志が通るようにしたい。
ここで、文字が必要になったのでないだろうか。文字は、対話のための道具ではない。むしろ、対話が成立しなくなったときに使われる。顔の見える関係が壊れ、空気や慣習だけでは人が動かなくなったとき、命令を固定し、正しさを保存し、疑問を封じるために使われる。そう考えると、文字は理性の結晶というより、不安を抱えた支配者が、自分を守るために磨き上げた道具だったのではないか、という疑念が浮かぶ。
再び、しだないくんに視点を戻そう。等身大に近い身体。役目を終えたあと、壊され、分けられ、土に返された痕跡。縄文の土偶は、壊されて出土することが多い。だが、ここで重要なのは「壊された」という事実そのものではない。壊すことが、終わりではなく、ひとつの行為として組み込まれていたという点だ。
しだないくんは、記録されるために作られた存在ではない。後世に残すための像でもない。その場に立ち、その時間を生き、その役割を果たし、そして消えていくことまで含めて、意味を持っていた。そこでは、文字は必要なかった。正しさを固定する必要もなかった。命令を書き残す必要も、力を永続させる理由もなかった。身体を通して共有され、儀礼として繰り返され、集団の記憶の中に溶け込んでいった。記録ではなく、記憶。命令ではなく、合意。支配ではなく、調整だった。
縄文社会やモヘンジョダロのような世界は、人類がまだ「管理を発見する前」の未熟な段階だったのではない。むしろ、管理や支配という強い仕組みを必要としない条件が、かろうじて成立していた社会だった。だが、気候が変わり、人が移動し、資源が不安定になったとき、管理は応急処置として現れ、やがて発見され、一部の人間の心の弱さと結びつき、文字とともに固定化されていった。
それは進歩だったのか。それとも、生き延びるために選ばざるを得なかった、ひとつの分岐だったのか。
しだないくんは、語らない。だが確かに、問いを残している。人類は、かつて、管理と文字に深く依存しなくても、秩序を保ち、意味を共有し、社会を営んでいた。その事実を、等身大の身体で、壊され、土に還るというかたちで、今に伝えている。管理と文字とデータに覆われた現代に生きる我々は、その問いの前に立っている。