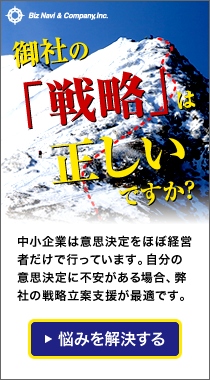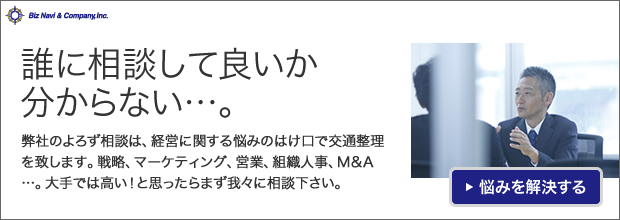早嶋です。約7600文字。
子どもの誕生と共に、レゴの基本セットを購入した覚えは無いだろうか。まだ言葉も話さないうちから、ブロックを積み、崩し、色を並べる。その後、レゴニンジャゴーに夢中になり、クリスマスには毎年新しいセットを欲しがった。アウトレットモールにはレゴストアが入り、子供にとってつまらないアウトレットモールが夢の場所に変わった。
レゴは、およそ90年の歴史があり、「失敗と再発明」を繰り返し成長している企業だ。世界最大級の玩具会社でありながら、同時に「人間はなぜ手で何かを作ると夢中になるのか」という欲求と解消を、産業として向き合い続けてきた稀有な存在だ。
(レゴの概要)
2024年、レゴグループの売上は約743億デンマーククローネ(日本円で約1.6兆円)。営業利益は約187億クローネ、純利益は約138億クローネ。世界中に3万人以上の従業員を抱え、130カ国以上で販売されている。
レゴは上場企業ではない。今も創業家の持ち株会社 Kirkbi A/Sにより支配されている。Kirkbi A/Sは レゴグループ株式の約75%を所有し、残りは非営利組織であるレゴ財団(The LEGO Foundation)が保有する。この所有構造は、短期の株価や投機ではなく、長期的ブランド価値と遊びの思想を守るためのもので、創業家による世代を超えた統制が今も続いていることを示す。
レゴの売上推移を見る、同社の歴史の節目が数字にも表れている。2003年から2004年に会社が経営危機に陥った直後は、売上規模は 約70億から90億デンマーククローネ程度 で推移していた。その後の復活と事業再編で成長が加速する。
2003年:売上 約70億から80億DKK程度(1400億から1500億)
2004年:売上 約60億から70億DKK程度(1200億から1300億
2005年:売上 再び回復し、約 1500億円
2010年前後:売上規模約160億から180億DKK(3600億円)程度と拡大
2015年:約350億から380億DKK(8000億)以上の規模へ成長
2020年代:約550億DKK以上(約1.2兆円)
2023年:売上 約650億から700億DKK(約1.5兆円)に到達したという推計がある。
この数字の流れを見ると、2003年から2004年の低迷期から2005年前後で復調し、2010年代に入って売上が加速度的に伸び始め、2010年代中盤から後半には大台に乗ったという構造が読み取れる。特に2015年以降は、IP戦略(ニンジャゴーや映画・テーマ別ライン)や直販・グローバル展開の強化によって成長が加速し、2020年代には玩具業界最大級の規模にまで到達している。
(木からプラスチックに)
レゴは1932年、デンマークの大工オーレ・キアク・クリスチャンセンによって創業された。最初は木製玩具の工房だった。木の積み木や木製の車は、当時の子どもたちにとって定番の遊び道具であり、レゴもまた、その延長線上にあった。
しかし戦後、プラスチックという新しい素材が登場する。軽く、壊れにくく、寸法を正確に量産できる。この「寸法を揃えられる」という性質に、オーレは決定的な可能性を見た。彼が目指したのは、単なる新素材の玩具ではなく、「互いに正確につながる部品」だった。
1958年に完成したスタッドとチューブによるブロック構造は、見た目以上に革命的だった。それはブロックを、ただ積むための塊から、「組み立てられる部品」へと変えたからだ。しかも、その接続は強すぎず弱すぎない。遊んでいる最中には崩れないが、子どもの手で簡単に外せる。この絶妙なバランスによって、レゴは壊すことを前提とした玩具になった。作って、壊して、また作る。失敗が遊びの中に組み込まれたのだ。
ここでレゴは、木の積み木とはまったく異なる領域を創造した。木の積み木は、その場で形を作る遊びだが、レゴは「構造を設計する遊び」になる。橋や車や街は、重ねるのではなく、組み上げるものになる。しかも、同じ形を何度でも再現できる。説明書が成立し、他人と同じものを作り、そこから改造するという文化が生まれた。
さらに重要なのは、この接続の規格が追加を自由にしたことだ。新しいセットを買っても、古いブロックは無駄にならない。すべてが同じ規格でつながり続ける。家庭の中にレゴの部品が蓄積されるほど、遊びの世界は広がる。レゴは「完成品を売る会社」ではなく、「創造を拡張する部品を売る会社」になったのだ。
プラスチック化は、単なる素材の変更ではない。レゴは、積み木の概念を変えた。子どもの想像力を、再現可能で、共有可能で、拡張可能な構造に作り上げたのだ。そのことが、のちにデジタルやIPの時代が来ても、レゴが中心に居続ける土台になっている。
(デジタル化の誤読)
1994年、ソニーのプレイステーションが登場した。それまでのファミコンとはまったく違う、立体的で、映画のような世界がテレビの中に現れた。コントローラーを少し動かすだけで、キャラクターが走り、ジャンプし、敵を倒す。子どもたちは、リビングの床に座り込み、画面に吸い込まれるように遊び始めた。
1996年にはポケモンが現れる。ポケットの中のゲーム機の中に、小さな生き物の世界があり、友達と交換し、戦わせ、コレクションしていく。学校の休み時間や帰り道の話題は、いつのまにかレゴではなく、ポケモンになっていった。
当然、レゴの経営陣も、その光景を見ていた。子どもたちの視線が、テーブルの上のブロックから、テレビやゲームボーイの画面へと移っていく。これまでレゴで遊んでいた時間が確実にゲームの世界に奪われていくのだ。
一方で、1995年にWindows95が出て、インターネットという言葉が家庭に入り始める。まだ動画もなく、回線も遅い。ただ、「世界とつながる」という新しい感覚が、少しずつ広がっていった。2000年に入れば、これが本格的な社会インフラになることは、薄々見えていた。
レゴの経営陣の中では、こんな不安が膨らんでいたはずだ。「子どもたちは、もうブロックでは遊ばなくなるのではないか」と。そこで彼らは、極端な選択をした。ブロックの会社であることを忘れたように、ゲーム会社になろう、IPの会社になろう、テクノロジーの会社になろうと行動したのだ。
レゴ・アイランドというゲームが作られ、レゴ・レーサーが出る。Bionicleという独自のSF世界が立ち上がり、Galidorというアクションフィギュアと連動したIPも作られる。Mindstormsでは、レゴはロボットとプログラミングの会社になろうとした。外から見ると、未来的で、挑戦的で、格好良かった。だが、レゴの箱を開けたときのあの感覚、床にブロックを広げ、何かを組み立てていく体験とは、少しずつ切り離されていった。
子どもは、手を使ってレゴを組み立てて遊ぶのではなく、レゴのゲームをデジタル上で遊ぶようになる。レゴで創造するのではなく、製造されたストーリーの中で、遊ぶようになり、ただ時間を消費するようになるのだ。そして気がつけば、レゴは「レゴでなくてもよい商品」を山ほど抱えた。ゲーム会社としては中途半端で、IP会社としては弱く、玩具会社としての強みも失いかけていたのだ。
その結果が、2003年の巨額赤字だ。倉庫には売れ残った在庫が積み上がり、開発費とライセンス費が経営を圧迫する。レゴは、ほとんど自分が何の会社なのか分からなくなっていた。倒れかけたのは、ブロックが時代遅れになったからではない。本質のブロックからドメインを切り離したからだった。
(CEO交代と手で考える会社に戻る戦略)
2004年、レゴは創業以来最大の危機に直面していた。莫大な赤字、膨らんだ在庫、分裂した事業。社内には「レゴはもう終わったのではないか」という空気すら漂っていた。その中で創業家が下した決断が、外部から一人の若い経営者をCEOに迎えることだった。ヨルゲン・ヴィグ・クヌーストープ。当時まだ30代半ばの、ほとんど無名の経営者だった。
だが彼が選ばれた理由は、年齢や肩書ではなかった。創業家が求めていたのは、「レゴの組織の外にいながら、内側の組織を見渡せる人間」だった。長年の成功によって、レゴの組織内には「自分たちは創造性の会社である」「子どもの夢を作っている」という強い自己物語が出来上がっていた。その物語が、90年代後半のデジタルの波にうまく適応できず、会社を迷走させていたことを、創業家は直感的に感じ取っていた。
社内の重鎮では、その物語を壊せない。かといって、レゴを何も知らない外部のプロ経営者では、この会社の魂を切り捨ててしまう。ヨルゲンは、その中間にいた人材だ。戦略コンサル出身で数字と構造を冷静に見られる一方で、社内の戦略部門としてレゴの文化や矛盾を組織内部からも同時に見てきた人物だった。レゴの神話に縛られず、しかしレゴの本質を理解している。その稀有な立ち位置こそが、彼をCEOに押し上げた。
創業家は、事業を立て直す前に、「レゴは何の会社なのか」という物語そのものを立て直す必要があると分かっていた。そのためのCEOが、ヨルゲン・ヴィグ・クヌーストープだった。彼に期待された役割は、コストを削ることではなく、レゴという会社の原点をもう一度見つけ直すことだった。
多くの企業なら、まず銀行と交渉し、コストカットを進め、工場を閉める。だが彼が最初にやったのは、まったく別のことだった。彼は世界中の家庭や保育園を訪れ、子どもたちが実際にレゴで遊んでいる様子を観察させた。経営会議室ではなく、床の上に広げられたブロックの山の前に立ち、子どもたちが何を作り、どう壊し、どう考え直すのかを見続けた。
そこで見えたのは、経営陣が想像していた姿とは違う光景だった。子どもたちは、レゴの設定やストーリーをなぞって遊んでいるわけではない。説明書通りに一度は作るが、すぐに崩し、パーツを混ぜ、別の何かを作り始める。車は船になり、城はロボットになり、正解の形は存在しない。彼らが夢中になっているのは、完成した作品ではなく、「組み替える過程」そのものだった。
クヌーストープは、そこでようやくレゴの本質を掴む。レゴの価値は、世界観やキャラクターではない。子どもが「こうしたらどうなるだろう」と試し、失敗し、やり直す、その思考の運動そのものにあった。彼は社内でこう語ったとされている。「我々はエンターテインメント会社ではない。私たちは手で考える会社だ」と。
レゴの進むべき方向はこのような背景で明確になる。ゲーム会社でもなく、IP会社でもなく、テック企業でもない。レゴはあくまで、子どもの手と頭をつなぐ道具の会社なのだ。
そこからレゴは、ばらばらになっていた事業を整理し、再びプラスチックのブロックを中心に据え直す。売れないIPは切り離し、ブロックと結びつかないデジタル事業は縮小、「組み立てる体験」を核に事業を整理した。レゴが復活したのは、奇跡でも運でもない。自分たちの存在意義を、コアユーザーである子ども達に教えてもらったのだ。
(ニンジャゴーの開発)
ヨルゲンが「レゴは手で考える会社だ」と再定義したあと、レゴの中にはひとつの難題が残った。ブロックの会社に戻ることはできた。しかし、2010年代の子どもたちは、90年代とは明らかに異なる。テレビ、ゲーム、YouTube、キャラクターに囲まれて育っているのだ。ただのブロックだけでは、彼らの注意をつかみ続けられないことも分かっていた。
そこでレゴは、過去の失敗をもう一度、慎重に分析した。BionicleやGalidorで失敗した理由は何だったのかを。そして明確な答えにたどり着いた。それらのIPは、ブロックから独立していたのだ。それらのIPはアクションフィギュアになり、アニメになり、ゲームになり、レゴである必要がなくなっていた。そこでヨルゲン体制のレゴは、逆の設計をした。物語をブロックに連携するIPを作ったのだ。こうして生まれたのがニンジャゴーだった。
ニンジャゴーの世界観は、最初から組み立てることを前提に設計されている。忍者、ドラゴン、メカ、都市、敵と味方。これらはすべて、ブロックで作ると楽しい構造になっている。つまり、アニメは世界観を説明するための装置であって、遊びの中心ではない。遊びの中心は、あくまで子どもの手の中にある。
さらにレゴは、ニンジャゴーを「無料で配信する」戦略をとった。テレビやYouTubeで誰でも見られるようにし、入口の摩擦を限りなく下げた。その代わり、世界の続きはブロックの箱の中にあるように設計した。アニメの一話が終わると、次の展開を自分で作りたくなる。ここで初めて、商品が欲しくなる。
これは、Bionicle時代の「キャラを売るIP」とは正反対の構造だ。ニンジャゴーは、物語を消費させるためのIPではなく、創造を引き出すためのIPだった。だからレゴは、他の独自IPを整理した。世界観だけが先行し、ブロックとの結びつきが弱いものは削除する。IPの数を増やすのではなく、「ブロックで遊びたくなるIP」だけに集中した。
結果として、ニンジャゴーは単なるヒット作品ではなく、レゴの戦略そのものを体現する存在になったのだ。子どもはアニメを見る。そしてブロックで再現する。壊して、組み替えて、自分の物語をまた作る。再びアニメに戻る。この循環こそが、「手で考える会社」としてのレゴが、デジタル時代に見つけた答えだった。
ニンジャゴーがブレークした当時、私の子どもたちも、まさにその世界にいた。YouTubeでアニメを見て、レゴのカタログで新しいメカやドラゴンを眺め、H&MのニンジャゴーTシャツを着て、床にブロックを広げて遊ぶ。画面と現実、物語とレゴ、キャラクターと自分の手が、ひとつの循環の中でつながっている。だが、その中心は、常にブロックだった。アニメは入口で、カタログやTシャツは世界観を広げるための仕組みに過ぎない。物語が実際に進み、勝ち負けが決まり、世界が変わる場所は、子どもたちの目の前に広げられたリアルのレゴだった。
これは、90年代にレゴが迷い込んだ「スクリーンの中で完結するデジタル」とは、まったく逆の設計だ。ニンジャゴーは、IPを消費させるための仕掛けではなく、創造を引き出すための文脈として作られていた。デジタルは子どもを引き寄せるが、遊びの主役にはならない。主役はあくまで、組み立て、壊し、考え直す手の動きだ。だからニンジャゴーは、レゴにとって単なるヒット作ではない。レゴの再定義である「手で考える会社」が、実際に現実の世界で機能していたのだ。
(新しいブロック)
ニンジャゴーが当たったからといって、レゴはそれに依存しなかった。むしろレゴは、「手で考える」という思想を、あらゆる子どもとあらゆる年齢に拡張していった。
レゴ・シティの中では、警察官や消防士が街を守り、空港や港が動いている。そこには、現実の社会を自分で再構築できる遊びがある。女の子向けにはお姫様やファンタジーの世界が用意され、そこでも物語は完成品ではなく、組み替えられる舞台として与えられる。スター・ウォーズやハリー・ポッターのような外部IPも、単なるキャラクター商品ではなく、「ブロックで再現できる世界」としてレゴに組み込まれていった。
年齢が上がれば、レゴはより難しくなる。テクニックシリーズでは歯車やサスペンションを使って車やクレーンを作り、子どもは自然に構造や力学を学ぶ。レゴで育った子どもが、レゴを卒業しなくてもいいように、レゴは成長の階段を用意しているのだ。
さらにレゴは、ブロックを教室の中にも持ち込んだ。プログラミングで実際のレゴを動かすキットは、STEM教育の入口となり、レゴ・シリアス・プレイは、企業研修の場で「手を動かしながら考える」ための公式メソッドとして世界中で使われている。レゴは、玩具を超えて、思考のインターフェースになっている。
2026年、レゴは 「LEGO SMART Play(レゴ・スマートプレイ)」 という新しい遊びのプラットフォームを投入する。これは単なるギミックではなく、玩具の根幹である「ブロックで遊ぶ体験」にデジタルの応答性を組み込んだ革新だ。
中心となるのは、これまでのレゴブロックとまったく同じ形状の中に、センサー、LED、スピーカー、無線通信機能などを内蔵した「LEGO SMART Brick(スマートブリック)」だ。このブロックは単独で光や音を出すだけでなく、周囲の動きや他のスマートパーツとの関係を感知し、リアルタイムに反応することができる。たとえば、飛行機のおもちゃを持ち上げるとエンジン音が鳴り、戦闘シーンではライトや効果音が出るように設計されている。しかも重要なのは、これがスクリーンやアプリの操作を前提としていないことだ。デジタル技術はブロックの中に「溶け込んで」おり、子どもがタブレットやスマートフォンを手にする必要はない。ブロックそのものが、遊び手の動きに応じて反応するインタラクティブな相手になるのだ。
第1弾として発表されているのは、スター・ウォーズをテーマにした3つのSMART Playセットで、2026年3月1日に世界各国で発売される予定だ。
『SMART Play: Darth Vader’s TIE Fighter(75421)』
『SMART Play: Luke’s Red Five X-Wing(75423)』
『SMART Play: Throne Room Duel & A-Wing(75427)』
これらにはそれぞれ SMART Brick、SMART Minifigure、SMART Tag が含まれ、スター・ウォーズの世界観を生き生きと再現するサウンドやライト、物語的な反応が楽しめる。たとえばタイ・ファイターならエンジン音やレーザー音、X-ウイングなら補給音や戦闘音が自動的に鳴り、シーンに合わせて光が変化するよう設計されている。
この取り組みは、90年代のデジタル挑戦とは根本的に違う。あの頃、レゴはスクリーンの中の体験を追い求めすぎて、本来の遊びから離れてしまった。だがSMART Playは、デジタルをブロックの体験そのものに埋め込み、スクリーンレスのインタラクティブ性を付与するというアプローチだ。デジタルを「外に出す」のでなく、「フィジカルな遊びの中に織り込む」。これこそ、レゴが過去20年かけて磨いてきた「手で考える遊び」の延長上にある新しい進化なのだ。