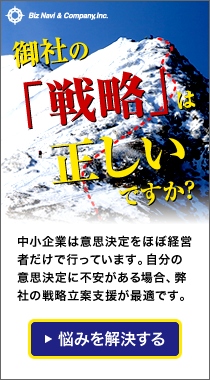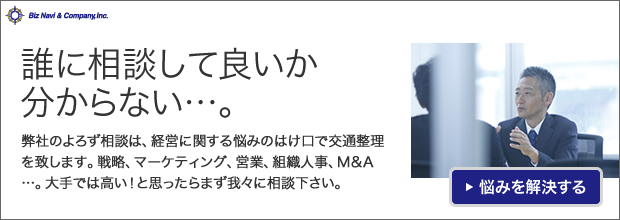早嶋です。約1.8万文字と最近の中でも長いので、簡単にサマリを示す。
(サマリ)
昔は、良いものを作れば勝てた。今は違う。顧客の日常に入り込み、提供サービスは使われ続け、支払いが耐えない仕組みを持つ企業が圧倒的な勝者だ。企業は顧客の使用ログを取り続け、それらを活かして更に、顧客の利便性をあげるための価値を提案する。そのような企業は、将来キャッシュフローが増加するため企業の価値は上がり株価が上がる。その株価を武器に、関連する周辺事業を買収して更に経済圏を広げる。業界の境界は薄れ、通貨に近い領域(決済・ポイント・信用)の奪い合いが始まる。そして次は、AIがロボットとして現実世界にインストールされ、経済圏の端末にシフトする。そこで問われるのは「技術があるか」ではない。「顧客経済の主権」を持てるかだ。持てなければ、技術は称賛されながらも部品として組み込まれるのだ。
(顧客接点を重視する企業が勝ち続ける)
今後、大企業の勝ち方は変わる。正確に言えば、企業が「何を取りにいくか」が激変している。かつては、良い商品をつくり、良い機能を積み上げ、その結果として売上を伸ばすことが王道だった。もちろん、いまでも商品は重要だ。しかし近年、成長している企業の多くは、商品そのものよりも先に「顧客とのつながり」を最重要KPIに置いているように見える。
ここで言う顧客とは、単なる会員数やユーザー数のことではない。顧客の生活の中で、あるいは現場の仕事の中で、その企業が提供する仕組みが使われ続けている状態のことだ。使われ続けるということは、支払いが継続し、使用ログが蓄積され、それが改善に回され、さらに周辺の価値提供へと拡張されていくということを意味する。企業は、顧客の時間と習慣、そして最終的には財布の中に入り込むことを目指しているのだ。
では、なぜ企業はそこまでして「顧客を取りにいく」ようになったのかだ。それは、顧客との関係性を起点にしたビジネスモデルが、構造的に、従来の製品ビジネスよりもはるかに強い成長カーブを持つようになるからだ。この差を生んでいるのが、ハードとソフトの性質の違いだ。ハードの事業は投資に対して比例して売上が伸びる。売上は台数×単価に縛られ、製造能力、在庫、物流、販売網がボトルネックになるからだ。一方でソフトは、一度作り上げれば、コピペ(複製)して通信で届けるコストがほぼゼロに近い。限界費用がほとんどかからないため、同じ仕組みを多くの人に配るほど利益率が上がりやすく、成長のカーブも比例ではなく自乗に近づいていく。
さらに重要なのは、ソフトは「売り切り」である必要がないことだ。むしろ使用を前提に提供し、サブスクや従量課金に寄せることで、顧客が実際に問題を解決している瞬間、つまりリトルハイアを合理的に観測できるようになるのだ。売り切りの商品を買ってもらって終わり、ではない。使ってもらい、使われ方を観測し、改善し、さらに価値を足す。その循環が回り始めると、顧客の問題解決は深まり、関係性は強くなる。顧客にとって利便性が高く、その商品から離れる必要はなくなる。従って企業は、一定の売上が計画的に見込める。そのため企業は次の価値提供を計画的に設計できるのだ。だからこそ「商品を売る」よりも先に、「顧客を取りにいく」企業が増えているのだ。
その結果、こうした企業は将来のキャッシュフローを高い確度で見通せるようになる。顧客が離れず、使われ続け、そこから新しい価値が生まれ続ける構造を持っているからだ。だから資本市場は、その企業の将来に高い期待を置き、株価も高くなるのだ。次に起きるのは、株価の差だ。顧客を取りにいく企業の株価は高くなりやすい。市場が見ているのは「今の売上や利益」よりも「将来のキャッシュフロー」なのだ。そして、将来のキャッシュフローを最も確度高く見積もれるのは、すでに顧客の習慣と財布を握っている企業だ。
サブスクの企業が評価されるのは、売上が毎月積み上がるからだけではない。リトルハイアの情報を持ち、その情報を使って、顧客あたりの価値提供を増やせるからだ。顧客が何に困り、どう使い、どこで離脱し、何が刺さるのか。これがわかれば、改善も、追加提案も、金融の設計もできる。改善が回ればさらに継続率が上がり、継続率が上がればLTVが伸び、LTVが伸びれば株価が上がる。株価が上がれば資金調達が容易になり、買収も仕掛けやすくなる。これが勝利の方程式になっている。
そしてここが重要だ。高い株価は「結果」ではなく「武器」になることだ。株価が高い企業は、ロールアップで周辺領域を取り込める。ここで言うロールアップとは、株式交換や買収を通じて、周辺の企業や技術を次々と自社の中に取り込んでいく成長戦略のことだ。株価が高い企業は、自社の株を通貨として使い、現金をあまり使わずに他社を買うことができる。技術やノウハウを買い、顧客接点を買い、規制対応のチームすら買う。そうすると成長の速度が上がり、さらに株価が高くなる。資本市場が成長の燃料を供給し、企業がそれを使って領域を拡張する。だから、顧客を取りにいく企業は、ますます勝ちやすくなるのだ。
(産業の境が曖昧になり独自の経済圏が誕生する)
今後、産業の境が曖昧になるのは当然だ。昔は「銀行は銀行」「通信は通信」「小売は小売」だった。しかし顧客の財布と習慣を握る企業は、顧客の問題解決に必要な周辺領域へ事業を拡大する。決済を握ればローンができる。ローンができれば保険ができる。保険ができれば投資ができる。投資ができれば、購買の入口としてのECや広告が欲しくなる。広告が欲しければ、検索やOSが欲しくなる。こうして、領域が連鎖するからだ。
つまり、企業は「隣の産業に進出している」のではない。顧客の問題解決を軸に、連続させて取り組んだ結果、産業の境界線の上を超えてしまっていたのだ。境界が消えるのではなく、昔の業界人が考えた境界の意味が変わるのだ。顧客の生活は一つであり、顧客の財布も一つだからだ。
産業の境が薄くなると、次は「通貨」に近い領域の奪い合いが勃発する。ポイント経済がその典型だ。ポイントは割引のように見えて、実態は経済圏の通貨だ。貯まる、使える、交換できる、優遇条件が変わる。ここに信用が乗ると、実質的な通貨にさらに近づく。この構造が、最も早く、かつ大規模に可視化されたのが中国だった。
中国の話になると、よく「社会信用システム」という言葉が出てくる。少し物々しく聞こえるが、実態はもっと現実的な仕組みだ。中国では、たとえば裁判で「お金を返しなさい」と命じられたのに、それを無視し続ける人がいる。そのような人たちは「失信被执行人」と呼ばれ、一定のリストに載る。すると、高額な飛行機のチケットが買えない、ぜいたくなホテルに泊まれない、といった制限がかかる。要するに、「約束を守らない人は、経済活動がやりにくくなる」仕組みが、制度として組み込まれているのだ。
ここでよくある誤解は、「中国では国民一人ひとりに点数がつけられている」というイメージだ。しかし実際には、ひとつの巨大なスコアがあるわけではない。裁判所のリスト、税務のリスト、規制当局のリストなど、いくつもの行政データが連動して、「この人は信用できるかどうか」を判断する仕組みになっている。つまり中国では、信用が道徳ではなく、経済条件として扱われ始めている。信頼できる人は自由にお金を使え、約束を破る人は不利な条件を受ける。その違いが、決済や移動や消費の場面で、実際の制約として現れるようになっている。
この事例が示しているのは、信用が単なる評判ではなく、「お金の使い方の条件」として社会に組み込まれ始めたという事実だ。約束を守る人は自由にお金を使え、守らない人は使いにくくなる。つまり、信用は通貨の潤滑油として機能し始めている。この構造を企業の視点で見ると、ひとつの結論に行き着く。人の行動を左右するのは、商品ではなく、お金の流れそのものだということだ。
だから、ポイントや信用が通貨の潤滑油として機能し始めると、企業は決済、つまり顧客の財布を取りにいく。決済を握れば、顧客の支出の全体像が見える。支出が見えれば、金融条件(分割、ローン、保険料率、与信)を変えられる。条件を変えられれば、顧客の行動そのものを誘導することもできる。ここまで来ると、競争は「良い商品」ではなく、「良い通貨」に近づく。だから、ポイントとデジタル通貨の取り合いが始まり、すでに始まっているのだ。
(覇者は経済圏を構築する)
ここまでの流れをみれば、ひとつの結論が見える。これからの覇者は、国を取りにいくのではなく、「経済圏」を取りにいく。国境は、法律や税金、通貨の単位としては残る。しかし人々の行動は、すでに国境を越えて動いている。旅行を予約し、商品を買い、動画を見て、仕事をし、お金を払う。その多くは、ひとつのプラットフォームの中で完結している。そこに「どこの国の会社か」という感覚は、ほとんど関係なくなりつつあるのだ。
いま人々が実際に生きているのは、「国」の中というよりも、「サービスの中」だ。Amazonの中で買い物をし、Appleの中で支払い、Googleの中で検索し、Pay PayやLineの中で会話と送金をする。私たちは知らないうちに、それぞれの経済圏の中で生活しているのだ。だから、これから企業が取りにいくのは、領土のような地理的なエリアではない。人々の生活のまとまり、つまり「生活圏」そのものだ。ある決済で動く生活圏、あるOSで動く生活圏、あるプラットフォームで完結する生活圏。企業は、その単位で世界を取りにいく。その結果、企業は自然と総合サービスになっていく。買い物、決済、保険、ローン、コンテンツ、移動、仕事が一つの仕組みの中に集まる。そしてその中心にあるのが、通貨、つまり決済とポイントと信用だ。人の行動を束ねる力は、最終的にそこに集まってくる。
(中国の事例とDX国家)
理解を深めるために、中国の金融大手2社を見てみよう。一般に語られるのは、Alipay(Ant Group)と、WeChat Pay(Tencent)だ。
Alipayは、もともとはネット通販の支払いのための仕組みだったが、そこから送金、ローン、投資、保険へと広がり、中国人の「お金の出入り」のほとんどを通過させる存在になった。一方のWeChat Payは、チャットアプリであるWeChatの中に組み込まれ、人と人の会話の中で自然にお金が動くように設計されている。両者に共通しているのは、QRコードを入口に、買い物、送金、公共料金の支払い、タクシー、飲食店、ECまでを一つのアプリの中に取り込んだ点だ。多くの中国人にとって、財布よりもスマートフォンの方が重要な存在になっている。
これは単なる利便性の話ではない。決済が日常の中に入り込むと、それは単なる支払いの仕組みではなくなる。誰が、いつ、何に、いくら使ったかという記録が、すべてそこに集まるからだ。そこに信用の情報が重なると、社会の動きそのものが、その仕組みの中で見えるようになる。ただ「監視」という言葉だけで片付けると、議論が雑になる。実際は、不正や詐欺、踏み倒し、契約違反のコストを下げるために、信用とデータを使う局面が確かにある。裁判所の判決を無視する債務者に対して、一定の高額消費や移動に制限をかける、といった設計は、その典型だと思う。
更に視点を拡げて、国家単位の事例を見てみよう。デジタルで仕組みをアップデートした事例はいくつもある。エストニアは、電子IDとデジタル署名を軸に、行政手続きをオンライン化してきた国として有名だ。Smart-IDやMobile-IDのような仕組みは、本人確認と電子署名の土台を提供し、オンラインでの契約と行政サービスを成立させる。
デンマークも強い。行政とのやり取りをデジタルポスト(Digital Post)に寄せ、公式な通知を電子的に受け取る前提を整えている。これは「紙をなくした」ではなく、「行政と国民の通信路を再設計した」ことを意味する。
シンガポールはSingpassが象徴だ。単一のデジタルIDで政府・民間のサービスへアクセスできる設計を徹底し、本人確認の摩擦を極端に下げた。その結果、口座開設、契約、行政手続きが一つの動線でつながり、「誰であるか」と「何ができるか」がデジタル上で一体化した社会ができている。
インドはAadhaarを軸に、銀行口座(Jan Dhan)とモバイルを組み合わせたJAM構想を語り、補助金の直接給付(DBT)などで漏れや不正を減らす文脈がある。ここも賛否はあるが、「ID×口座×通信」で国家の給付配管を作り直した点が大きい。
ヨルダンではSanadが「政府サービスの入口」として統合され、数百の行政手続きや公共サービスにつながる設計が進んでいる。国民は、どの役所のサービスかを意識することなく、ひとつの入口から国家とやり取りするようになっている。
アイスランドでも、island.isを中心に公共サービスの入口が統合され、行政のデジタル基盤が組み替えられつつある。そこでは、役所の縦割りよりも、「市民が何をしたいか」を起点にした動線が優先されるようになってきている。
こうして見てくると、国家のDXと企業のDXは、実は同じ場所を目指していることがわかる。誰が人を識別し、誰が支払いを通し、誰がその行動を記録するのか。その設計を握った側が、生活の流れを握ることができるのだ。
(企業の事例)
いくつかの企業の事例を見ると、更に解像度が上がってくると思う。アントグループ、衆安保険、ウィーチャット、ペイペイ、アップルとグーグル、アマゾンをみていこう。
●Ant Group
まずアントグループ(Ant Group)だ。アリペイ(Alipay)を入口に、資産運用(Yu’e Bao)や与信(花唄・借唄など)に広がり、信用(Zhima Credit)にまで手を伸ばした流れは、生活金融の統合モデルとして象徴的だ。支払い、貯蓄、借入、そして信用が、ひとつのアプリの中でつながったとき、「銀行に行く」という行為そのものが不要になる。
もう少し丁寧に見ると、Antの強さは「金融商品が揃っていること」ではない。順番と接続の設計が巧いのだ。入口はAlipay、つまり決済だ。決済は毎日使う。毎日使うから、顧客の行動ログが溜まる。行動ログが溜まるから、特定の顧客の与信の精度が上がる。与信ができると、分割や小口ローンの審査が瞬時に判断可能になるのだ。ここで重要なのは、ローンが特別な取り組みではなくなることだ。従来の金融は、銀行に行き、書類を書き、審査を待つ。しかし生活金融では、支払いの延長として与信が動く。花唄(Huabei)のような後払い・分割は、買い物の文脈で自然に組み込まれる。借唄(Jiebei)のような小口借入も、アプリの中で完結してしまう。
さらにYu’e Baoのような資産運用が重なると、給与や売上の残高がそのまま運用に回り、資金が効率的にキャッシュを生んでくれる。つまり、決済のお金が貯蓄や運用と自由につながるのだ。Zhima Credit(芝麻信用)は、興味深い。日常の取引における互いの手間を減らすための仕組みなのだ。顧客の信用が高ければ、デポジットが不要になり、手続きが簡素になり、条件がよくなる。日常の決済で普通に支払い、普通にサービスを利用している人の信用高いが、何らかのペナルティや違反を続ける人は企業にとってコストだ。そのような人の信用は下げるのだ。その結果、信用は人格の評価ではなく、経済的な条件になるのだ。
こうして決済、運用、与信、信用がひとつながりになると、Antが握っているのは金融商品ではなくなる。顧客の支払いを入口に、生活の取引コストを低減し、顧客の行動ログをベースに、より快適なサービスを提供することを実現する。生活金融の統合モデルとは、結局、これらを実現したモデルなのだ。
●衆安保険
保険の文脈では、ZhongAn(衆安保険)が象徴的だ。ZhongAnは、いわゆる既存の保険会社とは少し違う位置に立っている。オンライン専業保険として設立され、対面営業や紙の契約を初めから想定していない。保険を「売る商品」ではなく、「行動に紐づくサービス」として設計してきた点がとても特徴的だ。
その成り立ちを見ると、ZhongAnが何を狙っていたのかがよくわかる。株主には Alibaba、Tencent、そして保険大手の Ping An が名を連ねる。テック企業と金融企業が、最初から一体となって設計された保険会社なのだ。ZhongAnが提供してきた保険は、長期の生命保険や複雑な商品ではない。ECで商品を買ったときの配送保険、旅行に出たときの短期保険、スマートフォンの破損保証といった、行動の発生点に紐づく小さな保険が中心だ。ユーザーは「保険に入る」という意識すら持たないまま、気づけばリスクがカバーされている。
ここで起きているのは、保険の役割の変化だ。従来の保険は、将来の不安に備えるために、あらかじめ契約するものだった。一方、ZhongAnの保険は、行動の結果に自然に組み入れられる。買う、送る、移動する、使う。その一連の流れの中で、リスクだけが切り出され、最小単位で保険がかけられるのだ。
この設計が可能になった背景は、プラットフォームが行動ログを持つ前提だ。誰が、いつ、何をしたのかがわかっているから、リスクを細かく分解できる。その結果として、保険料は小さくなり、不正や過剰なコストも抑えることができる。保険は、特別な金融商品ではなく、生活の些細なリスクを減らす部品になるのだ。
ZhongAnの事例が示しているのは、保険単体の革新ではない。決済、EC、移動、通信といった生活の入口を握るプラットフォームの上に、保険をどう載せるかという問いへの一つの答えだ。金融とテクノロジーが接続するとき、保険は「売るもの」から「自動的に組み込まれるもの」へと姿を変える。その変化が、ここの事例では、はっきりと可視化されている。
●TencentとPayPay
Tencent側の中核にあるのが Tencent の WeChat だ。WeChatは、もともとはチャットアプリとして普及した。しかし中国では、チャットが単なる連絡手段にとどまらなかった。日常の会話が集まる場所は、そのまま生活の入口になり得るからだ。
WeChatの強さは、アプリの中にさらにサービスを内包した点だ。ミニプログラムと呼ばれる仕組みは、いわば「ダウンロード不要のアプリ」だ。飲食店の予約、配車、行政手続き、EC、ゲーム。必要な機能が、会話の中で完結してしまう。ユーザーはアプリを離れて探す必要なない。会話アプリの動線の中に、サービスが埋め込まれているからだ。
その中心を流れているのが WeChat Pay だ。支払いが会話アプリと同じ場所で完結すると、決済もストレスがなくなるし、簡単に支払いができる。勿論、誰が、どの文脈で、何にお金を使ったかが自然に蓄積される。チャットがOSになり、ミニプログラムが市場になり、決済と結びつく。これらが揃ったとき、WeChatは単なるアプリではなく、生活インフラになった。
日本でこれに最も近い位置にあるのが PayPay だろう。PayPayも、決済だけで完結することを目指していない。ポイントを軸に利用頻度を高め、ミニアプリ的な仕組みでサービスとの接点を増やし、金融や投資の文脈へと広がりつつある。
象徴的なのが、PayPayが Binance Japan に出資したという動きだ。これは単なる暗号資産への関心ではない。決済を握ったプレイヤーが、「次の通貨」「次の価値の保存手段」に橋渡しをすると考えると、非常にわかりやすい。
WeChatもPayPayも、目指しているのはスーパーアプリという言葉そのものではない。日常の入口を押さえ、支払いを通し、そこから金融やサービスを自然に拡張していくことだ。決済を中心に据えた経済圏が、確実に形を取り始めている。
●AppleとGoogle
Apple と Google は、生活金融の統合をOS側から進めている。両社に共通するのは、決済アプリを前に出すのではなく、OSそのものに金融と生活の機能を溶け込ましていく取り組みだ。
Appleの場合、その象徴がApple Walletだ。Walletは、クレジットカードを入れる場所にとどまらない。鍵、チケット、搭乗券、身分証といった「生活に必要な証明書」をまとめて収納する場所になりつつある。財布というより、生活の中で使う権利や資格を管理する箱に近い。
決済側でも同じことが起きている。Apple Payは、支払うか否かだけを扱う仕組みではなくなった。サブスクリプション、分割払い、継続課金の管理など、支払いの前後に発生する体験そのものが、OSの中に吸収されていく。ユーザーは「どのサービスで払っているか」を意識しなくなる。
Googleも同様だ。Google Walletは、単なる支払い手段から、取引履歴、各種パス、移動や利用の記録をまとめる器へと広がっている。支払いの結果として生まれるログを、検索や地図、広告と結びつけられる点で、Walletは生活のログを受け止める基盤として位置づけられている。
AppleとGoogleのアプローチは、WeChatやPayPayとは少し違う。彼らは決済から経済圏を広げるのではなく、OSという日常の前提条件の中に、決済と金融を組み込んでいる。その結果、生活の入口はアプリではなく、最初からOSになるのだ。
●Amazon
Amazon は少し毛色が違うように見えるが、構造は同じだ。Amazonは決済アプリやOSを入口にしたわけではない。入口にしたのは「購買」と「物流」だった。
Amazonが強いのは、誰が、何を、どれだけ売り、どのくらいの回転で資金が動いているかを、マーケットプレイスの中で正確に把握している点だ。販売データ、在庫回転、レビュー、返品率。事業者の実力とリスクが、ほぼリアルタイムで可視化されている。
だからこそ、Amazonは Amazon Lending のような形で、出店者向けの資金供給に踏み込める。従来の金融機関が見るのは、決算書や担保だ。一方Amazonが見ているのは、日々の売上と資金の回転そのものだ。
売上の実績と回転を観測できる主体が金融に入ると、審査と回収のコスト構造が根本から変わる。貸せるかどうかを判断するための書類は要らない。売れているか、回っているか、それだけでいい。回収も、次の売上から自動的に行えるからだ。
ここで起きているのは、金融の内製化ではない。購買と物流という生活インフラの延長線上に、金融が自然に組み込まれているだけだ。Amazonもまた、商品を売る企業から、事業者の経済活動そのものを支えるプラットフォームへ移している。
ここまでの企業を眺めると、共通点ははっきりしている。商品を売るのではない。顧客の行動と支払いが発生する場所を起点に、リトルハイアの情報を取り、それをベースに周辺の問題解決へ拡張していくのだ。だから産業の境があいまいになり、決済から通貨の主導権争いが始まり、経済圏を作りにいく争いになっているのだ。
(AIと物理ロボットが融合する世界)
ここまで見てきた議論は、すべて「人の行動がどこでデータ化され、どこで決済と結びつくか」という話だ。決済、ID、OS、購買、移動。人が画面の中で行う行動は、ほぼすべてログとして蓄積、金融や信用と結びつけて活用されている。2026年のCESを俯瞰すると、その構造がいよいよ画面の外に出ていく兆しがある。AIはアプリやクラウドの中に留まらず、ロボットという形で物理的な世界で登場する。CESの公式発信でも、ヒューマノイドを含むロボティクスは周辺テーマではなく、次の主戦場として扱われている。
ここで重要なのは、「ロボットの性能がどれほど高いか」ではない。ロボットが、現実世界における経済活動の端末になるという点だ。現場の仕事、家庭内の作業、移動、物流、介護、清掃。これらはすべて、これまで人が担ってきた行動であり、同時に必ず支払いと結びつく行為だ。
ロボットがそれらを担うようになると、やはり売り切りのハードとしての提供は薄まり、使用を前提に配備され、稼働状況や成果が常時ログとして記録されるだろう。そのデータをもとに、対価が決まり、保険やリース、融資といった金融商品が重ねられていく世界が想像できる。つまりロボットは、労働を助ける機械とともに、やはり金融と経済圏を保管する仕組みになるのだ。
この世界を理解するには、ロボットメーカーの理解だけでは不足する。重要なのは、これら全体を脳、体、神経、学習機能、運用、そして支払いと、誰がどう束ねるのかになる。その役割分担を6つに分けて整理すると、今後のプレイヤーの立ち位置が見えやすくなると思う。
●脳(AI)
まずは、脳(AI)をつくる企業だ。ここで言う脳とは、単なる認識AIではない。言語を理解し、状況を判断し、物理世界での行動に結びつく意思決定の中枢を指す。
現時点での中心は、OpenAI、Google DeepMind、そして NVIDIA だろう。OpenAIは汎用モデルをロボット制御へ拡張し、DeepMindは強化学習と世界モデルの文脈で物理行動を扱ってきた。NVIDIAは少し立ち位置が違うが、AIの脳と身体を同時に設計できる点で特異だと思う。
NVIDIAが Isaac GR00T N1 をヒューマノイド向け基盤モデルとして提示し、シミュレーションや合成データ生成まで含めた枠組みを出してきたのは象徴的だ。単にモデルを作るのではなく、「どう学習させ、どう現場に出すか」までを一気通貫で押さえにきている。ただし、この領域はまだ勝者が固定されたとは言い切れない。ワンチャンが十分に残っている。
たとえば Tesla。自動運転で蓄積した世界モデルと実走データを、人型ロボットに転用できるポジションにいる。Metaも無視できない。基盤モデルと強化学習、シミュレーション環境を内製し、オープン寄りの戦略で研究者を囲い込んでいる。Microsoft はOpenAIとの関係を軸に、クラウドと実装の側から脳を支配しにいく立場だ。
中国勢も厚い。Baidu は自動運転と大規模言語モデルを結びつけ、Huawei は独自チップとAI基盤をセットで押さえにいく。研究色が強いところでは、Anthropic や Mistral AI のようなプレイヤーも、汎用モデルの別解を提示し続けている。さらに視野を広げると、Boston Dynamics AI Institute のように、ロボット前提で脳を鍛える研究組織もある。大学発やスピンアウトも含めると、名前が知られていないプレイヤーが、特定用途では一気に抜ける可能性も十分ある。
この層の特徴は明確だ。単体で勝ち切るというよりも、「どの身体」「どの運用」「どの経済圏」と結びつくかで、価値が何倍にも跳ね上がる。脳だけでは完結しないからだ。従い、まだ勝敗は決まっていないのだ。
●身体(ロボット)
次に、身体(ロボット)を量産配備する企業だ。ここで問われるのは、デモの完成度ではない。大量に作れるか、壊れたときに直せるか、安全に現場へ出せるか。そのすべてを同時に満たせるかどうかだ。
名前が挙がりやすいのは、Boston Dynamics、Agility Robotics、Tesla、Figure AI といった企業だ。それぞれ強みは違うが、共通しているのは「研究室を出て、現場に出る」ことを明確に意識している点だ。ただし、この領域にはまだ確定覇者は見えにくい。理由は単純で、最後に勝敗を分けるのが、AIの賢さではなく、量産、保守、安全という現実だと思うのだ。ロボットは壊れるし、転倒する。更に現実空間では人と交わるため、事故の責任も問われる。この現実を乗り越えられる企業は、まだ限られている。だからこそ、この層はワンチャン勢が最も多い。
たとえば Agility Robotics は、倉庫という用途に絞り、人と同じ空間で動く前提を徹底している。Figure AI は、設計をシンプルに保ち、量産と外部連携を強く意識した戦略を取っている。Tesla は、車で培った量産、サプライチェーン、保守の知見を、そのまま人型に持ち込もうとしている。
中国勢も無視できない。UBTECH、Unitree、Fourier Intelligence などは、完成度よりもスピードとコストを優先し、実地配備を前提に動いている。制度や社会実装の許容度が高い環境では、こうした企業が一気に前に出る可能性がある。
さらに視野を広げれば、産業ロボット出身の企業が、人型に転用してくる可能性もある。FANUC、ABB、KUKAのように、量産と安全を知り尽くした企業が、本気で参入してくれば、風景は一変すると思う。
●製造
3つ目は、すでに工場を押さえている企業だ。ここは一気に現実寄りだ。FANUC、安川電機、ABB、KUKA、オムロン。彼らはすでに製造現場に深く入り込み、ロボット本体だけでなく、制御、保守、更新という長いサプライチェーンと歴史と経験を保持している。
この層の強みは、技術の先進性ではない。現場で現在進行系の稼働を続けていることだ。既存の生産ラインに組み込まれ、保守網を持ち、SI(システムインテグレーター)のパートナーを抱えている。つまり、長い時間軸で既に「動かし続ける責任」を引き受けているのだ。AIロボットが広がれば広がるほど、既存の自動化ラインや制御システムとの統合は避けて通れない。そのとき、この層の価値は下がるどころか、むしろ爆上がりだ。
ABB が OmniCore のような制御基盤を打ち出し、デジタル接続やソフトウェアアップデートを前提にした設計へ寄せているのも、その文脈で理解できる。ロボット単体ではなく、「工場全体をどうアップデートするか」を視野に入れているのだ。
また、協働ロボットの文脈も重要になる。Universal Robots のように、人と同じ空間で動き、現場の周辺作業へ自然に入り込むプレイヤーは、AIロボット時代のタッチポイントとして存在感を持つ。完全自動化ではなく、段階的な置き換えが進む現場では、こうしたロボットが最初の入口になる。
どれだけ賢い脳や新しい身体が生まれても、既存の工場や現場とつながらなければ、経済圏はつくれない。だから、すでに現場を押さえている企業は、AIロボット時代においても、重要な機能として拡大しつづけると思う。
●ロボット用コンピュータ(神経)
4つ目は、ロボット用コンピュータ(神経)を供給する企業だ。ここで言う神経とは、単なる演算性能ではない。センサーからの情報を受け取り、判断し、身体へ指令を返す。その一連を、どれだけ速く、安定して、安価に実現できるか。その能力が、ロボットの性能とコストを根本から左右する。
中心にいるのは、やはり NVIDIA だ。GPUに加え、Jetsonのようなエッジ向けプラットフォームを揃え、学習から推論、シミュレーションまでを一気通貫で押さえている。ロボット向けにNVIDIAが強いのは、単に速いからではない。開発者が「とりあえずこれを使えば動く」環境を用意しているからだ。
ただ、この層もNVIDIA一強で固定されているわけではない。Qualcomm は、低消費電力と通信を強みに、ロボットを動き続ける端末として捉える立場だ。Intel は、産業用途や既存システムとの親和性で巻き返しを狙っている。AMD は、GPUとCPUの統合設計でコストと性能のバランスを取りにいくだろう。孫さん一押しのArm は、自ら作らず、設計思想を世界中に配ることで、神経の標準を握ろうとしている。
さらに重要なのが、エッジAI勢だ。Hailo、Edge Impulse、Graphcore のように、「学習はクラウド、判断は現場」という前提で最適化された企業は、用途次第で一気に存在感を増す可能性がある。日本でも、ソニーのイメージセンサー系技術や、ルネサスの産業向けSoC(システム・オン・ア・チップ:コンピュータに必要な機能を1つの半導体にまとめたもの)など、部分最適では強いプレイヤーがいる。
この層が重要なのは理由がはっきりしている。ロボットはクラウドだけでは動けない。遅延が許されないからだ。通信が切れても止まってはいけない。安全が最優先されるからだ。そのため、判断の多くは現場、つまりエッジで完結する必要があると思っている。
つまり、神経系を握る企業は、ロボットが「どれだけ賢く」「どれだけ安く」「どれだけ安全に」動けるかを決めてしまうのだ。脳と身体の間に位置しながら、実は全体の制約条件を支配する。この層は地味に見えて、極めて戦略的な立ち位置の企業になる。
●シミュレーション/デジタルツイン(学習)
5つ目は、シミュレーションやデジタルツインなどの学習機能の企業だ。この層が重要になる理由は単純だ。ロボットを現場で一体ずつ人が教えていたら、絶対にスケールしない。2000年代初頭、PCと制御装置を配線で繋いでファームをアップしたことがある。最悪の経験だった。勿論26年移行は、一定人間のように何らかのミスや失敗や事後があれば、そこから学習するなどの機能は必須だろう。ただ、いちいちリアルの場で行っていたら、今度は結構な割合で事故が多発して導入を見送る状況が想像できる。
だから学習は、まず仮想空間で行われる。現実とほぼ同じ物理法則、摩擦、重さ、衝突を再現した環境で、何千回、何万回と失敗させる。そして現場では、最後の微調整だけを行うのだ。この仮想で鍛え、現実で仕上げる前提が、ロボットの普及を現実のものにするのだ。
この学習の工場を押さえる企業も強くなる。その象徴が NVIDIA だ。NVIDIAがGPUやSoCだけでなく、OmniverseやIsaac Sim(NVIDIAが提供するロボット向けの学習環境)といったシミュレーションの枠組みまで含めて語るのは、計算力だけでは勝てないことを理解しているからだ。学習環境を押さえた者が、脳と身体の進化速度を決めるのだ。
ただ、この層もNVIDIA一強ではない。Unity は、ゲームエンジン由来の強みを活かし、物理シミュレーションとインタラクションの設計で存在感を持つ。Epic Games(Unreal Engine)も、フォトリアルな再現性とデジタルツインの文脈で産業用途へ広がっている。Siemens や Dassault Systèmes のような産業系プレイヤーは、製造ラインや設備のデジタルツインを長年扱ってきた経験を持つ。
ワンチャン勢も多い。Ansys のようなCAE(コンピュータ支援エンジニアリング)系は、物理の精度で強い。Covariant のように、学習データそのものを資産として積み上げる企業も出てきている。大学発やスタートアップも含めれば、特定用途に最適化した学習環境で一気に抜ける可能性は十分ある。
ロボットの賢さは、現場ではなく、現場に出る前の学習量で決まるというのが面白いところだ。本番前に、どれだけ多くの失敗をさせるか。その失敗を、どれだけ安く、安全に、速く回すか。そこを支配する企業が、ロボット経済圏の進化速度を握るのだ。
●通信や運用
最後は、通信や運用を担う企業だ。この層は完全に技術の凄さから離れる。問われるのは、ロボットを何台作れるかではない。100台、1000台、1万台と増えたときに、止めずに回し続ける必要がある。
ロボットが普及すると、次は運用が重要になる。ログを集め、状態を監視し、ソフトウェアを更新する。異常を検知した場合、止めるべきときは止めないといけない。事故を未然に防ぎ、起きた場合は記録を残し、責任の所在を整理する。そして、それらを保険や契約、規約に落とし込む作業も必要になる。この一連が回らなければ、どれだけ優れたロボットも、現場では使い続けることはできないい。
中心にいるのは、AWS、Microsoft Azure、Google Cloud といったクラウド事業者だ。彼らは計算資源を提供しているだけではない。ログの集約、デバイス管理、セキュリティ、アップデート配信といった「止めない運用」の型をすでに持っている。
通信キャリアも重要になる。ロボットは常にクラウドにつながっている必要はないが、つながるべきときには確実につながらなければならない。低遅延、冗長性、切断時のフェイルセーフ。こうした条件を満たせる通信インフラを持つ企業は、ロボット経済圏の裏側で不可欠な役割を担う。
さらに、この層には運用ソフトウェアの企業が入ってくる。デバイス管理、遠隔監視、ログ分析、セキュリティ対応。これらは派手ではないが、現場では最も信頼される部分だ。ロボットが「いつ壊れたか」よりも、「なぜ壊れなかったか」を説明できることが、導入の条件になる。
この層の価値は、規模が大きくなるほど増していく。ロボットが数台なら、人が見張れる。数十台でも何とかなる。しかし数千台を超えた瞬間、人の目は役に立たなくなる。そこで初めて、通信と運用の設計が、経済圏の土台として効いてくる。この運用層は地味だ。だが極めて重要だ。
もちろん、ロボットは必ず壊れる。運ぶ人も、直す人も必要になる。ただし重要なのは、その作業を誰がやるかではない。誰の指示で、誰の契約のもとで、誰のデータとして行われるかだ。現場は分散するが、運用は一つに束ねられる。その設計を握った側が、経済圏を支配する。
国内で考えると、この「束ね役」はまったくの新規プレイヤーから生まれるというより、すでに現場と地域を持っている企業が担う可能性が高い。たとえば、ソフトバンクのような企業は、自ら現場に出ることはないが、通信、認証、課金、契約という基盤を持っている。ロボットが増えれば増えるほど、どのロボットが、どこで、どの条件で動いているのかを一元的に把握する必要が出てくる。そのとき、ローカルの保守会社やSIを個別に管理するのではなく、ネットワークとして束ねられる企業が前に出てくる。
一方で、地場のインフラ企業がその役割を引き受ける展開も十分にあり得る。電力、ガス、石油化学といった企業は、すでに「止められない設備」を長年運用してきた。24時間体制、安全管理、行政との調整。ロボットの運用に必要な感覚は、実はこうしたインフラ運用と近い。ロボットが社会に溶け込むほど、こうした企業が担う役割は自然に広がっていく。
さらに、メーカー系やプラント系の企業も見逃せない。彼らはすでに、設備の定期点検や部品交換、長期保守契約をビジネスとして成立させてきた。ロボットは彼らにとって未知の存在というより、「動きが増えた設備」に近い。既存の保守ビジネスの延長として、ロボットの運用を引き受ける余地は大きい。
ここで再び重要になるのは、誰が油をさすか、誰が部品を運ぶかではない。それらの行為が、どの契約に紐づき、どのログとして蓄積され、どの責任分界のもとで実行されるのかだ。現場はローカルに分散していく。しかし、その上位にある運用の設計は、一つに束ねられていく。その構造を設計できた企業だけが、ロボット時代の経済圏を現実のものにするだろう。
(機能で売り続ける企業の近未来)
ここで今回の議論を再度、もう一段抽象化してみよう。長く日本を支えてきた事業は、機能を磨き、性能を売ってきた企業群だ。光学、精密機械、素材、センサー、制御。世界最高水準の技術を持ち、真面目に作り、壊れにくく、正確に動く。そうした企業は確かにすごい。
しかし、その強さは、いまの潮流の中では、対極に置かれてしまう。なぜなら、機能を軸にしたビジネスは、どうしても「売った瞬間(ビックハイア)」で完結しやすいからだ。良い製品を作り、販売し、代金を受け取る。顧客がその後どう使い、どこでつまずき、何に満足したか。つまりリトルハイアの積み重ねには、構造的に関与しにくい。
市場がいま評価しているのは、そこではない。評価されているのは、顧客の財布と習慣を握り、使用を通じて関係を深め、将来のキャッシュフローを自社の中に積み上げていける企業だ。売上の大きさよりも、関係の継続性。単発の販売よりも、使われ続ける設計。その差が、企業価値の差になっている。
ところが、機能重視の企業ほど、販売や顧客接点を子会社や代理店に委ねがちだ。製品は自社のものでも、使用ログは手元に残らない。顧客が何に困り、どこで離れ、どこで感動したかが見えない。結果として、技術は自社にあるのに、顧客経済の主権を持てない状態が続いている。そして、その致命的な欠陥に気づいていないのだ。
この構造は、資本市場から見ると非常に分かりやすい。優れた技術を持つ、信頼できる企業。しかし、顧客を束ねる力は弱い。将来のキャッシュフローは読みにくい。そうなると、評価はどうしても「頃合いの良いハードメーカー」に落ち着いてしまう。買収しやすい部品供給者、あるいは機能提供者として見られるのだ。
プラットフォーム側の視点に立つと、これはさらに明確になる。彼らにとって、優れた技術は喉から手が出るほど欲しい。しかしそれは、顧客を連れてくる価値だからではない。あくまで、自分たちの経済圏を強化するための機能や部品として見ているのだ。だから、技術は称賛される。しかし、評価の中心にはならない。残酷だが、これが現実だと思うのだ。
(まとめ)
最後に、全体を振り返ろう。今回も何日かに分けて書いたので、自分のなかの復讐の意味も含めている。今回のブログは、技術が負けたと言う話ではない。ましてや、技術の価値が消えた話でもない。変わったのは、価値の置き場所だ。
かつて価値は、機能の中にあった。より高精度に、より速く、より安定して動くこと。それ自体が価値だった。しかし今、価値はそれだけでは完結しない。価値は、顧客の生活の中に置かれるようになった。顧客が日常の中で使い続けること。毎日の中で使われ、習慣として定着し、そして最終的には財布の流れの中に入っていく。価値は、そうした場所へと移っているのだ。
だから企業は、「良い商品を作る」だけでは足りなくなった。商品より先に、顧客を取りにいく。顧客との関係性を先に設計する。顧客を取りにいく企業は、将来のキャッシュフローを増やすことが可能だ。すると、株価が高くなり、株価が高いから、ロールアップで周辺領域を取り込むことを続ける。そうして事業は拡張し、結果として産業の境界が曖昧になっていく。
境界が曖昧になると、次に争点になるのはポイントや決済、デジタル通貨だ。つまり誰が顧客の財布を握るのかという競争だ。覇者は国境そのものを取りにいくわけではない。経済圏を取りにいく。中国や各国の国家DXは、その未来がすでに始まっていることを示している。
そしてCES 2026が示唆しているのは、その経済圏が、ついに物理世界へ伸びてくるという兆しだ。AIは画面の中から出ていき、ロボットとして現場や家庭に入り込む。ロボットは単なる機械ではなく、支払いと接続される経済圏の端末になる。労働と金融、物理とデータが、そこで重なり始める。
この流れの中で、機能を軸に強さを築いてきた企業は、どう生きるのか。誰と組むのか。プラットフォーマーが国境を簡単に越えていったように、機能を軸に戦ってきた企業も、まもなく選択を迫られる。今回書いてきた経済圏の中で、下流工程として組み込まれるのか。それとも、上流の一部として接続されるのか。
極めて戦略的な議論だと思う。そしてこれは、従業員1,000人から2,000人規模以上の企業にとって、もはや無視できない世界になってきている。