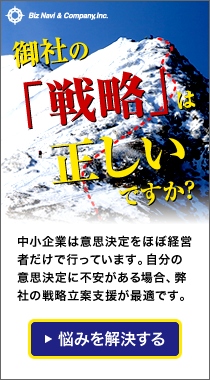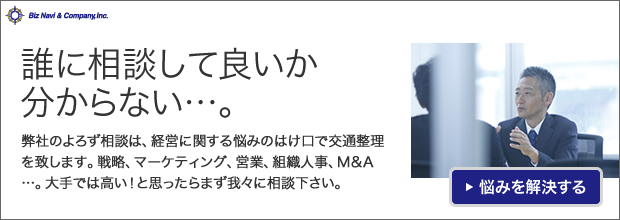早嶋です。約5100文字。
ここ十数年で、日本のあちこちに「子ども食堂」が展開されている。はじめに「子ども食堂」という言葉が広く知られるようになったのは、2012年に東京都大田区の八百屋さんが始めた取り組みだと言われる。八百屋の店先で、近所の子どもたちに安く、あるいは無料でご飯を食べてもらう。それが新聞やテレビで取り上げられ、「自分たちの地域でもやってみよう」と動く人たちが現れた。そこから広がった。消費者庁の調査では、現在活動している子ども食堂のうち、活動開始が2011年以降の団体が約98%を占めている。つまり、子ども食堂は、ここ10年から15年のあいだに生まれ、まだ新しい現象なのだ。
(数で見る「子ども食堂」の爆発的な増え方)
子ども食堂の数は、まさに右肩上がりだ。複数の調査をつなぎ合わせると、だいたい次のようになる。
2012年頃:全国で十数か所から数十か所程度。まだ「知る人ぞ知る」活動。
2016年:319か所
2017年:2,286か所
2018年:3,718か所
2019年から2020年頃:5,000〜6,000か所と推計。
2021年:7,363か所
2022年:9,132か所
2024年度の調査:10,867か所と報告。
公立中学校の数(約9,200校)を比較するとイメージが湧くだろう。十数年前まではほとんど存在しなかった活動が、「全国どこに行っても、探せば近くに一つはある」レベルにまで広がっているのだ。子ども食堂は、もはや一部の熱心な人だけのチャレンジではなく、新しい形の社会インフラだと言って良いと思う。
(平均的な「子ども食堂」の姿)
「子ども食堂」のスタイルや運営をイメージしてみる。農林水産省が行ったアンケートでから、開催頻度の分布をみてみる。
●月に1回から2回のペースで開催:全体の4割程度
●週に1回から2回開いている:約2割
●ほぼ毎日のように開いている食堂:ごく少数
1回あたりの参加人数も、そこまで多くない。平均すると、子どもが約15人、大人が約23人で、合計38人程度だ。中央値は31人なので、「子どもが20人前後いて、大人が10人程度利用している」という光景が、典型的な子ども食堂のイメージだ。
参加費も、かなり抑えられている。子どもの参加費は平均134円で、中央値は100円。つまり、100円玉を1枚だけ持ってくれば食事ができる設計だ。そもそも子どもは「無料」のところも多く、アンケートでは、半数以上の食堂が「子どもは無料」と答えている。一方、大人の参加費は平均310円、中央値300円で、こちらもコンビニ弁当より安い。
場所は、公民館や地域センター、自治会館、寺や教会、飲食店の定休日、企業の社員食堂、学校の家庭科室や給食室などが使われている。10食から20食程度の小さなところもあれば、100食以上を用意する大規模なところもあるが、30人から50人前後が集まる中規模の食堂が全体のイメージに近い。
整理すると、平均的な子ども食堂とは、「月1回から2回、多くても週1回から2回ほど開き、1回あたり子どもが20人前後、大人も含めて30人から40人ほどが集まる。子どもは100円か無料、大人は300円程度で食べられる場所」ということだ。
(年間のコスト)
このインフラは、年間どれくらいのお金で支えられているのかを想定してみた。全国の子ども食堂を支援する「むすびえ」が行った大規模な調査では、9,132か所の子ども食堂のデータから、全国全体で1年間に動いているお金が推計されていた。人件費を除いた運営費用(食材費や消耗品費、家賃、光熱費など)の総額は、約216億円(21,632,725,395円)だという。これを1か所あたりに割ると、平均で約236万円/年になる。
人件費の勘案が無い。つまりボランティアで成り立っているので、仮にボランティアの労働を、最低賃金ベースで「お金に換算」してみた数字を出してみた。同じ調査をベースに計算すると全国で約349億円という金額になった。1か所あたりで見ると、約380万円/年だ。つまり、子ども食堂は、現金としては年間236万円ほどの原材料費等と380万円相当のボランティア労働がかかる構造だ(ただし、ここには調理器具や設備投資の減価償却は含まれていない)。
1回あたりの直接費は、参加人数によって大きく違う。参加者が10人から20人規模の食堂では、1回の開催で使うお金の中央値は約6,000円。21人から30人だと約15,000円、31人から50人だと約26,000円、51人から100人で約57,000円、100人を超える大規模食堂になると、1回あたり約88,000円とされている。
ここに、場所代などがさらに加わるので、「子ども一人あたり100円」ではとうてい賄えないことがよくわかる。
(事業として成り立つのか?)
子ども食堂を「事業」として捉えたとき、どこまで自立できるのかを考えて見よう。分かりやすくするために、いったん人件費をゼロ、つまり「すべてボランティア」と仮定して考えてみる。
典型的なケースとして、1回あたり30人程度(子ども20人+大人10人)が参加し、月2回開催する食堂をイメージする。先ほどの中央値を参考にすると、1回の開催で必要な直接費は15,000円から25,000円程度だ。月に2回開催すれば、合計で3万から5万円になる。
一方で収入はどうか。子どもが20人来て、1人100円を払うと2,000円。大人が10人来て、1人300円を払うと3,000円。合わせて1回あたり5,000円。月2回で1万円の収入になる。そうすると、毎月2万から4万円は赤字になり、その分を寄付や助成金、食材の寄付などで埋める必要がある。年間で見ると、24万から48万円の不足だ。
もう少し規模が大きく、40人から50人が参加し、月4回開催している食堂を考えてみると、毎月のコストは10万から20万円程度になる。参加費収入は、大人も含めて月2.8万円ほど。ここでも、月あたり7万から17万円、年間にすると80万から200万円を、外部の資金で補わなければならない計算になる。
この数字を見ると、「子ども食堂単体を、参加費だけで成り立つビジネスにする」という発想はほぼ不可能だと分かる。もし参加費を本気でコストに見合う水準まで上げるなら、子どもは500円、大人は800円から1,000円といった価格設定が必要になるだろう。しかし、それをやってしまうと、そもそもの目的である「貧困対策」や「孤食対策」とは矛盾してしまう。来てほしい家庭ほど来られなくなるからだ。
従い、現実には、子ども食堂は「事業」というより、「マルチな資金を束ねた社会的な取り組み」として成立している。公的な補助金、企業からの協賛金、ふるさと納税の仕組み、地域住民や企業からの寄付、フードバンクやスーパー・農家からの食材寄付、さらには宗教施設や自治会館の無償提供、こうした資源を総動員することで、ようやく年間200万から300万円の活動プラス、そこに関与する人のボランティアで回っているのが実態なのだ。
(立地のパターンと可能性)
子ども食堂の立地を考えるとき、いくつかの典型的なパターンがある。
一つは、企業の社員食堂を開放する形だ。すでに厨房設備が整っており、衛生管理の体制もある。余った食材や、社食の仕込みの一部を活用することで、食材コストを抑えることもできる。職住近接のオフィスであれば、社員の子どもがそのまま立ち寄ることもできる。企業にとっては、地域貢献(CSR)と、社員のワークライフバランス支援を同時に実現できるモデルだ。ただし、オフィス全体のセキュリティ設計や、社員以外の人の出入りをどう管理するか、といった課題は残る。
次に、学校の調理室や家庭科室、給食室を放課後に活用するモデルがある。すでに子どもたちは放課後も学校にいる。多くの自治体では、放課後子ども教室や学童保育が学校の敷地内で行われている。ここに子ども食堂が組み合わされると、「仕事で帰りが遅い家庭の子どもが、学校でそのまま宿題をして、晩ご飯も食べてから帰る」という形が実現できる。孤食の問題にも直接的に効いてくる。ただ、学校現場の教職員の負担をどう抑えるか、教育委員会や自治体との調整をどう進めるか、という別のハードルがある。
現状もっとも広く使われているのは、公民館や地域センター、自治会館、寺や教会といった、地域の公共空間だと思う。ほとんどの自治体には、こうした場所が何らかの形で存在する。調理室がついているところも多い。高齢者サロンや趣味のサークル、地域の会合といった活動とも組み合わせやすく、子どもだけでなく、地域の大人や高齢者も一緒になって食卓を囲む場を作りやすい。ただし、人気のある公民館ほど利用枠の競争が激しく、使用料も1回数千円から数万円かかることがある。自治体がここを「子ども食堂優先枠」として位置づけ、料金や利用条件を優遇するような制度設計をすれば、さらに広がる余地は大きい。
最後に、ゼロから専用拠点をつくるモデルもある。空き店舗や古民家を改修して、「子ども食堂+学習スペース+地域カフェ」といった複合施設にするやり方だ。昼間は一般向けのカフェとして営業し、夕方から夜にかけては子ども食堂として開放する。場合によっては、コワーキングスペースやフリーランス向けのオフィス機能を備えることも考えられる。こうした専用拠点は、まちの「顔」となりやすく、ブランドも育てやすい。ただし、初期投資や家賃の負担が大きく、運営もそれなりに複雑になる。ここまで来ると、もはや子ども食堂単体というより、「ソーシャルビジネス拠点」の一機能として子ども食堂を位置づける発想が必要になってくる。
(インフラとして成熟した先の税金投入の可能性)
ここまで見てきたように、子ども食堂はすでに「新しいインフラ」としての姿を見せ始めている。全国で1万か所以上あり、多くの地域で、子どもだけでなく大人や高齢者も含めた「居場所」となっている。貧困対策、孤食対策、見守り、高齢者との交流、食育、さらには学習支援や相談窓口など、担っている役割は多岐にわたる。
ここまで役割が広がると、次の問いが浮かぶ。「これは、市民活動としてだけでなく、公共サービスとしても位置づけるべきではないか?」という問いだ。日本は、どうしても「公務員が直接やる仕事」が前提になりがちだが、子ども食堂のような取り組みは、民間やNPOが主体となり、行政が資金や制度面で支える、という形の方が相性が良い分野だと思う。行政がすべてを自前で抱え込むのではなく、地域のNPOや市民団体を「パートナー」として位置づける。その代わり、税金を一定程度投入し、継続性を担保する。
その前提として、本来の公務員の仕事も見直す必要がある。今の行政は、膨大な事務作業やルール運用に多くの時間を費やしている。これを、AIやロボット、デジタルツールにどんどん移していく。会計処理、申請書のチェック、補助金の事務、統計の集計、こうした仕事は機械の方が得意だ。逆に、人間にしかできないのは、子どもの表情の変化に気づくこと、一人ひとりの事情を聞き取ること、地域の信頼関係を紡ぐことだ。
もし自治体が、「人手が必要な支援は人がやる。それ以外は徹底的にデジタル化する」という方針を本気で掲げるなら、子ども食堂のような取り組みに税金を振り向ける余地は十分に出てくるはずだ。
(まとめ)
子ども食堂は、十数年前にはほとんど存在しなかった。しかし今では、全国で1万か所以上が活動し、年間236万円の現金と380万円相当のボランティア労働で支えられている。参加する子どもは平均で1回あたり15人前後。大人も含めると30人から40人が集う。参加費は子ども100円、大人300円程度。数字で見ると、どれだけ「無理をして」成り立っているかがよく分かる。
それでも、このインフラを支えているのは、地域の人たちの「子どもを見守りたい」「一人で食べる子を減らしたい」という思いだ。その思いに、これからどこまで制度が追いついていくのか。NPOや市民活動としての自律性を残しながら、公共サービスとしても位置づけることができるのか。
子ども食堂をめぐる数字を追いかけていると、日本のこれからの福祉や教育、地域社会のあり方が、そのまま縮図として見えてくる気がする。ここから先をどう設計するのかは、政治のテーマでもあり、同時に、地域の一人ひとりが考えるべきテーマでもあるのだと思う。
(早嶋聡史のYoutubeはこちら)
ブログの内容を再構成してYoutubeにアップしています。
(ポッドキャスト配信)
アップルのポッドキャストはこちら。
アマゾンのポッドキャストはこちら。
スポティファイのポッドキャストはこちら。
(過去の記事)
過去の「新規事業の旅」はこちらをクリックして参照ください。
(著書の購入)
「コンサルの思考技術」
「実践『ジョブ理論』」
「M&A実務のプロセスとポイント」