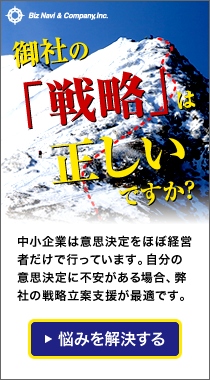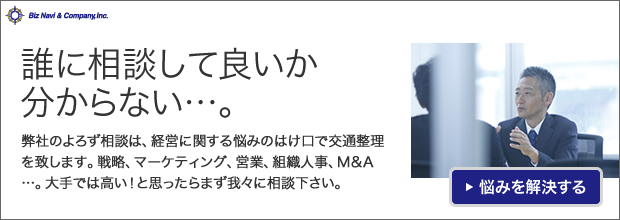早嶋です。3200字。
どうして、スマホを使って選挙をしないのだろうか。デジタルなら不正はないし、コストも下げられると思っていた。ただ、実際のところどうなのかについて、少し考察した。
現在、スマホで株も買える。ローンも組める。海外送金すら指一本でできる。にもかかわらず、なぜ選挙は、いまだに紙と鉛筆で行われているのだろうか。僕はずっと、選挙のような仕組みこそ、早くデジタル化されるべきだと考えていた。
投票用紙を刷り、投票箱を並べ、封筒に入れ、人の手で回収する。そのたびに国家予算が数百億円も動いている。この仕組みは明らかに非効率だし、コストもかかりすぎている。スマホで投票できるようになれば、時間もお金も節約できて、しかも票のカウントミスや開票作業の人為的ミスも防げるのではないかと、素直に思っていた。
さらに、テクノロジーの進歩を見れば、それは決して夢物語ではない。ブロックチェーンを使えば投票の記録は改ざんできないし、投票履歴が残っていれば監査もできる。投票システムをオープンソース化すれば、誰でも中身を確認できて、透明性も担保される。そういうふうに、「デジタル=合理的、安全、効率的」という考え方が、僕の中には自然に染みついていた。
だが、調べていくうちに、選挙という仕組みが思っていた以上に複雑で、繊細なバランスの上に成り立っていることを知った。何よりも驚いたのは、「選挙がそもそも匿名である」という前提についての理解が、自分にはまったく足りていなかったのだ。
それまで、匿名性とは単なる人権的なマナーのようなものだと思っていた。だがそれは逆だった。匿名であることこそが、選挙の自由と公正を守るために不可欠な条件だったのだ。誰が誰に投票したかがわからないようにすることで、人は圧力から解放される。
会社の上司から強要されても、家族や宗教団体から命令されても、外からは本当に誰に投票したかを確認できないからこそ、最後は自分の意志で投票できる。もし投票の中身が誰かに証明できてしまうと、それは票を売ることや、命令に従わせることを可能にしてしまう。匿名性とは、つまり「誰にも支配されない自由な選択」を保証するためにあるのだ。
ところがその一方で、匿名であるということは、自分が本当に投票した内容が正しくカウントされたかどうか、確認する術がなくなるということでもある。自分がA候補に投票したのに、開票結果ではB候補にすり替えられていても、それを証明する方法がない。
誰がどの票を入れたかを記録できないようにしている以上、個人レベルでも、第三者の立場でも、改ざんの有無を確実に検証するのが難しい。選挙という制度は、この「匿名性」と「検証性」という二つの価値を同時に成立させなければならない。これが根本的に矛盾した課題なのだ。
実際、ここが選挙をITで実現するうえで、最も根本的な難所になる。投票が匿名である以上、それが「誰のものか」を記録してはいけない。ところが、ITの世界では、「誰が」「何を」したのかがログとして明確に残ることを前提としている。送金も、契約も、ログインも、すべてはその記録性と追跡性によって成立している。だが選挙だけは、まったく逆のことを求めるのだ。
「記録はされなければならないが、個人とは結びついてはいけない」、この矛盾をどう処理するかが、選挙の電子化における最大の技術的・制度的課題なのだ。ゼロ知識証明やブラインド署名のような暗号技術を使えば、このジレンマを回避する設計は理論的には可能だ。
しかしそれらは極めて高度で、仕組みを説明しても一般市民がすぐに納得できるようなものではない。国民の理解と信頼を得ながら、この矛盾を抱えた制度を設計し、運用するには、技術だけでなく、法制度、監査、教育、文化的合意など、多層的な準備が必要になる。
この構造的な難しさは、紙でもデジタルでも変わらない。紙であれば、投票用紙をすり替えたり、廃棄したりすることができる。デジタルであれば、スマホ端末が乗っ取られていたら、本人が押したボタンと、送信された投票内容が異なるかもしれない。
デジタルの場合は、それが一人や一カ所の問題では済まず、何千人、何万人規模で同時に発生する可能性があるという点で、より構造的なリスクを内包している。つまり、票の「記録」そのものがいかに安全であっても、その「入力」が不正確であれば、結果は簡単に歪められるのだ。
「ブロックチェーンがあるから安全だ」と考えていたが、それはあくまで「正しいものが記録された」場合の話であって、そもそも不正な情報が記録されてしまったら、逆にそれが強固に残り続けてしまうという、皮肉な結果を生むことにもなりかねない。もちろん、同じような前提条件の中で、すでにデジタル選挙を実現している国もある。
エストニアだ。そこでは、有権者の半数以上がネット投票を行っている。投票は電子IDによって認証され、電子署名が施される。さらに、投票は何度でもやり直すことができ、最終投票のみが有効となる仕組みのため、仮に誰かに脅されて投票しても、自分の意志で後から修正できるようになっている。
そして何より、このe-IDという本人確認の仕組みが、医療、行政、金融、教育など、日常生活のあらゆる機能と統合されている。つまり、選挙のデジタル化が、社会のデジタル化の延長線上にある。
では、なぜ日本やアメリカでは同じようにできないのか。その理由は、一つではない。日本ではマイナンバー制度が形だけはあるものの、社会インフラとして機能していない。アメリカは州ごとに制度が分かれており、連邦単位で共通のIDや投票システムを導入すること自体が困難だ。そして両国に共通しているのは、「デジタル=改ざんされやすい」「紙=信頼できる」という感覚が根強く残っていることだ。制度の設計そのものよりも、「目に見えるものを信じたい」という文化的心理が、技術的な導入の足を引っ張っている。結局のところ、「デジタルなら不正はない」という前提は、条件付きでしか成立しないのだ。
本人認証、暗号技術、端末の安全性、改ざん検知、そして国民の理解と信頼。これらが揃って、はじめて選挙のデジタル化は「紙と同等、あるいはそれ以上の安全性と公正さ」を持つ可能性を持つ。しかし、どれか一つでも欠ければ、それは危うい制度になりかねない。
技術だけでは、制度はつくれない。透明性だけでは、信頼は得られない。匿名性だけでは、公正は担保されない。
選挙という仕組みをデジタル化するなら、それは単なる道具の入れ替えではなく、社会そのものの設計と向き合うことになるのだ。したがって、選挙制度のデジタル化を検討するのであれば、同時に、国家の根幹に関わるインフラ、たとえば国民ID制度の再設計と制度化にも踏み込まなければならない。
投票だけをデジタルにするのではなく、保険、金融、政治参加、医療保障、教育、行政手続など、生活のあらゆる場面において、本人認証と情報の真正性が保証される土台を整える必要がある。エストニアが選挙の電子化を成功させたのは、選挙だけをIT化したからではなく、社会全体を一つのデジタル構造として統合していたからだ。
そうした構想を持たずして、ただ「スマホ投票にしよう」と声高に言っても、国民の不信をかき立てるだけだろう。だからこそ、日本も今のうちから、10年、20年という時間軸で将来を構想する必要がある。
デジタル化の是非を問うのではなく、「どんな信頼設計を社会全体に築くのか」を問う発信と対話を、いまから始めなければならない。選挙は、単に票を数える作業ではない。国家と個人の信頼関係の象徴であり、それをどう支えるかという設計図こそが、僕たちの未来のかたちを決めるのだと思う。